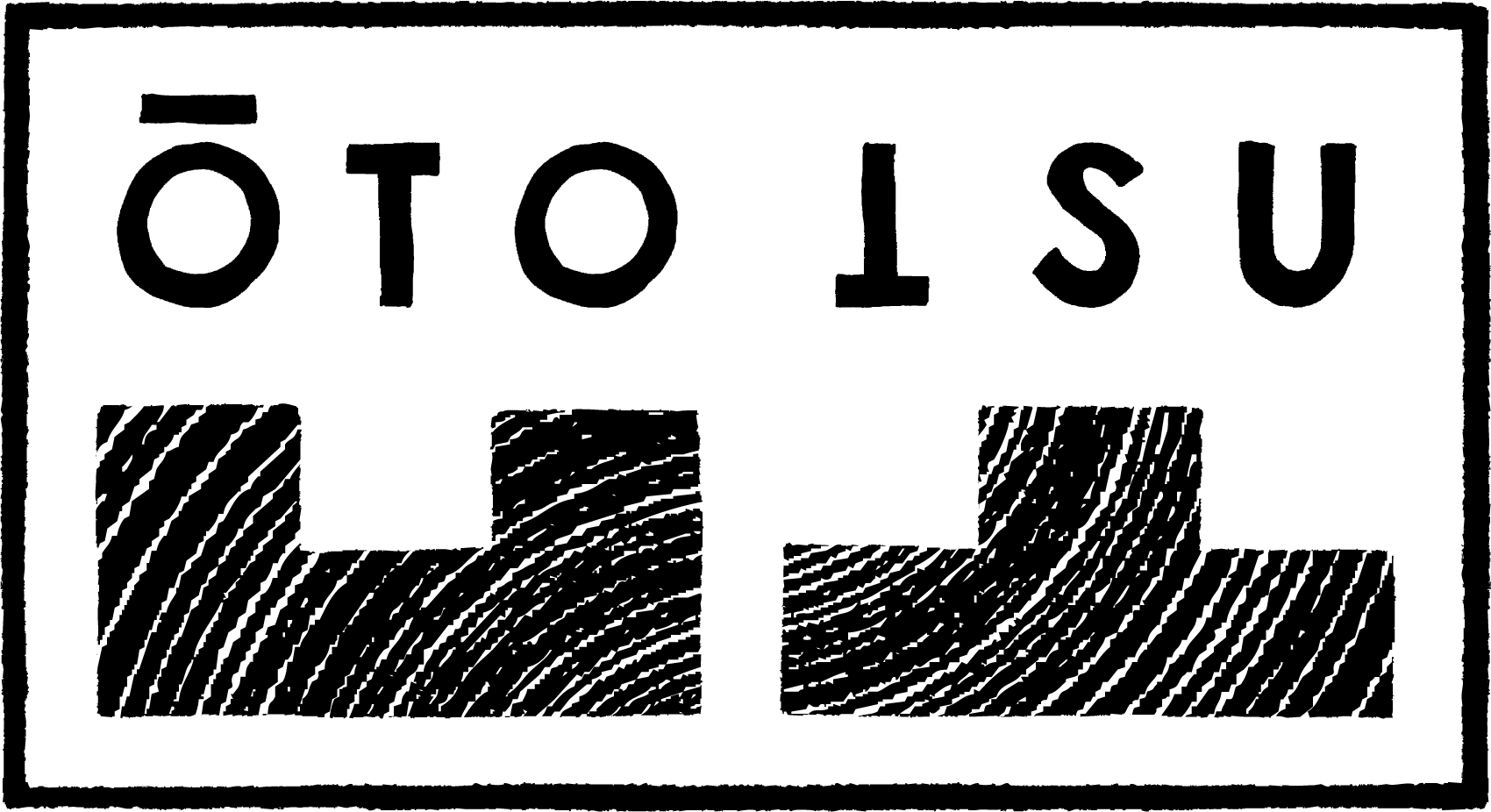トロピカル・ファンク・バンドof Tropique (=オブトロピーク)が新たに制作中のフル・アルバムには、小林ムツミ (民謡クルセイダーズ / ムンビア・イ・スス・カンデロソス)、moe (民謡クルセイダーズ)、ワダマンボ (カセットコンロス)、長久保寛之 (エキゾチコ・デ・ラゴ)、ロッキン・エノッキー(ジャッキー&ザ・セドリックス)、八木橋恒治や、クマイルスの西岡ディドリー、和泉美紀、サムット野辺、さらにUSのニューウェイヴ・ラテンの旗手であるミラマールの全メンバーやチチャ・リブレのジョシュア・キャンプといった国際的かつ多彩なジャンルでいて、それぞれを代表するミュージシャン達が参加。既存のカテゴライズに抵抗するように、まるで極彩色のおもちゃ箱のような無国籍音楽を紡ぎ出している。
“トロピカル”であり”エキゾ”であり”モンド”。この音楽をどう形容すれば良いのだろう?
その答えを求めて、オブトロピークの近藤哲平とゲスト・ミュージシャンによる対談シリーズを連載としてお届けする。
今回は、7インチ・シングルのレーベルやステッカー、アルバムのレーベル、ジャケットデザインなど、すべてのアートワークを手掛けたデザイナーYOTSことRyota Watanabeと、オブトロピークの近藤哲平による対談をお届けする。
自らもシガー・ファング(Siguah Fang)というジャンルレスのバンドで活動するYOTSと近藤の対談は、現在のライヴ現場における状況も交えて大変興味深いものとなった。
取材/構成:森崎昌太
▼第一弾はこちら▼

◆Release Infromation◆

ARTIST:of Tropique (オブトロピーク)
TITLE:Fishcake and Fortune / Here Comes Andi
LABEL:Pepei Records
CAT No:PPR-004
FORMAT:7″ Vinyl
PRICE:¥2,750(Tax in)
ARTIST:Siguah Fang (シガー・ファング)
TITLE:Natural Dreams
LABEL:Okazu Records
CAT No:OKAZU-002
FORMAT:LP Vinyl
PRICE:¥3,801(Tax in)


ARTIST:of Tropique (オブトロピーク)
TITLE:Looking For My Foot Foot
LABEL:Pepei Records
CAT No:PPR-005
FORMAT:LP Vinyl
PRICE:¥4,950(Tax in)
●もっと「何なんだろう、これ?」というミステリアスな状態にしておきたい。(Ryota Watanabe)
—— まず、今回の対談のきっかけとして、お二人のバンドが「一般的なマーケティングの視点」では非常にカテゴライズしにくいと感じているからです。一方で、ヨーロッパを中心としたDJやプロデューサー、オーガナイザーたちが提唱する「トロピカル・ミュージック」という括りがある。これは欧米では大規模なパーティーをパーマネントに開催するほどに広がる概念ですが、実際にはクンビア、スークース、アフロビート、サルサまで内包する、非常に雑多でいて実態のないものです。哲平さんは以前からこのテーマに触れていましたよね?
 近藤哲平
近藤哲平そうですね。5~6年くらい前、コロナ禍の前から「トロピカルって何だろう?」と思って、色んな人にインタビューして回っていた時期がありました。でも、結局のところ、全員「わからない」というのが結論だったんですよ。誰も定義できない。ただ、欧米で面白いバンドが出てきて、それがトロピカルと呼ばれているという事実だけがあった。
 Ryota
Ryota僕は、逆にその「トロピカル・ミュージック」というものが、もし確立されたジャンルとして固定されちゃったら、そこに参加するのはちょっと違うなと感じてしまうんです。
—— なるほど。
 Ryota
Ryotaどこかに属したくないという感覚があるんです。常に「はみ出し者」でありたいというか。そういうカテゴライズできない人たちが、便宜上「あえて名付けるならトロピカル」と呼ばれているのかなって気もする。僕自身の音楽に「トロピカル」という言葉を使うのは、実はものすごく違和感があるんです。だって、そんなに明るい音楽じゃないから(笑)。
 近藤哲平
近藤哲平それはわかります。でも、CDショップの売り場や配信プラットフォームでは、どうしてもジャンルを書かなきゃいけない。いつも悩みますね。
 Ryota
Ryota友達に「どんな音楽やってるの?」と聞かれた時に説明するのも難しい。だから僕は夢や絵のストックを貯めておいて、それから着想して形にすると言う方法をとっています。そうすれば、ジャンルというステップを飛ばして、どんな世界観かという話ができる。
—— 世間一般の「トロピカル=明るい、ヤシの木、南国」というイメージ、その「南国の明るい音楽」というイメージを壊したいんですよ。例えば今回のオブトロピークのアルバムにも参加しているUSのニューウェイヴ・ボレロ・バンドMiramar (ミラマール)だって、底抜けに明るくはない。
 近藤哲平
近藤哲平歌詞も暗いしね。ラテンと暗さが結びつかないのは、ひょっとしたら日本独特の感覚なのかもしれない。例えば、ヴァンパイア・ウィークエンドだって「トロピカル」と言われるけれど、彼らの本質はロックですよね。結局、しっくりくる言葉がないから、ラテンより少し広い意味で「トロピカル」という言葉を借りているだけというか。
 Ryota
Ryotaそうなんですよね。トロピカルって言葉、多分ジャンルを指す言葉ではないですよね。
 近藤哲平
近藤哲平海外でそういう「トロピカル」をやってる人はジャンルレスなところもあると思うんですよ。さっき亮太くんも、外れた人がって言っていましたけど、日本でラテンとか、そういうものをやってる人はわりと専門性が高いというか。
——「ラテン」と言うと、専門性が高く、マナーを重視するイメージがありますね。
 Ryota
Ryota僕はあまり専門性を出したくない。例えばですが、ラテンの畑に自分の旗をさしたくないんです。旗をさしてしまったら、そのジャンルのマナーを完璧に学んで、より専門性を高くして、その頂点を目指すのが目標になる。それはそれでとてもかっこいいことだとは思いますしもちろん専門性の中にも謎な部分はあります。ただ、自分はそうじゃなくて、もっと「何なんだろう、これ?」というミステリアスな状態にしておきたい。種明かしをしちゃうと、つまらなくなるじゃないですか。だから、本当はこういうこともあまり言いたくはないんですけど(笑)。
——今はたしかに手の内をさらす感じにはなってますね(笑)。
 Ryota
Ryota僕はデヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライヴ』が大好きなんです。なぜこの作品が好きなのかというと、監督が内容を詳しく説明していないから。前作の『ロスト・ハイウェイ』も当然名作だし大好きですが、リンチがインタビューで成り立ちを説明しすぎちゃった。そうすると、観る側のフォーカスが固定されて、想像の余地がなくなっちゃう。もっと色んな変な想像をしていたのに(笑)。音楽も同じで、「わからない」からこそ、味のするガムのようにずっと噛み続けられるんだと思います。

——なるほど。いい話ですね。
 Ryota
Ryotaオブトロピークの音楽もどこから影響を受けたのかすべてを説明することはできないし「わからない」。多すぎるから。でもだから面白いと思う。
ただ、わからないから面白いというその聴き方が一般的かというとそうではないかもしれません。普通はただ「わからない」で終わっちゃうのかな、と。楽しみ方もわからない、”聴いたことがない”ってことを楽しめないから。聴いたことのある音楽を聴きたいんですよ、みんな。
——そうかもしれないですね。
 Ryota
Ryotaソウルやファンクを参照したポップスって、やっぱり聴いていて気持ちがいいですよね。耳馴染みのあるコード進行だし、ホーンがパッと入ってくるだけで、初めて聴く人でも一気に盛り上がれる。 ただ、そういった「音楽の聴き方」が世の中に定着しすぎているというか……僕たちが面白いと思う「わけのわからないもの」がなかなか浸透していかない一因なのかなとも思うんです。だから僕も音楽を作る時、あえて分かりやすいコード進行を入れて、キャッチーにしてみようと意識することもあります。
——なるほど。
 Ryota
Ryota僕はスライ・マングース (SLY MONGOOSE)というバンドが大好きなんですけど、彼らの音楽って後期になるにつれてどんどんわけがわからなくなっていくんですよ(笑)。でも初期にはすごくキャッチーな曲があって、今でもそれが人気だったりする。あの曲たちがどういう意図で作られたのか、狙ってキャッチーにしたのかは、いつか聞いてみたいです。
●これをきっかけに、今回のアルバムに参加してくれたミュージシャンの音源を掘ってくれたり、この対談を読んでシガー・ファングを聴いてくれたりして、世界が広がればいいなと。(近藤哲平)
 近藤哲平
近藤哲平オブトロピークは、わりとキャッチーだと思わない?
 Ryota
Ryotaキャッチーだと思います。土台にファンクがしっかりありますよね。
 近藤哲平
近藤哲平それもあるけど、僕が管楽器プレイヤーだからというのも大きいかもしれない。歌モノが好きなので、自分でも「歌えるような音」を出したい。実は今回のアルバムではほとんどソロを吹いていなくて、ほぼメロディーだけ。ライヴでは盛り上がればやるけど。今回も録り終えてから「さすがにソロがなさすぎるかな」と思って、”TOTEM”という曲に後からアドリブを少し足したくらい。基本的には、僕自身がキャッチーなものを好むプレイヤーだということ。あえて「キャッチーにしよう」と考えて作ってはいる。
 Ryota
Ryota僕も、自分が好きなものは全部キャッチーだと思って生きてきたんですけど……振り返ってみると「あ、これって世間的にはキャッチーじゃないんだ」と気づかされることがあって。
——マニアックだったのか、と?
 Ryota
Ryotaそう、自覚がなかったんです(笑)。以前DJをやった時、ジミ・テナー (Jimi Tenor)の曲をかけたんです。基本的にはいろんなジャンルを流そうという趣旨のイベントだったので。そうしたら他のDJから「これは難しすぎて分かりませんね」と言われてしまって。「えっ、これカッコよくないですか?」って、思って、すごくショックで。
 近藤哲平
近藤哲平僕らはその点、自分らがマニアックだってことを自覚しています。「この人にはシガー・ファングを薦めても響かないだろうな」とか、相手を見て判断する知恵がついている(笑)。
 Ryota
Ryota僕もようやくここ数年で、その自覚が芽生えてきました(笑)。
—— お二人の共通点として「インストゥルメント(インスト)」であるという点があります。ただ、一般的なインスト・バンドとは構造が少し違いますよね。
 近藤哲平
近藤哲平そうですね。一般的なインスト・バンドって、テーマがあって、そこから各楽器のソロ回しになって、ビートはずっと一定……というポピュラーなフォーマットがあるじゃないですか。でもその聴き方って、ポップスの聴き方とは全く別物だと思うんです。 僕はポップスが好きだから、オブトロピークの曲は短く、レコーディングではマニアックなこだわりやソロを排除して、できるだけ「3分のポップス」にしたい。
—— 確かに、曲がコンパクトですよね。
 近藤哲平
近藤哲平長く演奏しようと思えばいくらでもできます。でも、普通に聴いている人が「今のギター変だな」「このピアノ面白いな」とふと感じた時に、そこから何かに繋がってほしい。これをきっかけに、今回のアルバムに参加してくれたミュージシャンの音源を掘ってくれたり、この対談を読んでシガー・ファングを聴いてくれたりして、世界が広がればいいなと。それが人生を少し豊かにすることだと思うんです。
 Ryota
Ryotaインストって、どうしても「楽器の巧さ」に注目が集まりがちじゃないですか。でも僕は、巧さだけじゃなくて、曲の「へんてこりんさ」や「不思議さ」にフォーカスしたい。まあ、自分が楽器をそこまで巧く弾けないからっていうのもあるんですけど(笑)。あと、本当にへんてこりんな人たちからしたら我々の音楽も全然普通だとおもいますが!
 近藤哲平
近藤哲平そういう観点で、好きなインスト・バンドはいるの?
 Ryota
Ryotaやっぱりスライ・マングースですね。日本のインスト・バンドで「これだ!」と思った最初の人たちです。当時の僕はレッド・ホット・チリペッパーズやレイジ・アゲインスト・ザ・マシーン、リンプ・ビズキットといったミクスチャーを聴いていたのに、どうしてあれが自分にささったのかはよくわからないのですが。そういったミクスチャーを聴いていた中に、一つポンってスライ・マングースが放り込まれてきた時の「よくわからない」感覚がすごく好きでした。その感覚を音楽をやっていく上で大切にしているところもあります。
——なるほど。原風景みたいな感じですね。
 Ryota
Ryotaちなみにシガー・ファングのアルバムでは、スライ・マングースのターボーさんがパーカッションを叩いてくれています。
●結局、僕らが惹かれているのは「エキゾ」であり「モンド」なんですよね。(近藤哲平)
—— 今後の展開として、この「わけのわからない音楽」をどう広めていこうと考えていますか?
 Ryota
Ryotaやはり「イメージ」や「ファッション」の力は大きいと思います。例えばクルアンビン(Khruangbin)。めちゃくちゃインストですが、豊洲ピットでワンマンをやれる。じゃあどうしてクルアンビンが日本でもあんなに成功したかというと、あのチルな空気感とビジュアルを含めたスタイルがあったからなんじゃないかと思っていて。
—— クルアンビンのライヴに来るファン層って、実際どういう方が多いんでしょうか?
 Ryota
Ryotaやっぱり、ちょっとオシャレな感じの人が多いですよね。
 近藤哲平
近藤哲平普通にオシャレなカフェとかでかかってるもんね。
 Ryota
Ryota音楽そのものをガチガチに軸にしているわけではないけれど、「オシャレなこと」に常にアンテナを立てているような層にささっている感じがしましたね、ライヴでは。
 近藤哲平
近藤哲平僕は、音楽にはカルチャーやファッションといった「音楽以外の要素」が必要だと思っていて。レゲエやスカが残っているのは、その要素も大きいと思うし、モッズのようなスタイルもありますし。一方で、僕のルーツであるニューオーリンズ音楽が日本でそこまで浸透しないのは、ファッションやライフスタイルとしてのカルチャーが紐付いていないからだと思うんです。だからこそ、亮太くんが描くイラストのようなビジュアル・イメージが、入り口として重要になる。
—— でも、それを突き詰めすぎると「専門性」の話になって、結局は内輪ノリになってしまいませんか?
 近藤哲平
近藤哲平そうなんです。特化しすぎると、どんどんジャンルが閉じていってしまう。
 Ryota
Ryotaクルアンビンや、サプライズ・シェフも、やってる本人たちは相当マニアックなんですよ。でも、それを全面に出さず「ふわあっと」した心地よさ、いわゆるチル感に昇華できているのが良いのかなと思います。
—— 「なんかよくわからないけど、このビジュアル、この界隈は面白そうだぞ」と思わせることが大事ですよね。
 近藤哲平
近藤哲平今話していて思ったんですが、僕らがやっていることは「ニュー・ウェイヴ」に近いのかもしれない。「こういうリズムじゃなきゃいけない」という縛りはなく、とにかく「変なことをやりたい」という先鋭的な感覚。
 Ryota
Ryota確かに、先鋭的ですね。
 近藤哲平
近藤哲平以前、オブトロピークのライヴで「これはサルサですか?クンビアですか?」って聞かれたことがあって。「いや、俺も知らねえし」って困っちゃった(笑)。日本人は、何かにカテゴライズされないと安心できないところがある。
—— それは日本のコマーシャリズムの弊害かもしれませんね。
 Ryota
Ryota多分我々はそういうものにあまり拘らずに音楽を聞いてきたんだと思います。僕は元々メタルが好きで、ブラックメタルのブラストビートとか音楽そのものも好きなんですが、「なんでこんな意味不明なことを必死で練習してやってるんだ?」っていう奇妙さに惹かれたんです。だから、正統派のロックやパンクを通っていないコンプレックスが逆にあるんですよ。
 近藤哲平
近藤哲平僕は逆にメタルは全然通っていなくて、ライ・クーダーやプリンスがブラック・ミュージックやワールド・ミュージックの入口。そこからレコード屋の『ジャニス』に通い詰めて掘り下げていった人間です。
 Ryota
Ryota僕のワールド・ミュージックへの入口はヒップホップのサンプリングソースでした。アフロビートに衝撃を受けたのは、ピート・ロックがプロデュースしていたアイ・エヌ・アイが、フェラ・クティの『Water No Get Enemy』のキーボード・ソロの一瞬をループさせてサンプリングしているのを聴いた時ですね。「こんな使い道があるのか!」という驚き。そういうミステリアスな構造が、自分の音楽作りにも影響しています。確かに。
 近藤哲平
近藤哲平その「ミステリアス」さで言うと、オブトロピークは「胡散臭さ」をあえて意識しています。
 Ryota
Ryotaそれ、すごくわかります。エキゾチカやモンド・ミュージックの魅力って、まさにその「胡散臭さ」ですよね。現地の伝統音楽そのものではなく、外部の人間が勝手にイメージを膨らませて作った「偽物の南国感」。
 近藤哲平
近藤哲平そう、そこでキーワードになるのは「トロピカル」よりも、むしろ「モンド」や「エキゾ」かもしれない。結局、僕らが惹かれているのは「エキゾ」であり「モンド」なんですよね。あの『モンド・ミュージック』という本、あれはみんな読むべきですよ。
 Ryota
Ryota本当に名著ですよね。僕も1と2を持っています。メタルを聴いていた頃に古本屋で偶然手にしたんですが、当時はレコードまで辿り着けなくても、眺めているだけで面白かった。後に、それがマーティン・デニーを筆頭とする「モンド」と呼ばれる音楽の入門書だったと知るわけですが。
—— なるほど。
 Ryota
Ryota僕はキャッチーなものが嫌いなわけじゃないんです。サザンオールスターズとかも大好きですし。自分の中にある色々な感覚の一つとして「キャッチーさ」があるけれど、全体を占めているわけではない、というバランスなんです。
 近藤哲平
近藤哲平でも、『モンド・ミュージック』に出てくる音楽もかなりキャッチーですよ。あの人たちはもっと突き抜けて「アホっぽいこと」を、ある種ロックな姿勢でやっている。
 Ryota
Ryota日本だと細野晴臣さんや、SAKE ROCKがその影響をポップスに昇華していましたよね。SAKE ROCKはマーティン・デニーの曲名からバンド名を取っていますし、とてもポップでした。
—— SAKE ROCKは素晴らしいバンドでしたが、どこか「上品」な印象もありました。もっと「下世話」な面白さがあるものとは少し違うというか。
 Ryota
Ryota上品でしたね。でも、あの「変なこと」をやりつつ大衆に受け入れられるラインってどこにあるんでしょうね。
 近藤哲平
近藤哲平アカデミックになりすぎると、聴く側に「耳を育てる覚悟」を強いてしまうのかも。その点、デヴィッド・リンチはすごい。やっていることは難解で前衛的なのに、根底にものすごくポップなものがあるし、何より見かけがカッコいい。あの胡散臭さ、コラージュ感、チープなモンド感。アートに寄りすぎず、絶妙な「怪しさ」を保っている。
——お二人は曲を作る際、どういう層に届けたいといったターゲットは意識されますか?
 近藤哲平
近藤哲平僕は全く考えていないですね。
 Ryota
Ryota僕もですね。ジャンルすら考えていない。自分の好きなものをボックスに詰め込んで、後で編集して作る。たまたま出来上がったものが「トロピカル」というカテゴリーに入れられるだけで、狙っているわけではないんです。
 近藤哲平
近藤哲平僕の場合、「最終的に自分がメロディを乗せればなんとかなる」という自信があるんです。どれだけ前段階で変なことをしていても、キャッチーに仕上げられる。だから制作過程で誰かを意識することはないですね。
 Ryota
Ryota強いて言うなら、スライ・マングースの笹沼さんに「いいじゃん」って言ってもらいたい、という気持ちはあります。僕に初期衝動を与えてくれた人なので。
—— リファレンスにする特定のジャンルなどはあるのでしょうか。
 近藤哲平
近藤哲平曲によりますが、特定のものはないですね。オブトロピークに関しては、あえてラテンの専門家を一人も呼ばなかった。呼んでしまうと「本物のラテン」になってしまうから。専門外の人間が寄ってたかって作った結果、今の独特な形になったんです。
 Ryota
Ryotaあるジャンルを真っ当にやるとなると、そのジャンルが背負っている歴史や文脈まで引き受けなきゃいけなくなりますからね。たとえばビヨンセ(BEYONCE)がカントリーのアルバムを出しましたが、あれは彼女が黒人としてカントリーをやることに強いメッセージ性がある。でも、僕は性格的に音楽を使って何かを表明したり、伝統を背負ったりすることはできないなと思うんです。「日本でインストをやるなら和を取り入れるべき」みたいな考え方にも、僕はあまり乗れない。
 近藤哲平
近藤哲平和を取り入れているバンド、嫌いでしょ?(笑)
 Ryota
Ryota嫌いではないですよ(笑)そこに造詣がないだけで、キッカケがあればいずれやるかもしれない。
——専門性を突き詰めすぎると、逆に面白みが欠けてしまうこともありますよね。
 近藤哲平
近藤哲平たとえばカセットコンロスは、ジャンルがどうっていう以前にバンドとして素晴らしいわけで、純粋なカリプソが聴きたいなら、昔のマスター(巨匠)の音源を聴けばいいわけですから。
——本当にそうですね。カセットコンロスにしても、世間的にはカリプソ・バンドのイメージですが、ライヴではそれほどカリプソのマナーに縛られていない。
 近藤哲平
近藤哲平でも、マーケティング的には「キャッチーな文言」が必要になる。オブトロピークも「エキゾ・トロピカル・ファンク」なんて言っていますが、それはあくまで入り口を作るための言葉でしかないんです。結局、僕らがやっているのは「何だかよくわからないけれど、メロディがあって、どこか胡散臭くて、でもキャッチー」という音楽。このパッケージをどう面白がってもらうかですね。
——細野さんの三部作が好きな人とかには、絶対ささると思うんです。今作のアルバムは。この「トータルコンセプト」を大事にしながら、頑張って売っていきたいですね。
 近藤哲平
近藤哲平うん、頑張りましょう。
●PROFILE
of Tropique (オブトロピーク)

近藤哲平(clarinet)、田名網大介(bass)、藤田両(drums)
クラリネット、ベース、ドラムの3人によるエキゾチック・ファンク・バンド。
2018年にイラストレーターのオタニじゅんと制作したアートブック『La Palma』(オークラ出版)を発表。架空の南の島での冒険を描いた楽曲群がヨーロッパで話題となり、フランスでは2つのラジオ局で同時に特集が組まれた。
2021年より米ワシントンD.C.のElectric Cowbell Recordsから作品のリリースを続け、これまでにアメリカのみならずフランス、ドイツ、イタリア、クロアチアなど欧米各国のラジオ局で楽曲がオンエアされている。2023年のアルバム 『Buster Goes West』(Electric Cowbell Records)は複数の海外メディアで年間ベストにランクインし、Bandcampにインタビューと特集記事が掲載された。また、AppleやGimletをはじめ複数の欧米企業で楽曲が使用されている。
国内では映像作品への参加も多く、東海林毅、冨永昌敬監督作品の音楽やアパレルブランド等への楽曲提供を行う他、『彼女のウラ世界』『僕の手を売ります』などTVドラマの音楽も担当している。
2025年にはアルゼンチンの人気ミュージシャンRolando Brunoとのスプリット・シングル(Electric Cowbell Records)を発表した。