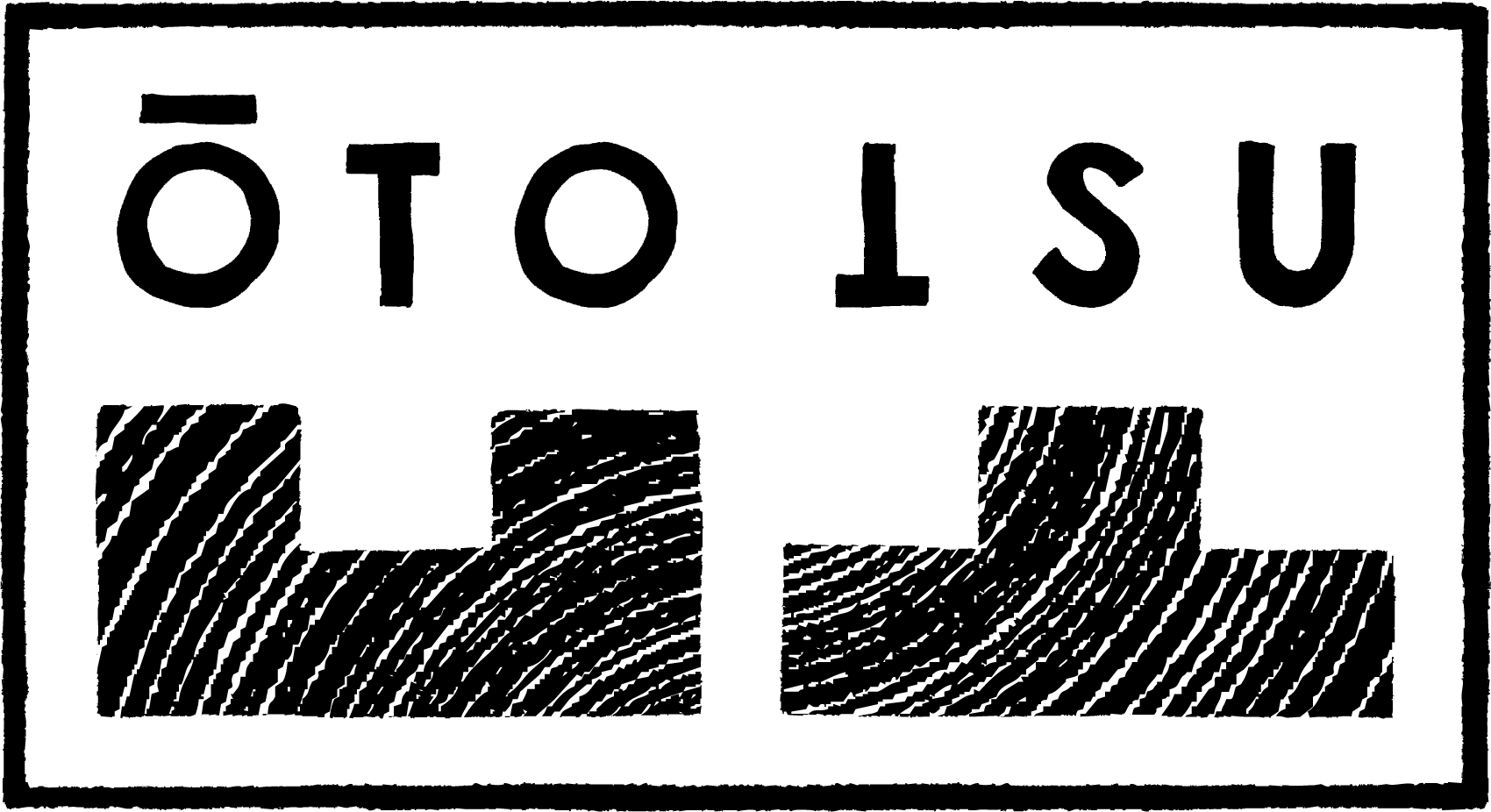Photo by:Kozaburo Sakamoto
日本のテクノ黎明期から活動を開始し、シーンが発展・多様化していく中、独自のスタンスで魅力あふれるエレクトロニック・ミュージックを紡ぎ続けた孤高の才人、スズキスキーこと鈴木隆弘。そんな彼が1993年から2006年までに発表したスズキスキー名義の全9枚のアルバムの内、原雅明と虹釜太郎が設立した気鋭レーベル〈Soup-Disk〉からのリリース作となる7タイトルがついに配信開始となった。
ケン・イシイがベルギーのテクノ名門レーベル〈R&S〉からデビューを飾り、国内でその後のシーンを牽引する幾つかの重要レーベルが設立され、「テクノの聖地」とも称されたクラブのマニアック・ラヴが青山にオープンしたのは、1993年のこと。そんな日本における「テクノ元年」に、スズキスキーはシカゴ・ハウス~デトロイト・テクノから受け取った衝撃・インスピレーションをもとに1stアルバム『Thought』を完全な自主制作で完成させ、電子音楽家としてのキャリアを歩み始める。なお、同作が2003年に〈Soup-Disk〉からリイシューされた際には、生前にスズキスキーへのリスペクト・シンパシーを事あるごとに公言していたレイ・ハラカミがライナーノーツを担当し、その音楽が孕むジャンルやテクノロジーの新規性のみには帰すことのできない魅力や特異性について、鋭く真摯な言葉を寄せている。『Thought』を皮切りとして、スズキスキーは、日本テクノの草分けレーベル〈Transonic〉主宰の永田一直とのユニットであるファンタスティック・エクスプロージョンのメンバーとしての活動もはさみながら、ハウスやテクノ、ブレイクビーツ、電子音響など様々なジャンル・音楽的意匠を取り入れ独自に換骨奪胎させつつ、精力的にアルバムをリリースしてゆく。それぞれがユニークな相貌をたたえるスズキスキーのアルバムだが、そこにはある種の抑制感や音色・構成に対する絶妙なセンス、バランス感覚など、スズキスキーの「地声」のようなものが通底して鳴り響いていて、それは当時のジャンル、ムーブメントの新規性や熱狂から遠く離れた今だからこそ、より聴き取りやすくなっているのかとも感じられる。ノスタルジーとは無縁の、古びることのないエレクトロニック・サウンドがそこにはあふれている。
スズキスキーを巡っては、今回の配信開始に先駆けて、国外で興味深い動きが起こっていたこともここに記しておきたい。昨年、UKのレーベル/エージェンシー〈Toi.Toi.Musik〉に所属する日本人DJのJunki Inoueが国産エレクトロニック・ミュージックをヴァイナルでリイシューしていくレーベル〈SAISEI〉を立ち上げ、同レーベルの第3弾作品としてスズキスキーの1stアルバム『Thought』を世界に向けてLP2枚組のフォーマットでリリースしたのである(第1弾と第2弾は日本アシッド・ハウスの先駆Kino-ModernoのEP『Into The Future』、杉本卓也の別名義COLOGNeのEP『Deep Talk』となり、スズキスキーの『Thought』には上述のレイ・ハラカミのライナーも再掲・付属する)。ブギーやシティ・ポップ、ニュー・エイジ~環境音楽、レフトフィールド・ポップなど、様々なジャンルで国外におけるジャパニーズ・ミュージックの再発見・再評価が進められてきたが、次は90年代テクノ~クラブ・ミュージックと目される向きもあり、その流れにおいても、今回の配信開始によりスズキスキーの過去作品に世界のリスナーがアクセスしやすくなるのは非常に意義深いことだと感じる。
そんなスズキスキーに、デビュー作『Thought』に始まり、〈Soup-Disk〉内に設立した自主レーベル〈LOGIC〉からドロップした『Ozma』に至るまでのキャリアを、各作品の制作背景や当時のシーン、レイ・ハラカミとの交流など振り返りながら、語ってもらった。
インタビュー・構成:藤川 貴弘
写真:Kozaburo Sakamoto
編集:三河 真一朗(OTOTSU 編集担当)
——2022年7月6日よりスズキスキーさんの作品から、7タイトルが配信開始となりましたが、それに先立ち、Junki Inoueさんが主宰するUKのレーベル〈SAISEI〉から、1st アルバム『Thought』(1993年)がアナログ盤でリイシューされました。〈SAISEI〉からはこの後にスズキスキーさんの楽曲も収録されている国内テクノレーベルの草分け〈Transonic〉のコンピ『SOUNDS OF TRANSONIC EP』のリリースも控えていますが、『Thought』がリイシューとなった経緯について教えてください。
スズキスキー(以下、SU):〈SAISEI〉からは永田一直(以下全て敬称略)を経由してお話を戴きました。90年代の日本のテクノの「再生」に特化したレーベルと聞いて正直「何ンで俺のコレなん?」感は拭い切れなかったが自分では解らない価値基準に委ねてみるのも一興かと思って。先発がKino-Modernoなのには驚きました。学生時代、AIR-CONというユニットを組んでてENDMAXで対バンしたんです。30分のアクト2回で素人コンビのギャラが各々4万円。嗚呼バブル。
—— 今作がリリースされた1993年は、ケン・イシイさんのベルギーのレーベル〈R&S〉からのデビューや〈フロッグマンレコーズ〉や〈とれまレコード〉といった国内の先駆的テクノ・レーベルの設立、青山マニアックラブのオープンなど、日本においてテクノという音楽ジャンル、ムーブメントが本格的に花開き始めていく年でもありました。スズキスキーさんは当時の状況をどのように感じていましたか?
SU:自分も同じ頃、SYZYGY RECORDSのコンピ『Believe In The Frequency Power』に参加しましたが、実は他の日本のレーベルの音楽は殆んど聴いていませんでした。レコードプレイヤーを持っていませんでしたから。今でもです。ただ、噂に聞くとやってる連中が自分と同じ1970年前後生まれが異常に多いらしく、非モテ男子達に遅れてやって来た青春時代かと勝手に妄想したりはしてました。自分は東京都北区王子にあった3D CLUB BIRTHの「DIGITAL NIGHT」にちょくちょく出させて貰ってました。「警察が来たから踊らないで座ってくれ」ッて店員に言われて皆ンな座りこんで「踊っているね?」を回避したこともありました。
—— スズキスキーさんが音楽制作を行うようになったのは、大学生時代に通っていた芝浦GOLDでのハウス・ミュージックとの出会いによるところが大きいとのことですが、どのようなところに魅力や可能性を感じたのでしょうか?また、音楽家として制作を開始するにあたり、ハウスやデトロイト・テクノなどから受けた影響をもとにしながら自分だけの表現を紡ぐために、当時どのようなことを心がけていたのでしょうか?
SU:高校時代に大好きなEurythmicsを聴きながら「あーでもこれが歌無しでもっと音も削ったら恰好いーのになー」と焦燥ったい思いをしてたのがLil’ louisの「French Kiss」でやられちゃいました。初めて行ったクラブは六本木の「THE BANK」で、Juan Atkinsの「Techno Music」がかかって「『テクノミュージック』ッつッてんよー」ッて興奮して新潮社から出た「03」ッて雑誌でデトロイトテクノという耽美な単語を知り。身も蓋も無い言い方ですが音楽的に極端に貧しい癖に極端に楽しい。貧しすぎて全然駄目だったり、変に音楽的に豊か過ぎてつまんなくなってたのも沢山ありましたが。そこら辺の匙加減だけを矢鱈気にしながら作っていた気がします。
—— 当時はどのような機材で制作をされていたのでしょうか? また、制作時に「貧しさ」と「豊かさ」の匙加減というところで一番意識されていたのは、具体的にどのような点でしょうか?
SU:YAMAHAのV50がシンセ兼シーケンサー。サンプラーはYAHAMAのTX16W。定番を絶対に使わない天邪鬼。ミキサーは初期不良のノイズが非道かったTASCAM MM100。ROLAND TB303とBOSSのディレイDD3は、SYZYGYの稲岡健に呼ばれて福岡でやったライヴのギャラ代わりの現物支給。大儲け! あとはROLAND MC202使ったくらいでしょうか。で、その音楽的貧困の快楽については、ペラペラと得意げに御開陳するようなもんじゃ無いです。Rotterdam Recordsが大好きですが、もしあの音をスペクトラム解析した奴がいたら速攻で馬鹿確でしょ。こんなの解説に値する以下の音楽ですよ。だから大好きなんです。高校時代に同級生にSex Pistolsのテープ借りて聴いて余りにも普通の音楽過ぎてがっかりした。坂本龍一の「B-2 UNIT」聴けよ。今はNintendo DS用のソフト「DS10」しか使ってません。箱のPAの人とか対バンの人とかに凄く嫌がられることがあります。自分ではエピクロスの末裔だと思ってます。
—— 翌年にリリースされた2nd『big tomorrow』(1994年)は、パッドの音色・コード感、ベースラインやビートに、メランコリックなムードやストイシズムがより強く感じられるアルバムとなっています。制作時にどのようなことを考えていたのか、教えてください。
SU:あの頃、7th系のコードが上下する曲が巷に氾濫してて、その嚆矢は808 Stateの「Pacific」だったかなと思うんですが、ちょっとだけひねりを入れたかった。引っ掛かかるところが欲しいなと。楽理的な知識は皆無なので、誠に非生産的ですが鍵盤を一音一音確かめながら試行錯誤しておりました。Dan Curtinと比較してくれる人とかいて畏れ多いことでした。
—— 2ndのジャケットに使用されている、ご自身で撮影された横須賀の海のモノクロ写真もとても印象的です。スズキスキーさんにとって、横須賀はどのような街でしょうか。また、ご自身の音楽に影響を与えているところがあるとしたら、それはどのようなものでしょうか?

SU:逆にお訊ねしたいです。クレイジーケンバンド的なドン突きの街あるいはシェンムー? シェンムー好きな音響派ドイツ人がドブ板通りに来て幻滅したとかしなかったとか……。自分にとって横須賀は「東京を俯瞰出来る距離にある無風地帯」。横浜は「色」が強過ぎ。育った家が住宅街と工業団地の境界線(8マイル!?)みたいなとこで、原発の燃料を作っている工場の脇のドブ川で全身ヘドロまみれになって遊んでました。ある意味、それはテクノでした。
—— スズキスキーさんには、ソロに加えて、日本のテクノ・レーベルの草分け的存在である〈TRANSONIC RECORDS〉主宰の永田一直さんとのユニット、Fantastic Explosionとしてのキャリアもあります。「70年代型ドラムンベース」をコンセプトとしていた同ユニットでのご活動を振り返って思うことや、そこから得たフィードバックなどについて教えてください。
SU:兎に角ライヴをやるのが愉しかった。STOCK,HAUSEN AND WALKMANとかピチカート・ファイヴの前座をやりました。ドラムンベースの要素を排除してコラージュメインでやったこともあります。敢えてここでは名を秘しますが、FEの1stは某作曲家の作品からのサンプリングのみ上物として許されるという縛りで作られました。それは最早とんち合戦で、他人と組んでやるのもたまには凄ェ面白いなと思いました。たまには。
—— 1995年の「エレ・キング」2号の日本のテクノ・レーベル特集記事「Techno Label Rebels!!」において、永田一直さんは当時のシーンのダンスフロア至上主義に対する違和感を表明していました。ダンス・ミュージックとしてではない、「リスニング・ミュージックとしてのテクノ」という感覚、可能性について、スズキスキーさんは当時どのように考えていましたか?
SU:永田のその記事は読んだことがありませんが、多分その頃、某テクノ系ミニコミ誌(DELICじゃ無いよ!)からお薦め紹介してくれと言われてフロア全無視の曲ばっかしのリスト送ったら没にされて、永田も同じ目にあったと二人で苦笑した記憶があります。WARPのArtificial Intelligenceシリーズとか、日本ではDUB RESTAURANTのコンピを愛聴してましたし、フロアかリスニングかなんて区分けはどうでもよかった。
—— 5thアルバム『Joy of Running』(1997年)から8thアルバム『Helix』(2003年)までは、原雅明さんと虹釜太郎さんが設立した〈Soup-Disk〉からのリリースとなります。『Joy of Running』はサンプリングやブレイクビーツが前景化しておりこれまでの作品とは異なる印象も覚えますが、このような変化が生じた理由について教えてください。
SU:これは架空の物語のサントラなんです。ある日の新幹線の車中で虹釜に話したのは、「未来少年コナン」的な世界の中で競われる「F-ZERO」的なレースを舞台に「あしたのジョー」的な愛憎ドラマが繰り広げられる、という設定です。それで四つ打ちは敬遠して、想像のシーンに当て書きな感じで曲を作っていきました。だから曲名も示唆的になっている筈です。
—— 6thアルバム『Message』(1999年)は、ブレイクビーツを引き継ぐトラックもありながら、抜けの良くグルーヴィなハウス、テクノ・サウンドを聴くことができます。今作ではどのようなことを目指したのでしょうか?
SU:一遍真面目にハウスをやってみたかった。Pal Joey、Kerri Chandler、Mr Fingers、レーベルだとStrictly RhythmとかNu Grooveあたりと向き合いたい。かと言って自分がそれらの「まんま」を作っても意味が無いので斜に構えて。で結句、斜に構え過ぎて毎度お馴染みのヘンテコになっちまいましたが。でも「Young Jam」は今でも好きな曲です。
—— 7thアルバム『Utopia』(2001年)は、ブレイクコアやエレクトロニカ、アンビエント~ニュー・エイジなどさまざまな音楽的意匠が独自のバランス感覚で絶妙に入り交じっている、スズキスキーさんならではの作品だと感じます。今作のリリース時にレイ・ハラカミさんは「誠実な音楽」との言葉を寄せていますが、ご自身では今作をどのように捉えていますか? スズキスキーさんの音楽のどのようなところが、ハラカミさんに「誠実」と感じさせたのだと思いますか?
SU:これはモロにハラカミ・ショックを引き摺っています。ハラカミへの返歌でもあります。「○○ッぽいものを作ろう」みたいな、何かに寄せていく姿勢が無いところが「誠実」とということなのかも知れませんが言われたこっちはもうひたすらこっ恥ずかしいだけです。
—— ハラカミさんの楽曲を聴いた時、どのようなところに「ショック」を感じられたのでしょうか?また、ハラカミさんは、過去に原雅明さんとの対談(『GROOVE』2001年4月号・5月号)でスズキスキーさんの音楽を聴くと「『うんうん。わかるわかる』って感じ」になると発言されていました。スズキスキーさんの方で、ハラカミさんの音楽やスタンスに対して、シンパシーやご自身との共通性などを感じていたところがあれば教えてください。
SU:何よりコード感。『opa*q』の1曲目が始まったら速攻で動悸が上がって、ベンド・ダウンしたとこで一旦CD止めてエロ本買いに行きました。ちょっと他には無さ過ぎた。本当に聴いたことの無い音楽でした。「こいつ絶対泉鏡花ばりの神経質野郎やろ」思って大阪で遭遇したら落差がまた凄くて。でも神経質、いや言葉が思い当たらへんけど、病的に丁寧に音を作る。個人で打ち込みする側のジャンルでここ迄作り込む奴おらへんかった。だからハラカミに評価されたのがさっぱり理解出来へんかったし今でも変な気する。外側から俺ら二人を聴いたら「フロアから乖離してる連中」に十把一絡げに回収されんねやろけどハラカミが言いたいのはそんな詰まんないカテゴライズのことやないやろ。さっぱわややねん。
—— 昨年末に、レイ・ハラカミさんの初期作品集『広い世界 と せまい世界』(2021年)がリリースされましたが、作品を聴いてどのようなことを感じましたか? また、「Skyline」(スズキスキー『Action E.P.』収録)や「きえたこい」(レイ・ハラカミ『わすれもの』収録)共作時のエピソードや印象に残っていることを教えてください。
SU:これのマスタリングやらはった山本アキヲはんが3月にお亡くなりになって……。ハラカミの告別式で初めてお会いして何遍か呑んだけどめっちゃ優しい人やってん。哀しいな。これから一杯友達が死ぬな。で、これ、ギターやベースがメインのユーモラスな音楽やから前情報無しで聴いたらハラカミやと気附く人はいない思うねんけど、時々静謐な音響の中にハッとさせられる瞬間がありますね。「Skyline」は二人の機材を同期させずに録音したので妙にヨレてます。「きえたこい」の事は……、もう思い出せません……。
—— 8thアルバム『helix』(2003年)も、シャープなビート曲からメランコリックなノンビート、アブストラクトな電子音響やフィールド・レコーディングなどさまざまなスタイルのサウンドを聴かせる作品ですが、過剰感や詰め込み感はなく、ある種の抑制感やミニマリズムに貫かれているように思います。そのことについて、ご自身ではどのようにお考えでしょうか? また、制作の背景や思い入れのある楽曲などを教えてください。
SU:厚顔無恥を承知の上で申し上げますが、YMOの『BGM』を聴いて次に『Technodelic』を聴いた時の感覚、突き抜けたあるいは突き放した感、あの感じが欲しかったんです。「take it easy」が四つ打ちやったこと無い人が初めて作ってみましたみたいな浮き方してます。
—— 2000年前後は、オウテカの諸作品に代表されるような、より抽象性や複雑性を増した音響/ビートが強い存在感を放っていた時期でもありました。スズキスキーさんは『Artificial Intelligence』シリーズもリリース時に聴かれていたとのことでしたが、その後、先鋭化していくIDM/エレクトロニカについて、どのように感じていましたか?
SU:MAX/MSPでクリックアンドグリッチなアレのことなら当時全ッ然聴いてなかったです。PsysExのアルバムは本人がくれたから聴いた。良かった。裏ジャケが枯山水で「そうそうそーゆーことよ」と独りごちた。京都で枯山水ッてベタ過ぎかなとも思ったけどこんぐらいやっちゃわないと駄目な時があるな。音は、コンピュータの音だった。実機の音じゃ無かった。だから俺の出る幕じゃ無いしそもそもこんなのをやってみたいという食指も伸びなかった。で今、確認の為にPsysExでググッたら変な痛い人の方が沢山出たけどこれもこれでいい。Autechreの「Lowride」が好きやったけどここでこの曲を挙げること自体がニカに興味無かったことの証明になってまうな。
—— 9thアルバム『Ozma』(2006)は、浮遊感あふれるノンビート曲も力強い4つ打ちも曲もありますが、ご自身で立ち上げたレーベル〈LOGIC〉からリリースということもあり、今作では集大成的な作品を目指したのでしょうか? また、1993年の1stから今作のリリースに至るまで、ご自身の中で最も変化したところと、変わっていないところについて教えてください。
SU:色々コンセプトとか考えないで、普通に打ち込みをやった、という感じです。結局、1993年から2006年迄続けてみて、一度も本物になれなかったというのが率直なところです。本物とは、端的に「ちゃんとしてる・しっかりしてる」ということです。そうでない音楽を沢山愛してきたし、そういう立ち位置にいることはみっともないけれどこれは業みたいなもんで仕方が無いです。最近は本物の人ばっかしな気がしてつまんないです。
—— 今回のデジタル配信の解禁により、国境や世代を越えたリスナーがスズキスキーさんの音楽に新しく出会うことになると思いますが、率直にそのことについてどのように感じていますか?
SU:恐怖。それ以外無い。
—— 最近はどのような音楽を聴かれていますか?
SU:他人の音楽を聴くという習慣を失っております。配信は加入しておりませんし、フィジカルもかれこれ10年以上購入しておりません。それで音楽を作り続けると独善的で最底辺的な音楽が誕生して面白いです。dommuneでDS10のライヴを披露した時、twitterで「親父がDSで遊んでるだけじゃん。家でやれよ」という正鵠を得たTLが流れて来て感激しました。普段はラジオを聴いてます。それでいい曲を発見したらPCで動画探して視聴します。最近良かったのは、Thundercat の「I love Louis Cole」と浦上想起の「未熟な夜想」です。
—— 今後のご予定について、もしお話しできることがあれば教えてください。
SU:女にモテたい一心で音楽を続けてきましたが大大失敗の人生でした。予定はもう無い。
レイ・ハラカミ『広い世界 と せまい世界』稀代の才能の源泉を伝える貴重な初期音源集 text by 藤川 貴弘
スズキスキーの7作品と同時に、昨年12月に〈rings〉からCD/カセットテープのフォーマットでリリースされたレイ・ハラカミの初期音源集『広い世界 と せまい世界』も配信開始となることも、注目すべきトピックだ。2011年に惜しくも急逝したレイ・ハラカミは、自身の音楽制作に対する真摯な姿勢ゆえに、「安易」だと感じられる音楽やジャンルなどについて時に歯に衣着せぬ物言いで批判を行うこともあったが、賛辞を惜しまない対象も存在しており、その内の一人がスズキスキーであった。その想いはもちろん一方通行ではなく、2人は互いが互いをリスペクトし合う関係性にあり、稀代の音楽家同士の交流は「Skyline」(スズキスキー『Action E.P.』収録)や「きえたこい」(レイ・ハラカミ『わすれもの』収録)という刺激的な音楽としても結実している。
上述の通り、レイ・ハラカミはスズキスキーの1st『Thought』の2003年のリイシューに際してライナーノーツを寄せており、そこで「徹底した抑制感の機微」こそがスズキスキーの音楽における最大の魅力であることを綴っている。また、それはテクノロジーが生み出す新規性に回収されるものでは決してないのだ、ということもハラカミは強調する。
「広い意味でエレクトロニクス・ミュージックを聴く人の中には、新しいテクノロジーから生まれた価値観こそが新たな時代の革新的な表現を生むのだ、などという大仰な前提で、作品の良し悪しを語ろうとする人達もいるかも知れませんが、そういう括りの中だけで彼の音楽を語るのは、あまりに了見が狭すぎるのではないかと思うのです」。レイ・ハラカミがスズキスキー『Thought』リイシュー盤に寄せたライナーノーツより
スズキスキーの諸作品に通底する音色や構成に対する抑制や機微、独自のセンスやバランス感覚は、彼の音楽にジャンル的枠組みや時間の隔たりを越えて広く聴かれ得る魅力と強度を宿すこととなり、そのサウンドとビートは、ノスタルジーを引き連れることなく、今なお私たちの心と体を震わせてくれる。
テクノロジーがもたらす新規性に価値を左右されることのないエレクトロニック・ミュージック――。レイ・ハラカミがスズキスキーの音楽を評したその言葉は、また彼自身の音楽についても当てはまるものである。よく知られているように、レイ・ハラカミはデビュー作『Unrest』(1997年)から、最後のオリジナル・アルバム『Lust』(2005年)に至るまで、一貫してローランドの音源モジュール「SC-88 Pro」とオプコードのシーケンサーソフト「EZ Vision」を使い続け、自身の音楽制作に用いるテクノロジーを大きく更新することはなかった。サンプリング・レート32khzで収録された約40MBの波形データという限りある音色と、ピッチベンドやディレイ、パンニングといったベーシックなノート操作・エフェクトという先進性とは無縁のテクノロジーを用いながら、それでも魔法のように鮮やかで驚きに満ちたエレクトロニック・ミュージックを紡ぎ上げた。
ハラカミは音色やテクスチャーの新規性や構造・リズムのいたずらな複雑性を求めることはなかったが、彼の作品から聴こえてくるコード感やうたごころ、音の配置やスペースの作り方、楽曲の構築性や構成の妙、リズムの多層性などといった、言わば音楽における基礎的な部分に、確かな革新性が宿っていることは誰しもが認めることだろう。そのような音楽を生み出す想像力は、いかにして獲得されたのか。その背後には、どのような道程があったのか。この度、配信開始となった『広い世界 と せまい世界』は、そんな問いに対する答えを照らし出してくれる刺激的な一作となっている。
『広い世界 と せまい世界』は、まだレイ・ハラカミが「映像作家・原神玲」として活動していた時期にカセットテープで発表した『広い世界』(オリジナルリリース:1991年)と『せまい世界』(オリジナルリリース:1993年)という2つの音源をまとめた、『Unrest』の前史となる初期作品集だ。人の映像作品のためのBGMとしてクライアントワーク的に制作された楽曲を多く含む今作を聴き始めた時、「レイ・ハラカミの音楽」とはだいぶ様相を異にしていることにまず驚くかもしれない。ギターやベース、キーボードといった楽器を用いて、時にヴォーカルやコーラスをとり、4トラックのカセットMTRに録音された楽曲群には、『Unrest』以降の作品では(表面的には)聴こえてこない極めて肉体的でアナログな感覚にあふれている。そして次に驚くのは、その曲調、スタイルの振り幅の大きさだろう。アコースティックギターを主軸としたメランコリックな楽曲や民謡調や童謡調の楽曲、荘厳な響きをたたえたピアノ&オルガン曲にブルージーなロックンロール、フォーキーな弾き語りなど多彩なサウンドにあふれていて、ハラカミが多くの引き出しを持ち合わせていたこと、様々なチャレンジを行っていたことが伺い知れる。後のレイ・ハラカミの音世界は一朝一夕に培われたものではなく、広範な音楽的素養と試行錯誤の果てに達成されたものであろうことを、今作は教えてくれる。
『せまい世界』へ聴き進めていくと、基本的には『広い世界』を踏襲した多彩なサウンドが展開されていく中、「花道」のようなディレイやリヴァーブがふんだんに用いられたミニマルで浮遊感をたたえた楽曲や、「道を歩けば」のようなアンビエントやポスト・クラシカルを想起させる楽曲もあり、そのサウンドの「レイ・ハラカミの音楽」への確かな接近を感じさせる。また、今作では後のトレードマークとなる「ローランドの音源モジュールの音」も聴くこともできる。以前、レイ・ハラカミの学生時代の先輩であり当時に音楽制作者同士としての交流も持った由良泰人にインタビューを行ったのだが、その時に由良は、ハラカミがもともとはコンピューターを用いた音楽制作(DTM)を毛嫌いしていたこと、しかし由良の部屋での「遊び」としての作曲を通して徐々にハラカミがDTMに親しんでいったこと、そしてこの『せまい世界』の一部の楽曲ではローランドの音源モジュール「SC-55」(この機種の上位グレード後継機が後の愛機となる「SC-88 PRO」)が使用されていることを教えてくれた(TOKION:短期連載「今また出会う、レイ・ハラカミの音楽」 第1回:映像作家・由良泰人が語る、風化しない世界が生まれた「始まりの日々」のこと https://tokion.jp/2022/02/13/rei-harakami-music-vol1/ )。由良によれば、ハラカミはこの辺りの時期を堺に、細やかな音楽的ニュアンスが表現可能であることや、ポリリズムを実現する際の利便性への気付きによって、DTMにのめり込んでいったのだという。今作は、「レイ・ハラカミの音世界の始まり」を記録した貴重なドキュメントでもあるのだ。
スズキスキーという孤高の才人が残したタイムレスなエレクトロニック・ミュージックに、レイ・ハラカミという稀代の音楽家が残した貴重な初期音源に、世界中のリスナーが容易に触れられるようになったことを、二人の一ファンとして心から喜びたい。
—–
藤川 貴弘
出版社や広告制作会社などを経て2017年に独立。各種コンテンツの制作、編集・執筆などを行う。2020年8月から「TOKION」編集部にコントリビューティング・エディターとして参加中。同メディアでレイ・ハラカミを振り返る短期連載「今また出会う、レイ・ハラカミの音楽」を担当した。
—————–
https://tokion.jp/author/takahirofujikawa/
—–