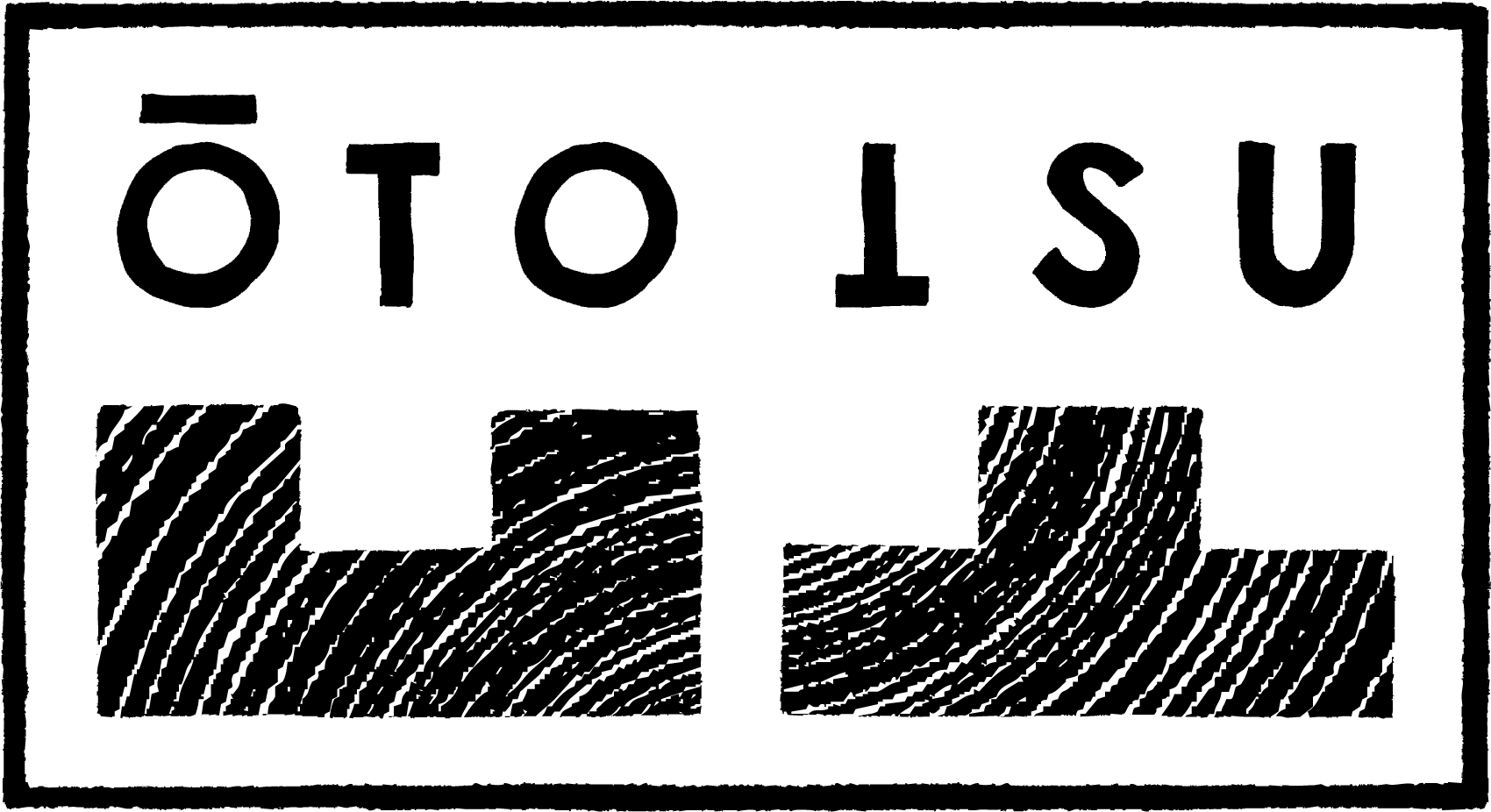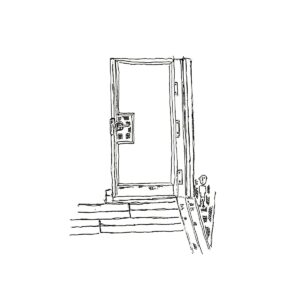2026年にシンガーソングライターとしてCDデビュー10周年の節目を迎える岡山健二の、新連載シリーズ。
2025年7月上旬より不定期更新。
文:岡山健二
編集:清水千聖 (OTOTSU編集部)
「ティーンエイジ・パンク」
はじめての物事を行う時、人は、かつてない恐怖、戦慄、または胸の鼓動といったものと対峙することになる。
そんなものは微塵も感じないという、肝の座った人物も、いないことはないであろうが、まず間違いなく、前者のパターンのほうが圧倒的に多いのではないだろうか。
そういった物事を、いくつも経験して、人は大人になっていくのであろうが、とりわけ、一人で、誰に尋ねるでもなく、はじめての物事を行う時、または、行わなければいけない時に、自ずと、考える力といったものが、身につくのではないかと、思ったりもしている。
冬の空気は、カラッとしていた。
八両編成の列車は、しばらく走り続けていた閑散とした山道から、徐々に、人の賑わいを感じられる街並みへと、足取りを進め、手元のスマートフォンを眺め疲れた乗客が、気分転換に見やる車窓の景色を変化させた。
そうして、その光景が、このまま続くかと思われていたところに、半ば強引な慌ただしさでもって、原由実菜が、目的としていた駅に辿り着いたのであった。
列車を降り、ホームを左に進むと、エスカレーターがあり、それを使い、ひとつ上のフロアまで行くと、左右に出口のある大きな通路が、改札の向こう側に見えた。
「ここに来るのは、久しぶりだな」
と、由実菜は呟いた。
由実菜が、この駅に初めて降り立ったのは、彼女が十五歳の時だった。もう、ずいぶん前のことだ。
当時、彼女は、高校に通っていたのだが、十二歳で始めたエレキギターに、のめり込むあまり、周囲も驚くような上達ぶりを見せ、地元の、自分よりも年上の学生達と、一緒にバンドを組んで演奏するようになっていたのだった。
やがて、その評判が、ライブハウスシーンにも知れ渡り、県外の二十歳くらいのバンドから「一度、スタジオに入らないか」と声をかけられて、降り立ったのが、この駅だった。由美菜の住む町からは電車で約四十五分くらいの距離にあった。
駅自体の作りは、おそらく八十年代くらいに建てられたであろう簡素かつ強固な印象で、色は白で統一されていた。
改札を出ると、先ほども述べた通り、左右に出口があるのだが、正面には、いくつかのテナントが、駅の相談所などと共に並んでいる。
全国各地に見られるような、駅と商業施設が併設した作りになっているこの建物も、時の経過と共に、いくつかの変化を遂げていたのだった。
「あれ、あの喫茶店なくなっちゃったんだ」
由美菜は辺りを見渡した。
改札を背にして、右側の出口のほうへと身体を向けると、左手の壁がひと区画だけ、レンガ張りになっている場所があり、そのレンガの幅の分だけ、そのまま奥行き五メートルほどのスペースとなっていて、軽食とカフェのみの利用ではあるが、わりと落ち着ける店が、当時はあったのだった。
いつも見かけてはいたが、その店に入ったことは、この駅に通っていた数年間のうちにも、一、二回あったかどうかだったと記憶している。
ただ、その店の前を通り過ぎる際に、間接照明の仄暗い灯りに照らされた店内を、ちらっと横目に眺めるというのが、長年の習慣だったので、その店が無くなってしまっているというのは、どこかしら寂しさを覚えるところではあった。
由美菜が、この駅を頻繁に使っていたのは、都合四年ほどであった。
その後、彼女は、近郊の都会に住居を移した。
声をかけられた県外のバンドで、ギターを弾くことに決め、そこからコンスタントに活動をするようになって三年目辺りで一度、音楽事務所から声をかけられたのだが、結果、契約までは至らずだった。
そして、その落胆から、バンド全体のムードが、それ以降、何となく煮え切らない感じとなり、それでも一年ほど活動を続けたのだが、ありがちな話で、バンド内でも『…もう解散でもしようか』という話が持ち上がるようになり、実際に、春を迎える頃には『…今日で解散します』という台詞をステージ上で、お客に向け、言わざるをえないという運びになった、というわけであった。
いい経験もたくさんしたが、同時に疲弊した部分もあった。それ以降、由美菜は、ひとつのバンドで根気よく活動していくというよりかは、いくつかのバンドで、少しずつギターを弾いていくというセッションギタリストといったスタイルに移行しようとしていた。
知り合いのミュージシャンが増えたというのも、その活動を可能にしたひとつの要因ではあった。
しばらくは、こんな感じで、一人で気ままに暮らしながら、ギターの腕でも磨いていこう。そんなふうに思っていた。
新しく移った街での暮らしが、性に合っていたのか、日々は思いのほか楽しく、別の街に繰り出すという機会も、ここ最近はめっきり減ってきていた。
しかし、今日はかつて頻繁に共演していたミュージシャンのライブが、この近くの店であり、由美菜はゲストとして演奏するべく招かれて、久々にこの駅へと降り立ったのであった。
懐かしい雰囲気に気持ちが和らいだのか、ふと思い出したことがあった。
それは、由美菜が、この駅に通い出して一年くらい経った時のことだった。
肌寒い季節、その日、彼女は学校を終え、いつもの駅に集合し、そこからはバンドメンバーの車で、以前共演したプロのバンドのライブを観に、近郊の都市まで出かけることになっていた。
改札をくぐって、右側の出口を突き当たりまで行くと、正面は高さ四メートルほどのコンクリートの壁となっており、上部のほうはガラス窓になっていた。
そのガラス窓から、冬の日暮れ間近の、密度の濃い光が差し込んでいた。そして、左右両側には、地上へとつながる階段があり、由美菜は、下へと降りていった。
駅前のロータリー。丸皿の上の冷めたホットケーキと、それに染み込んだメイプルシロップのような配色にまで色褪せた、駅周辺の地図が『迷子猫探しています』または『空手教室生徒募集中』などの貼り紙が、無作為に陳列している古めかしい掲示板と共に、横並びに設置されていた。
その場所が、バンドメンバーとの、いつもの待ち合わせ場所なのだが、その日は、由美菜の他にもう一人、女の子が、文庫本を片手に立っていた。
ライブハウスで、何度か見かけたことのある顔だった。
由美菜より、少し年上といった感じであったが、その年齢くらいの娘にしては、落ち着き、というよりかは、若干くたびれた雰囲気を漂わせていた。
一見、礼儀正しそうな印象を受けるのだが、諦めというか、投げやりな感じが、どこか見え隠れする表情。
髪は、肩より少し長いくらいの重めのロングヘアーで、荒い縫い目のグレイのニットを被っていた。淡紅色のスカートは丈が長めで、軽く覗く足元には、黒いブーツを身につけていた。
そして、腰から上は、今日これから観に行くバンドのパーカーを着ていた。
黒地に白が基調で、左の胸元には、バンドのロゴにしては、やや印象の薄さが否めない、良くも悪くもバンドの個性を上手に表現しているともとれるデザイン。
背中には、数ヶ月にも渡るツアースケジュールが、仲間にうまく馴染めない少年が放課後の校庭の隅っこで見つめ続ける蟻の行列の描く曲線のようにプリントされていた。
ちょうど全く同じ物を由美菜も持っていたが、今日着てこようか悩んだものの、虫の知らせというか、何となくやめにしておいたほうがよい気がして、着てこなかったのだったが、その判断が、あながち間違いではなかったことに、内心ホッと安堵しつつ、その場に立ち尽くしていると相手のほうが、慣れた手つきで、文庫本を鞄にしまい終えたあと、口を開いたのだった。
「こんばんは、お話しするのは初めてですね…」
と、土屋加音は言った。
トーンは低めだが、かわいげのある声をしていた。
「そうですね」
と、由美菜は言った。
向き合って立ってみると、二人の背丈は大体同じくらいであった。
「先月のライブ、観に行かせてもらったのですが、とても良かったです。余韻がなかなか抜けませんでした」
「あ、観に来てくれてましたね。どうもありがとうございます」
「新しい曲、やってましたよね。——何か今までにない感じで新鮮でした」
「あぁ、あの曲は、ここ最近バンドでずっとアレンジし続けていたもので、あの日ようやく披露できたんですよ」
「へぇ、そうだったんですね」
「そう、ここのところ、レパートリーが変わり映えしなかったから、ようやく風穴を開けられた感じというか」
「えー、全然いつも楽しいですよ!」
「そっか、そう言ってくれるとうれしい」
「はい、その上に新曲も聴けたんで言うことなし、という日でした」
「あぁ、何か、演奏してると毎回同じ曲ばかりで、観に来てくれる人達に悪いなと思ってたけど。——そう思いすぎるのも良くないですね」
「そうですよ、そこまで気にしなくてもいいと思います。それに同じようでいて、いつも全然違います」
と、そこまで続いた会話は、ふいに途切れた。
由美菜は何となく、先ほどまで自分がいた駅構内のことを頭に浮かべながらも、先ほどまで加音が手に持っていた文庫本のことが気になっていたので、何となく聞いてみたのだった。
「よく本は読むんですか」
すると、加音は、
「そうですね。読めないものもあるけど、短いものなら」
と言うのであった。
「へぇ、そうなんですね。私は昔から本は、からっきし駄目でして、教科書とかも頭に入ってこないくらいだったけど…」
「そうですか」
「でも、本を読んでたら、何か人生変わってたかなぁ、とか思ったりもするかな」
由美菜は、そこで理由もなく、立っていた所の足の置き場を変えた。靴と地面の間にあった砂利がジリッと音を立てた。
加音は、細い首を傾げつつ、組んでいた腕の片方の手の平を、柔らかそうな頰に当てがいながら、話を続けた。
「んー、でも私もさっきも言ったように、ほとんど本は読めないんです。五ページ、十ページくらいの短編小説なら読めるかなという感じで。ずっとスマートフォンを見てるよりはいいのかな、とか思ったり、それに何より、一つ読み終えた時の、読み終えた、という達成感がいいですね」
「そうかぁ、私もいつか読めるかな。——ちなみに、さっきは何を読んでいたんですか?」
「あぁ、私のですか?えっと、さっき読んでいたのはルシア・ベルリンという作家の短編集で、その中の『ティーンエイジ・パンク』という話ですね」
「へぇー、そうなんだ。面白そう」
「他にも何だか変わった作品が多くって、この話も三、四ページで終わるんですけど、全然パンクとか関係ないんです」
「ありゃ」
「シングルマザーの女性が、息子の友達と、夜明けにツルを見に行く、という話なんですけど」
「でも、そんなタイトルなんだ」
「はい。——でも、カッコいいんですよ」
「書いた本人が?」
「そう、女流作家で。容姿も整っていて、表紙の写真なんか煙草を片手に、まるでモデルみたい。でも大変な人生だったらしく。いろんな仕事につきながらも、短編を書き続けた人みたいなんです」
「そっか。じゃあ私も、読むのなら、その人にしてみようかな」
「はい、いいと思いますよ」
と、ここで、由美菜は話題を変えて、加音に尋ねた。
「ところで、私たちのバンドは、いつから観に来てくれるようになったんですか?」
「えーと、今年の春くらいからですね」
と、加音の声がロータリーにこだました。
「へー、そうですか」
「はい、夏のイベントにもお邪魔させてもらいましたよ」
「あー、あの、私のアンプが壊れて、音が出なくなった日だ!」
「あ、そうでしたね」
そう言って、加音が相づちを打ったところで、バンドメンバーである浅川隼人の運転する銀色の軽自動車が到着したのであった。
「お待たせ、行こうか」
運転席の窓から身を乗り出すようにして、こちらを覗いている浅川は、由美菜や加音よりも、六、七歳年上で、一見遊び人といった感じではあるが、芯の部分は、しっかりとしていることが、当人のまとっている空気や、いでたちからもよくわかるように、いわゆる兄貴肌というか、人を惹きつける魅力のある青年なのであった。バンドでのパートは、歌とベースであった。
「まあ、乗ってくれよ」
と、浅川は言った。
「ありがとう」
と、由美菜は応えた。
加音は、何も言わずに助手席に乗り込んだ。何か言葉を発したのかもしれないが、由美菜には聞こえなかったというだけのことなのかもしれない。
由美菜は、後部座席の左側の方に腰かけた。後ろの方には、浅川が昼間に行っている建築関係の仕事道具やバンドの機材など、いろんなものが雑然と並んでいるのが見えた。
浅川がギアを切り替えると車は颯爽とロータリーを横切った。せまい通りをいくつか進み、やがて混雑した国道へと出た。
地方都市でよく見かける、お馴染みのチェーン店が、いくつも現れては消えていった。
「今日の市原さんたちのライブ、楽しみだな」
運転席の浅川が、誰に話すでもなく口を開いた。
「…そうね」
少し待ってみたが、何も話しそうにない加音の様子を見て、仕方ないといった風に由美菜が相槌を打った。
「そういえば、市原さんたちは、今度新しいアルバムを出すらしいよ」
「あ、そうなんだね」
「うん、何でも事務所が変わるらしい。——それで、そこの社長が元々、プロドラマーかなんからしくって、けっこうバンドアレンジにも口出しされるんだって」
「そうなんだ」
「うん、それで挙げ句の果てには、社長もパーカッションとかで録音に参加したいって言い出す羽目になっちゃったんだって…」
「へー、何か大変そうなことになってるね」
「うん。まあでも、あの人たちが、この先もプロでやり続けるには、今はそうするしかない、みたいなことを電話では言ってたよ」
「電話したんだね」
「そう、今度のツアーでタイミングが合えば、俺たちのバンドのイベントに出てくれないか、って相談したんだ」
「そうか、話をするって言ってたね。ありがとう」
「うん、そう。そうしたら、俺たちもそこに合わせて、新作でも作れたらいいなと」
「あぁ、いいね。この前のライブで演奏した新曲も収録したい」
と、そこまで会話が続き、その話題が出たときに、由美菜は、先ほど、その曲について加音と話をしたことを思い出し、またもや、加音が何かを話すかなと、しばらく待ってみたが、一向にその気配もなかった。
おそらく、この娘は何人かで会話するのが苦手なタイプなのだろう。もしくは、自分に、浅川との会話を見せたくないのかもしれない、と考えることにしたのだった。
浅川の運転する車は、気づけば、高速道路のようなところを走っていた。
ある部分では、急に道が混み出し、しばらく消化不良のようなエンジン音を発しながら、ノロノロと進んでいたかと思うと、車の少なくなったスキを見計らって、車はスーッとスピードを上げていく、といったことを繰り返していた。
道が混んでいる時は仕方ないものの、それ以外は適度に気持ちのよい走りを見せる浅川の運転は、多少荒々しさは目につくものの、車を完全に自分のものにしている人特有の、この人に運転を任している限りは、つまらないヘマはしないのだろうなという、ある種の安心感があることは確かだった。それは純粋な才能といってもいいものであった。こと運転に関していえば、それは確かなことであった。
「遠いねぇ」
「そうだな…」
何処となく、河原に放った小石を思わせるような、短い会話はあったものの、それらが、たいして続くわけではない。
ちょうど夕方くらいから夜へと移り変わる時間帯のどんよりとした空の下、車は三人を乗せて走っていたのだが、タイヤが道路の上を走る際に起こるブォーンと、うなるような低い音が、この空間内においての最も大きな音だった。
そして、その次に大きい、というよりかは、その他に聞こえてくるのは、何十メートルかおきに配置されている道路のつなぎ目を通過する時の車のガタっと揺れる音と、浅川が日頃から愛聴している、いくつかのガールズバンドの往年のヒット曲なのであった。
九十年代の、いわゆるアジアンポップスということになるのだけど、多分に当時のイギリスやアメリカの音楽に影響を受け、日本の本来の特性であろう歌謡曲らしさが、極端に抑えられた、捉えようによっては、ある種、妙な音楽とも言えるものだった。
例えば、晴々しい気分の中で耳にすると、全く受けつけなかった、重苦しい雰囲気のミディアムテンポの十六ビートの曲が、この混んだり、空いたりを慢性的に繰り返している道路の上では、何故だかわからないが自分の気持ちに、しっくりくるのだった。
こんな風に、退屈だったり、ちょっとつまらない時に聴くことによって、輝く音楽があるのだなということを、後部座席に座り、外の景色を眺めることにも飽きて、何もすることがない、できることがないときに身をもって感じられたのであった。
そして、こういう、うだるような雰囲気の、格好良さだったり、いわゆる渋い音楽をいつか演奏できるだろうか、ということが頭をよぎった。
二人が普段から活動しているバンド『ステイヤングス』は、シンプルなスリーコードからなるパンクバンドで、曲調もテンポの速いエイトビートのものがほとんどであった。浅川と由美菜、そこに元々浅川の友人であったドラマーが加わった三人組だ。
由美菜が参加する前から、バンドは活動しており、やめていったメンバーが残していった曲の出来の良さと、それらの曲の客やライブハウスのスタッフ達への浸透具合からなる、固定のレパートリーというものがあった。
由美菜も浅川も、その曲達のことは大事にしているが、新たな曲とも入れ替えていきたい気持ちもあるし、しかし、ライブのことを考えると、なかなか動かせないというのが現状なのであった。
車は変わらず走り続けていた。空の様子も先ほどと特に変わりなかった。ぼんやりした頭で、由美菜はふと、
『諦めずにやっていれば、か——』
と、声に出すでもなく、そんな台詞を頭に浮かべた。
外の空気は、ずいぶんと冷え込んできている様子で、そのせいか加音は小さく咳をしていた。
浅川はその様子を見て、
「あ、寒いか」
と、車の暖房の温度を少し上げた。
ゴォッと、ヒーターの音が押し寄せるようになり、ガールズバンドの音楽は聴こえづらくなった。
その中で、微かにではあるが、最後まで聴こえてくるのは、ドラマーの刻むハイハットシンバルの音と、ハイトーンボイスの女性ボーカルの声だった。
ちょうどアルバムが切り替わり、微かではあるが、ヒーターの風の向こうから、由美菜の好きなバンドの曲が聴こえてきた。
「あー、はいはい。この曲いいよね!Jack&Betty」
と由美菜が、嬉々として話し出すと、浅川はヒーターの出力を下げながら応えた。
「うん、懐かしい。——だけど、それだけじゃない」
「そうだね。たしか解散するって発表がある少し前に、この曲のシングルが出たはず」
「そうか、それくらいの時期か」
「うん、なんだか半年くらいの間に、いい曲を連発してるなって思っていたら解散だって。すごいことにテレビのコマーシャルでも放送されてた」
「あぁ、あったね。メンバー四人が、うす暗い海辺みたいな場所にいてさ。——『Jack&Bettyは解散します』って、ヴォーカルのYUKAが話してた」
「風の音がゴゥゴゥ鳴っててね……」
「よく覚えてるもんだね」
「ほんと、お互いね」
「でも、あの時期のシングルって、ほんとにいい曲ばかりだった。——『ひとつの花』『サーファーの唄』『プールサイド』とか」
「『遊歩道』もね」
「あぁ、それよりちょっと前のやつだね。私も好きだった」
「そっか」
「でも、あの時期の凄みみたいなものって、やっぱり特別な感じがあったな。わかんないけど、あの人たちのすべて?ともいえるような、まあ、そればっかりは当人じゃないから、わかんないけど、そのさ、バンドが解散することになって、それに向かっていくエネルギーってさ、なんというか計り知れないところがあるというか。——でも、結局そういうものって、音に現れるんだよね。なんかすごいって、思ったもん」
「そうだな、たしかに音に現れる…」
由美菜は、浅川の何か言いたげな表情を読み取りはしたものの、そこから先は聞かずともよいかと思い、また音楽に耳を傾けていた。
道路標識には、目的地の街の名前が現れ始めていた。ビルや店の雰囲気も少し変わってきていた。
そして、それと同時に道路もまた混み始めていた。
浅川は、右足で軽くブレーキをかけながら、少しずつ車の速度を落としていった。
* * * * * *
目次
全話、こちらからお読みいただけます。
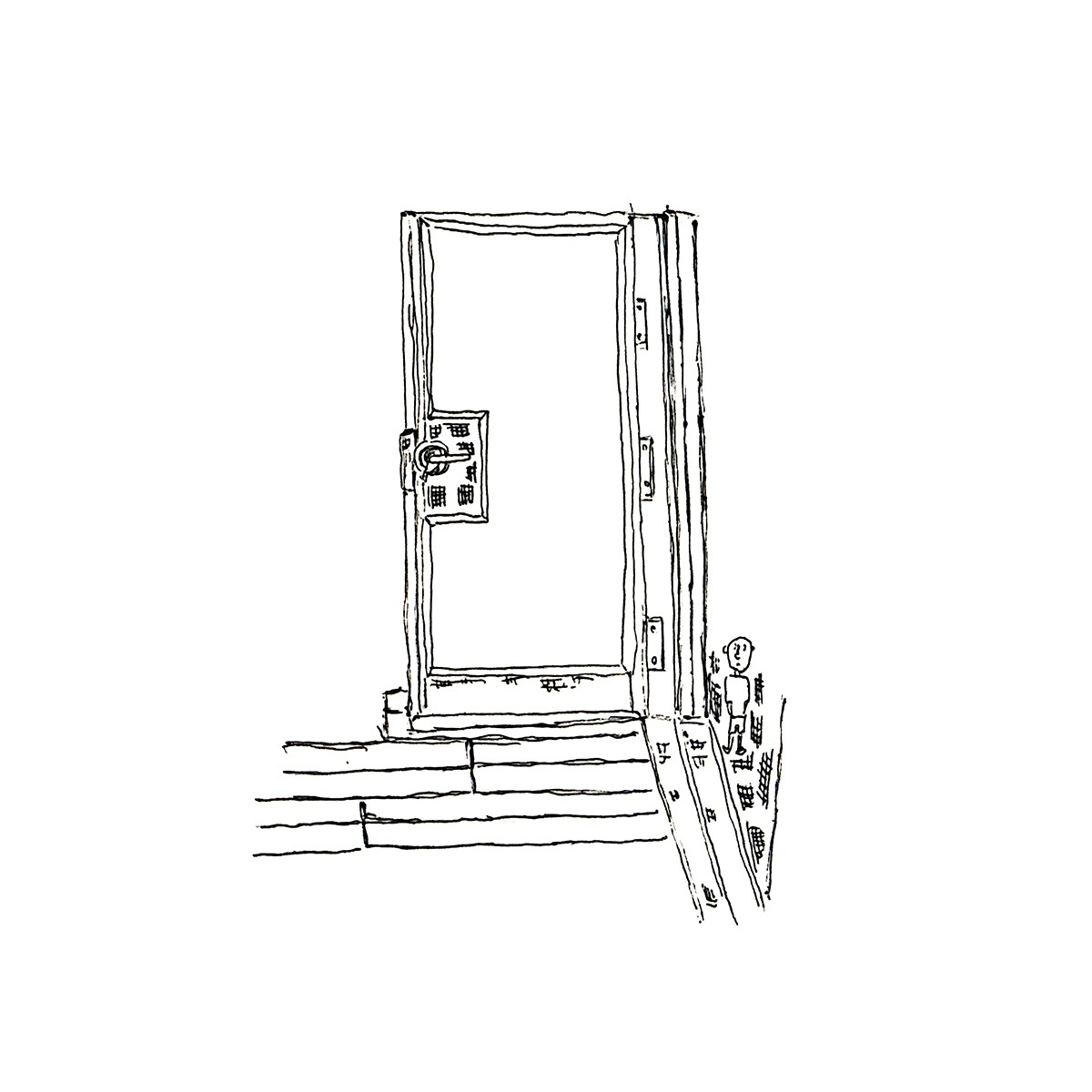
RELEASE INFORMATION
Hasta La Vista
classicus
2025.07.23 Release
second hand LABEL
Price: 2,500yen (tax in)
Format: CD / Digital
Catalog No: SHLT2
Track List
01 フェルメールの肖像 (free coffee ver.)
02 君の家まで (another motif ver.)
03 ブルーバード
04 Hasta La Vista
05 yokomitsu park
06 みえない
07 土曜の夜
08 ナイト・ドライブ

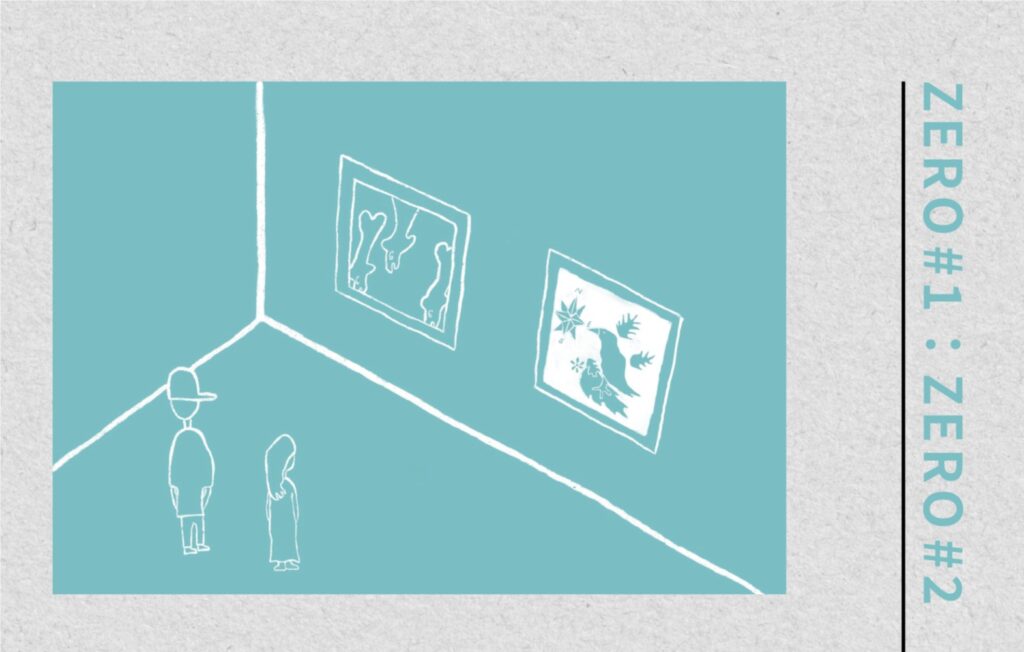
ZERO #1 : ZERO #2
classicus
2024.10.14 Release
second hand LABEL
Price: 2,500yen (tax in)
Format: CASSETTE / Digital
Catalog No: SHLT1
Track List
Side A 「ZERO #1」
01 真夜中
02 sea you
03 車輪の下で
04 ひらめき きらめき
05 恋の伝説
06 コチニール
Side B 「ZERO #2」
01 ホタル
02 シネマのベンチ
03 デッドストックのペイズリー
04 盟友
05 夜のプール
06 グッドナイト
The Unforgettable Flame (CD&LP)
岡山健二
CD 2023.08.02 Release
LP 2024.03.20 Release
monchént records
Price:
CD 2,200 yen (tax in)
LP 4,500 yen (tax in)
★ブックレットに書き下ろしライナーノーツ掲載
★ディスクユニオン&DIW stores予約特典:
オリジナル帯
Track List
Side A.
01. intro
02. 海辺で
03. 名もなき旅
Side B.
01. あのビーチの向こうに空が広がってる
02. 軒下
03. 永遠
04. My Darling

LIVE INFORMATION
11/25 (火) 東高円寺 U.F.O.CLUB
11/27 (木) 新高円寺 STAX FRED | ソロ ツーマン 原田茶飯事
11/28 (金) 南青山 POLARIS | 日高理樹 yagihiromi 中尾憲太郎 〈ドラム〉
12/2 (火)横浜 B.B.STREET | 川崎テツシと燃えるキリン 〈ドラム〉
12/7 (日) 大阪 心斎橋 歌う魚
12/8(月) 南青山 POLARIS | ソロ ツーマン 五味岳久
12/12 (金) 渋谷 WWW | 豊田道倫 〈ドラム〉
12/17 (水) 新高円寺 STAX FRED |ソロ ワンマン
12/19 (金) 大阪 心斎橋 CONPASS | 豊田道倫 〈ドラム〉
12/29 (月) 新高円寺 STAX FRED
1/12 (月・祝)都内 昼
1/13 (火) 都内
1/30 (金)下北沢 440 | 中川昌利 〈ドラム〉
ARTIST PROFILE

1986年三重県生まれ。12歳でドラムを始め、のちにギターとピアノで作曲を開始。19歳の時に上京し、2011年にandymoriでデビュー。2014年、同バンドの解散後は、自身のバンドclassicus(クラシクス)を結成し、音源を発表。
現在は、ソロ、classicusと並行し、銀杏BOYZ 、豊田道倫 & His Band!ではドラマーとして活動している。
【Official SNS】
岡山健二 Official SNS / リリース一覧
https://monchent.lnk.to/kenjiokayama
classicus
Web Site
https://www.classicus.tokyo/
YouTube
https://www.youtube.com/@classicusofficialchannel186