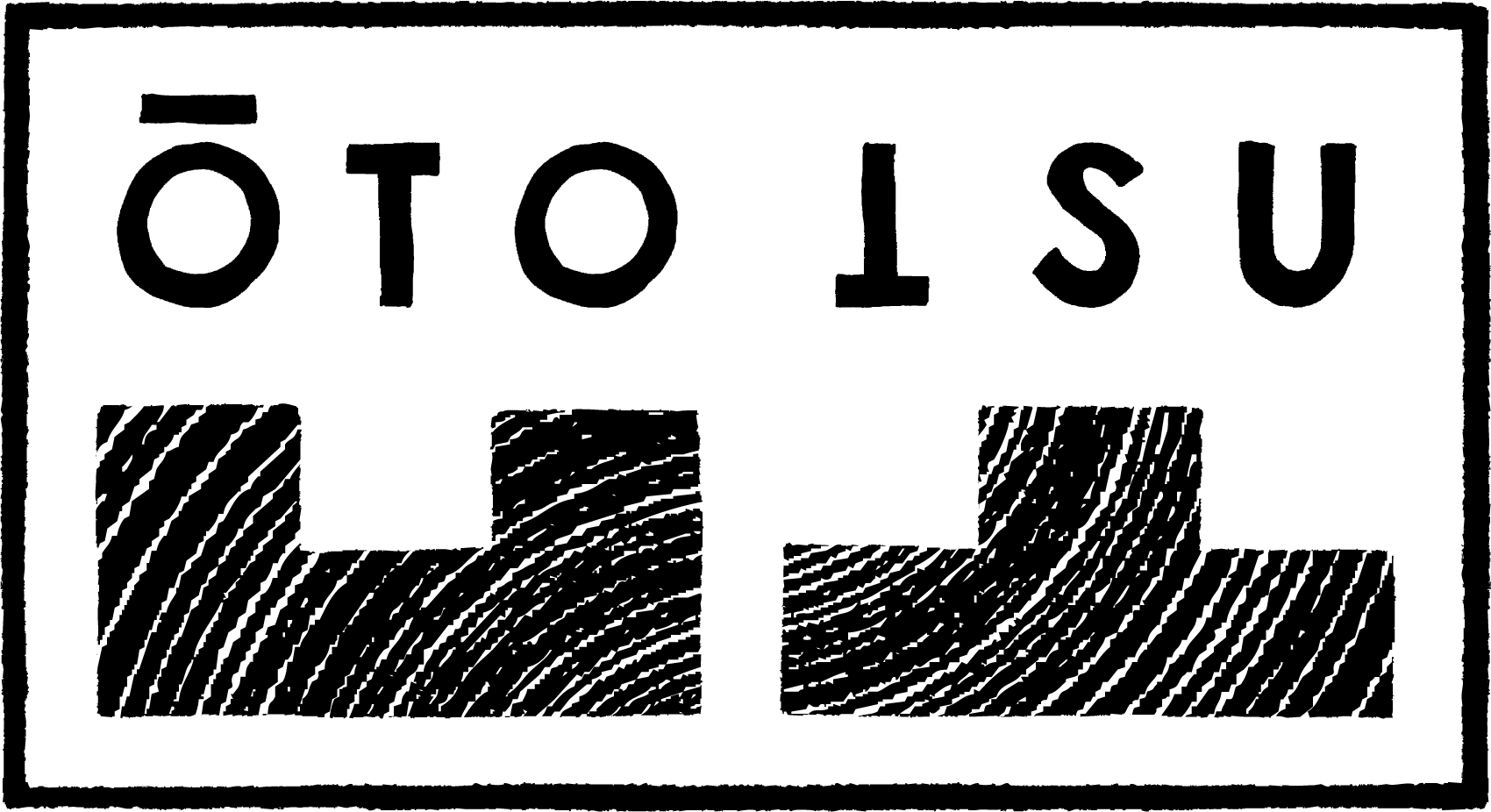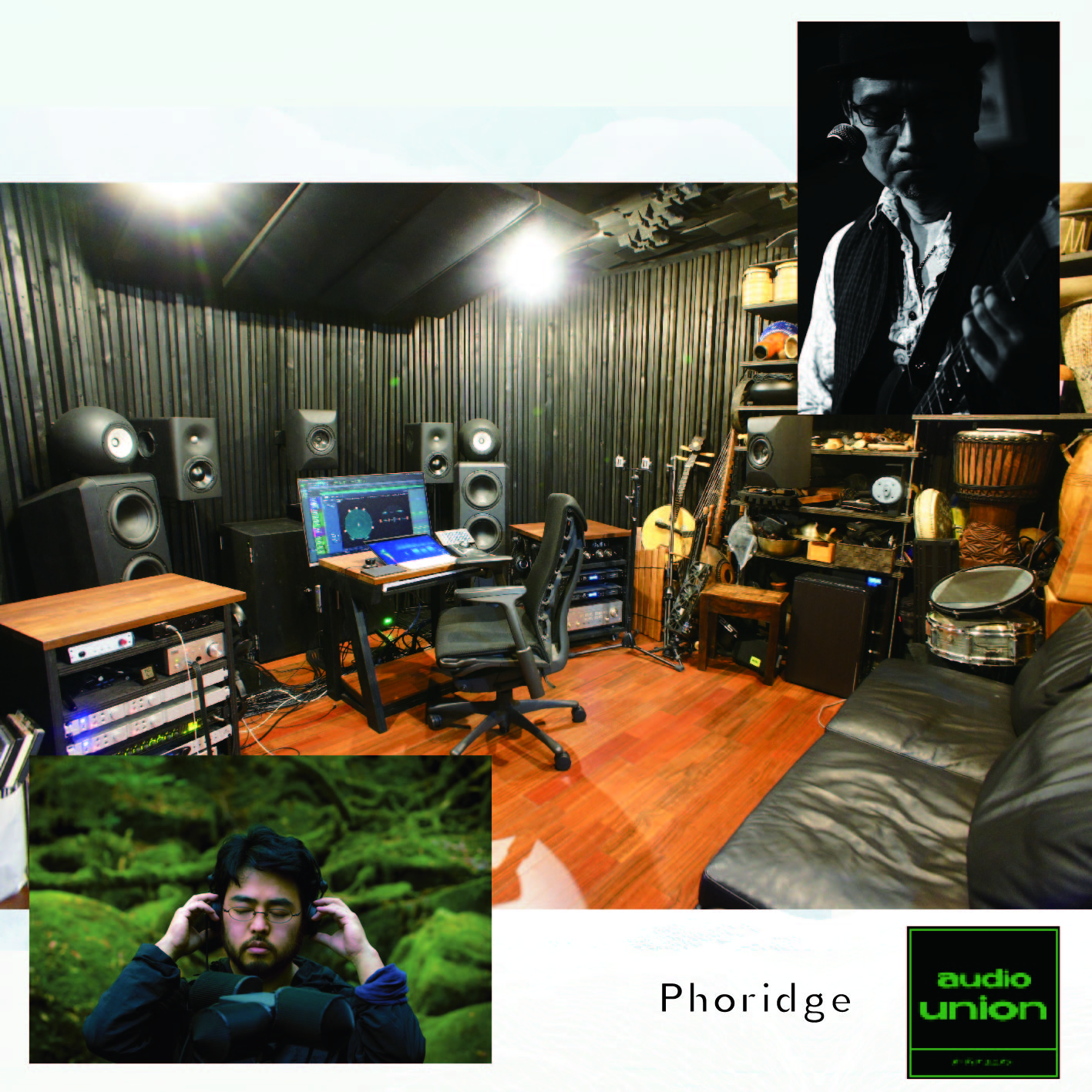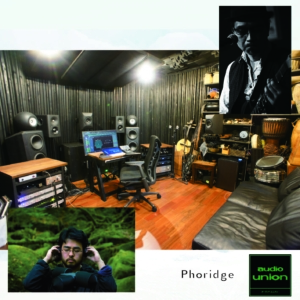「Phoridge(フォリッジ)」は、音のプロフェッショナル「オーディオユニオン」のレーベルとして2020年に設立された。レーベル名である「Phoridge」にはオーディオ業界の「今まで」と「これから」を見据えた沢山の想いが込められている。人と音楽の、音楽とオーディオの橋渡しとなることがこのレーベルの願いだという。

オーディオ・リスニングのプロフェッショナル、オーディオユニオンのスタッフが本気で選んだ、スピーカーでこそ聴いて貰いたい日本の錚々たるアーティスト達のエレクトロニックミュージックをコンパイルしたコンピレーションアルバム『Electronic Music for Loudspeakers』第二弾が、2022年2月2日に発売された。
前作に引き続きAOKI takamasaやGONNO(YOUR SONG IS GOODのリミックス作品)、HIROSHI WATANABE aka Kaito、mouse on the keysらが参加。さらにChari Chari、Kaoru Inoue、Go Hiyama、starRo、kuniyuki takahashiなど日本のシーンを支えるアーティストが勢ぞろいし、このコンピレーション作品で初フィジカル化の楽曲も含み、目が離せない内容になっている。

この度、レーベルの主催者であるオーディオユニオンのスタッフが聞き手となり、『Electronic Music for Loudspeakers』シリーズのマスタリングを担当した、Yosi Horikawaと堀部公史に、話を聞いた。
メンバー:オーディオユニオン(坂本哲平、山口真古都)、Yosi Horikawa、堀部公史
編集:三河真一朗 (OTOTSU 編集部)
オーディオショップがレーベルをつくるということ
 オーディオユニオン
オーディオユニオンこの企画はオーディオショップがレーベルを作り、CD製作をするという少し変わったものですが、まずマスタリングとリマスタリングのオファーを受けて、お二方はいかがでしたか?
『Electronic Music for Loudspeakers Selected by audiounion』
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawa単純にものすごく嬉しかったですね。数年前、Spotifyのヘッドホンの音質チェック用のプレイリストに僕の曲が選ばれて、それがきっかけでオーディオに興味がある人が僕の音楽をチェックに使うようになってくれている、というのをなんとなく知るようになったんですね。それって、僕としてはすごい驚きでした。その辺から良い音にしよう、スタジオを自分でしっかり作ろう、と意識するようになりました。
思い返せば最初に自分でスピーカーを買ったのがオーディオユニオンさんでした。ディスクユニオンさんで僕のCDも取り扱って貰ったりして、不思議なぐらいの気持ちもあったんですけど、とにかく光栄でした。
※ボブ・ディランやシガーロス、エルトン・ジョンなど錚々たるトップアーティストの楽曲が並ぶSongs To Test Headphone Withに「Bubbles」がリストアップされる。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンこの企画のオファーに関して、堀部さんはいかがでしたか?
 堀部公史
堀部公史ハーマンインターナショナル※に在籍していた時、10年近くオーディオユニオンさんの営業担当をさせていただいているんですよね。その当時からディスクユニオンさん、オーディオユニオンさんと「もうちょっと一緒になにかできるといいな」っていう夢がまず一つありました。
それから、Yosiさんをはじめ今現在のアーティストさんで良い作品を作ってらっしゃる方がいっぱいいるのに、オーディオマーケットで紹介する機会が少ない、っていう悔しい思いをしていたんですよ。それもあって、今回オーディオユニオンさんの企画に、僕は激しく賛同しました。もうちょっと(オーディオ)業界全体のフィールドを広げる足がかりになるといいかな、と思いますね。
※ハーマンインターナショナル : 米国スピーカーブランドの名門JBLなどの輸入販売を手がける歴史ある商社。
オーディオとのかかわり
 オーディオユニオン
オーディオユニオンちなみに、Yosiさんは好きなオーディオブランドは何かありますか?
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaオーディオユニオンで初めて買ったのはB&W※のCDM1※だったんですね。B&Wはいまだにすごく面白いことをしていて、革新的だし、すごく理にかなった設計というか・・・好きですね。
あと、イギリスのなんというか、どことなく漂う品の良さみたいなものは常にある気がしていて、そういう音は好きなのかな、やっぱり。
※ B&W : アビーロードスタジオでも採用されているイギリスを代表するスピーカーブランド。
※ CDM1:B&Wの小型スピーカー。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンイギリス製品の「品の良さ」っていうのはすごく理解できますね。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawa自分でも手の届く範囲で買ってみよう、というのが最初にあったのが、大学一年かな。バイトして、しっかり聴けるものを買おう、と思ったのは。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンそれが、B&Wだったんですね。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaでした。それとDENONのPMA-2000※のシリーズ。
※ PMA-2000シリーズ:日本のオーディオブランドDENONのプリメインアンプ。
 オーディオユニオン
オーディオユニオン結構いいやつを最初にもう買われたんですね。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaそうですね。DENONのあのどっしりした音も好きでしたし、B&WとDENONのセットは本当に長いこと使いました。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンありがとうございます。
堀部さんはオーディオとの出会いはどんなものでしたか?業界長いので・・・あえて伺いますが、好きなオーディオブランドなどありますか?
 堀部公史
堀部公史個人としてはイギリスのHarbeth※ というスピーカーを買ってるんですよ。あとはDynaudio※ の古いのをモニターとして使っているんですけど。
もちろん僕の癖として好き嫌いはあるんですが、井筒香奈江さんという歌手のプロデュースをやっていた時に学んだんですけど、例えばB&Wだったらこういう音源掛けるとこういう音がするだろう、とか。なんとなく予想がつくので、仕事としては好き嫌いというよりも、このスピーカーだったらこういう風になるんじゃないかっていうことで、リマスターの仕事はしていますね。
(オーディオ機器は)仕事道具なんで、逆に趣味で何が好きなの?と言われると「えっっとなんだっけ・・・」みたいなことになっちゃう感じ(笑)そういう意味では、使いやすいっていうことでHarbethが鉄板で、モニターするにはHarbethとSTAX※ でやる、というような感じになっています。
※ Harbeth : BBCモニターの元技術者が1977年に立ち上げたイギリスのスピーカーブランド。
※ Dynaudio:1977年に創業したデンマークのスピーカーブランド。
※ STAX:1938年創業の日本の静電型ヘッドホンメーカー。
使用機材について
 オーディオユニオン
オーディオユニオン制作機材の話題がでましたが、今回マスタリングとリマスタリングをしていただいた制作環境、ソフトなど、どんなモニター環境で作業されたのか、その辺も少しお聞きできますでしょうか?
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawa処理自体は全部ソフトでやりました。この仕事は何回も話し合いながら進めていく方が良いものになりそう、ということもあったので。ハードを通すと後に戻せないというのもあります。
ハード的に言うと、まずクロック、Antelope AudioのOCX HD、これに半自作のルビジウム10MHz発振器。これをMeric Halo ULN-8というオーディオインターフェイスにいれています。
あと半分ソフトですけど、Dirac LiveといってルームEQもして位相の歪を直してくれるソフトがあるんですが、それもモニターする時に挟んでいます。
それからスピーカーはどちらも自作で、二系統あるんですけど、まずはB&Wに触発されて作ったトールボーイ。SEASの同軸ユニットとサブウーファー2発を使ってます。


 オーディオユニオン
オーディオユニオンB&WのNautilus802に、似ていますよね。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaもろに影響をうけました(笑)このスピーカーは、LAB gruppenのDシリーズというアンプで鳴らしています。
それからもうひとつがPurifiの最新のウーファーとBliesmaのベリリウムのツィーターを使ったスピーカー。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンいいですね、オーディオ的な感覚だと、ベリリウムのツィーターが乗っているスピーカーは腰があって良い音がする、というイメージがあります。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaベリリウム良いですよね。これまでマグネシウムとかアルミの合金とか、その辺はよく聴いていたんですけど、ベリリウムの芯がしっかり出るという感じは初めてで、今はこっちばっかり使っています。このスピーカーはPurifi 1ET400Aを使った4チャンネルアンプで鳴らしています。

 オーディオユニオン
オーディオユニオン堀部さんは基本的にソフトだけだと思いますが、モニター環境はいかがですか?
 堀部公史
堀部公史リマスターの作業としては、完全にプラグイン的なソフトとしてやっています。倍音生成が主ですが、かなり人力で作業しています。波形を見ながらどこをどういじって、どうしよう、というのを最終的に自分の耳で決めているんですけど、もうずいぶん前にディスコンティニュードになってしまったヘッドホンAKG※のK501、これじゃないと最初のモニターができなくて、他のヘッドホンだとわかんなくなっちゃうんですね。
これを使ってソフトウェアで作ったもの、出来上がったものを確認作業という意味でHarbethのHL-P3ESRと80年代のDynaudio Special 1で聴きます。アンプはBJ ELECTRICの社長 石河さんの設計されたアンプを使っています。とても良い、すごく「普通」な音を出してくれるアンプですね。
この自分の環境で聴くのとは別に、DynaudioとカナダのオーディオメーカーMoonの現行品を使って、大きなスピーカーで大きな音でモニタリングします。
プロがプロオーディオの機材を使って制作した音源を、リスナー側の位置から、普通に手に入る民生機で聴いたらどうなるか、という立場をぶれずにリマスターする、というふうにやっています。
※AKG : 1947年にオーストリア・ウィーンで設立されたプロ用音響機器メーカー。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンありがとうございます。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaオーディオユニオンの皆さんは試聴室でB&Wでもモニターされたそうですね。D4※ でしょ?すごいよなぁ・・・。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンそうですね。出たばかりの804D4や805D4でモニターしました。D4ってユニット間の音のつながりが凄く良いんですよね。前作のD3からすごく進化しています。つながりの良さと音の広がり、音が空間に浸透してくるような感じに圧倒されます。
804D4はコンパクトなトールボーイ、805D4はブックシェルフタイプなんですが、それでも相当な空間の支配力があります。以前D&M※ さんの試聴室で801D4を聴きましたが、それは本当に・・ただすごいな・・・という感じでした。
※ B&Wのフラッグシップ800D4シリーズ : 最もコンパクトな805D4から最も大きな801D4まで、その他センタースピーカーやサブウーファーもラインナップされている。
※ D&M : 国内ブランドDENON, marantzの製造販売をはじめ、B&W, DALIなど海外ブランドの輸入販売も手掛ける商社。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaすごいなぁ、まだ聴けてないんですよね。聴きたいなぁ。
マスタリングの難しさ
 オーディオユニオン
オーディオユニオンそれでは、実際マスタリングをされて、苦労された点などはありますか?Yosiさんはご自身の曲も収録されているわけですが。いかがでしょうか?
『Electronic Music for Loudspeakers Vol.2 Selected by audiounion』
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaそうですね、既に選ばれた時点でやっぱり音の良い曲は多い、と思いました。なので、元の良さをどうやって殺さずに、通して聴いた時にうまく流れるように、引っ掛かりが無いように、できる限りいらないことをしない、っていうのを考えました。
全部揃えようとすればするほど、元の曲を悪くしちゃう気がしていて。結構そこばっかり悩みますね。
例えばこの中で言うと、starRoさんの曲はやっぱりちょっと作り方が違う感じがしますね。やっぱりアメリカで長く活躍されていたから、アメリカっぽい低音の出し方ですね。そういうクラブっぽいかっこよさっていうのを、あえて他の曲に合わせる必要はないし、結局あんまりいじってません。
結構全部の曲が雰囲気が違って音圧も違うけど、これをどう揃えるかって、好みとかセンスが出ちゃうと思うんで、これはほんと悩ましいんですよね。
でも人の曲を触らせてもらうっていうのは、すっごい勉強になりますよね、毎回。普通のリスニングとはまた違うところまで踏み込んで、それもただ聴くだけじゃなくて触っちゃうっていうのは、普通はあり得ないですから、それはすごく良い機会をもらったなって思いますね。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンKuniyuki Takahashiさんは、ご自身でマスタリングされてますし、マスタリングエンジニアとしてもすごく有名な方でいらっしゃいます。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaそうなんですよ!僕が(今回のコンピで)「Kuniyukiさんの曲をマスタリングしている」って言ったら、みんなすごい驚いてますね。「えぇっ!」とか言って(笑)
 オーディオユニオン
オーディオユニオンYosiさんにもうひとつお聞きしたいんですが、トラックダウン・データとマスタリングされたデータが結構違う、要するにマスタリングで色付けしているというパターンも、世の中には結構ありますよね。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaマスタリングに何を期待されるかっていうことなんですけど、できればご自身が作られた、ミックスが終わった段階がベストの状態であって欲しいのは、そうなんです。
そういう意味では、Eilex HD Remaster、これ、すごくいいなと思ってるんですけど、やっていることが明快というか。倍音が乗るっていう部分、たぶん2倍とか4倍が乗っているんじゃないかと思うんですけど、効果がはっきりわかるし、頼んだ時点でどういう音になるっていうのが期待できます。しかもあまりデメリットを感じないんですよね。僕、もしプラグインがあるならめっちゃ欲しいんですよね(笑)
 堀部公史
堀部公史Eilex HD Remasterって、ほんとプラグインがあったら欲しい、ってあちこちから言われます(笑)
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaああ、やっぱり(笑)
 堀部公史
堀部公史ダメ―、って言って出さない(笑)
Eilex HD Remasterとは
 オーディオユニオン
オーディオユニオンそもそもEilex HD Remasterってどんなものなんでしょうか?あわせて堀部さんの作業で苦労された点なんかもあれば、お願いします。
 堀部公史
堀部公史何をやっているかというと、さっきもお話したんですが、やっぱり「倍音生成」なんですよ。
そもそもの倍音生成って、例えば人間の声とかアコースティックな楽器とか、通常のレコーディングの段階で、現場では本当はこういう倍音が出てるのに、マイクがその特性上拾いきれない、というところ。その部分を「きっとこうであったろう」という想像力をもって元に戻してあげる、という認識でいます。
次に、苦労した点ですが、クラシックだったり、アコースティックな楽器だったり、人間の声だったり、それらの自然界にある音に対しての倍音生成というのは基の音が崩れることってないんですよね。ところがエレクトロニック・ミュージックは少し違う。そもそも倍音というものがこの自然界にない音に対して、どういう解釈で挑めばいいのかなっていうところで、結構悩みました。
一番苦労した曲が、最後のChari Chariさんの曲。例えばガットギターのピエゾで拾っている音。「プップッ」という感じのアタックの音が、処理を加えると「チッチッ」とか「ピッピッ」になってしまったり、出てくる音が変わってしまうということ。それと3曲目のAOKIさんの曲。「チチチ」という音が「チェチェチェ」に変わってしまう、という事態が発生するんですね。
そもそも基音に対する倍音という考え方が、人工的に作った音は自然界の音と違うんだな、というところに直面しました。
あとはYosiさんの曲で、ページをぺらっとめくった時に流れる空気みたいなものが、より出てくれると、いわゆるハイレゾリマスターということの意味が出てくるのかなと。最後に鉛筆をコロンコロンとおくところの立体感、鮮明さが出てくると、リスナーの皆さんもわかりやすいかな、というのを意識しました。
少し影濃くしてみました、とか、立体的にしてみましたとか、ある意味音楽的ですが、ちょっと離れた視点でリマスタリングしている、というのが僕の作業になるかもしれません。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawa僕は今回の主旨、一回目(一作目)から聞いていたので、わかっていました。大事なのはEilex HD Remasterの作業であって、僕はその前の下準備として整えるだけという意識。これは普段のマスタリングとは結構違うんですよ。その作業(リマスタリング)を見越してその前の下準備ですね。めったにないことですからね、こういう二段階共作で進めていくっていう作業は。すごく新鮮でした。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンちなみにエレクトロニック系のアーティストさんはマスタリングまで自分で終わらせる方も多いですが、そういう立場からするとEilex HD Remasterっていかがですか?
 Yosi Horikawa
Yosi HorikawaEilex HD Remasterに頼むって最初からわかってたら曲の作り方も変わってくると思います。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンそれは、すごく面白いですね。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawa途中で、中域の抜けが欲しいっていう要望いただいた曲、あったでしょ。たぶんこれEilex HD Remasterでその辺にまで良い影響が出る、と思って。僕はそっちに期待しようとして、あえて自分では処理しなかったんですよ。そういうことが曲作りにも起こってくると思うんですよ。
やっぱりこの技術は面白いんですけど、これをどうコントロールされるかですよね、ホントに。
 堀部公史
堀部公史Yosiさんのゲインの整え方とか、返ってくる音の太さとか、アルバムトータルですごくやっぱり流れができていて、今作もとても良いアルバムで。これをなんとか崩さないで、僕の段階で台無しにしないように、何とか上げたというのが、本当に(笑)。
おじさんにも聴いて貰いたい
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaこのアルバム是非、おじさんに買って欲しいですよね(笑)。これがきっかけで、うわぁ、こんな面白いアルバムがあるのかって。そういう世界に引きずり込むっていう。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンそこも目的としてはあるんですよね、確かに。
 堀部公史
堀部公史何人かから「これ、どういう音楽と解釈すればいいのかな」っていう質問受けたことがあったんですけど。「僕は掲げている絵を見ているくらいの感じで聴いてますよ」っていうふうにお答えしました。じっくり見れば細かいところも見えるし、壁にスッて掛けておけば、コーヒーを飲む時間の彩りにもなる。いろんな聴き方ができる音楽だなって僕は思いますね。
 オーディオユニオン
オーディオユニオン今回の選曲はクラブミュージックやエレクトロニックミュージックと言われる中でも、「聴けるエレクトロニック」、本当にコーヒーを飲みながらじっくりも聴けるし、でもノリもいいという、そのバランスも考慮しながら選曲しました。
 堀部公史
堀部公史Yosiさんに教えていただきたいんですが、アーティストさんとして製作された音源をどういう風に聴いて欲しいとか、きっとこういう風に聴いているんだろうな、といったイメージって持たれているんですか?
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawa僕はもう、とにかくいろんなところで聴いて欲しいです。自分の今まで音楽を聴いてきた体験で言うと、本当に大事なアルバムって自宅でじっくり聴くんですけど、例えば電車の中で、ウォークマンとカセットテープで聴いたり、電車の窓から風景が流れながら聴く音楽って、またすごく好きやったりするんですね。
その人がいつ聴いたってこと、凄い重要やと思うので、できればいろんなところで聴いて欲しい。トイレでもいいし、お風呂でもいいし、なんなら僕が想像もしないようなところで聴いて欲しい、ぐらいに思っています。
 堀部公史
堀部公史オーディオの機械もそうですけど、ちょっとかしこまりすぎているというか、もっと楽に聴いてくれればいいのになって思う時が多分にあるんですよね。
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaそういう意味では、このアルバムって、ある意味いい肩の力の抜け具合っていうか、ランニングしながら聴いてもいいし、とにかくいろんな場所で聴けそうな音楽。それも、音質にこだわっているっていう軸がしっかりあって、面白いチャレンジですね、やり方としても。
 堀部公史
堀部公史ほんと、僕もそう思いますね。
リスナーに向けて
 オーディオユニオン
オーディオユニオン最後に、お二人からリスナーの方に一言いただけますか?
 Yosi Horikawa
Yosi Horikawaまず、選び方がいわゆるコンピレーションとは全く違う。音質っていうところに軸があるのがとにかく面白かったのと、アルバムとしてもまとまりがうまく出ていて楽しめると思います。
かかわってる皆さんがこの一曲、絶対良いものにしようって、ここまで話し合って高めてく。しかも皆さんが一曲一曲に対する思い入れと分析までちゃんとあって、この曲はこうすべきという考えまである。なかなかそこはめったに出会えない機会なんで、そういう意味でも有意義でした。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンありがとうございます。では堀部さん、最後にリスナーに向けて。
 堀部公史
堀部公史選曲とそれぞれのトラックで演奏しているミュージシャンと、一流の人が本気でやっているアルバムです。僕も本気で一緒に仕事をさせていただきました。一流の人が本気で頑張ったアルバムだからこそ、リスナーの皆さんには楽に聴いて欲しいな、と思います。
また、これをきっかけに、今の最新の音楽・アーティストさんにもこんなに楽しいことやっている人がいるんだ、と気づいていただくきっかけになるとすごく嬉しいなと思いますね。
 オーディオユニオン
オーディオユニオンお二人とも、今日はお忙しい中、ありがとうございました。

Yosi Horikawa
環境音や日常音などを録音・編集し楽曲を構築するサウンド・クリエイター。これまでのリリース『Wandering』、『Vapor』、『Spaces』、それぞれTime Out、The Japan Times、The Guardian等、多数媒体のBest Album of the yearに輝く。リリースの度にワールドツアーを行い、Glastonbury Festival, Sónar Barcelonaを始めとする多数の世界的大型フェスティバルに出演。また2014年には自身の音楽制作過程を追ったドキュメンタリームービー「Layered Memories」が完成し話題をさらった。楽曲リリースの他、光州デザインビエンナーレにおいて建築家隈研吾の作品のためのサウンドデザイン、イタリアの革製品ブランド〈Furla〉やファッションデザイナーKansai Yamamotoのコレクションやブランド音楽の制作、東急プラザ銀座内〈METoA Ginza〉のエレベーターのサウンド・デザイン、八丁堀のSound & Bar〈HOWL〉のサウンドシステム設計・製作を手がけるなど、幅広い分野において活動している。
https://yosihorikawa.bandcamp.com

堀部公史(ほりべさとし)
1968年3月生まれ。オーディオ業界人であった父親の影響から、幼少期よりオーディオと音楽に親しむ。1996年、ハーマンインターナショナル株式会社に入社し、営業・広報を担当。2016年に自らの法人、BEAT & VOICE合同会社を設立し独立。オーディオブランドのコンサルタントをはじめ、オーディオにかかわる活動は多岐にわたり、現在はDynaudio Japan直営のオーディオショップ On and Onの店舗責任者も務めている。また、Eilex HD Remasterエンジニアとして、Phoridgeレーベル「Electronic Music for Loudspeakers」二作の他、井筒香奈江の諸作品、NAXOSレーベル作品のリマスタリングも手掛けている。エンジン付きの乗り物と葉巻をこよなく愛する。お酒は呑めない。

ARTISTS: V.A.(selected by audiounion)
TITLE:『Electronic Music for Loudspeakers Vol.2』
RELEASE DATE: 2022.02.02
FORMAT: CD
LABEL: Phoridge
CATALOG: PHOR2(CD)
TRACK LIST
1.Go Hiyama / Embrace
2.mouse on the keys / Earache
3.AOKI takamasa / Rhythm Variation 02(2021 NEW Mix)
4.Kaito / Beyond the Horizon -another sky-
5.kuniyuki takahashi / The Guitar Song (Original Mix)
6.Kaoru Inoue / The Invisible Eclipse feat.Jebski
7.starRo / It’s Over (ft.Jarell Perry)
8.Yosi Horikawa / Letter
9.YOUR SONG IS GOOD / Waves(Gonno Remix)
10.CHARI CHARI / Luna de Lobos (Prophet’s Harmonic Drone Mix)
Mastered by Yosi Horikawa
Hi-Res Remastered by Satoshi Horibe (BEAT&VOICE / eilex HD Remaster)
https://www.audiounion.jp/ct/detail/new/188611/FEATURESaudiounionphoridge