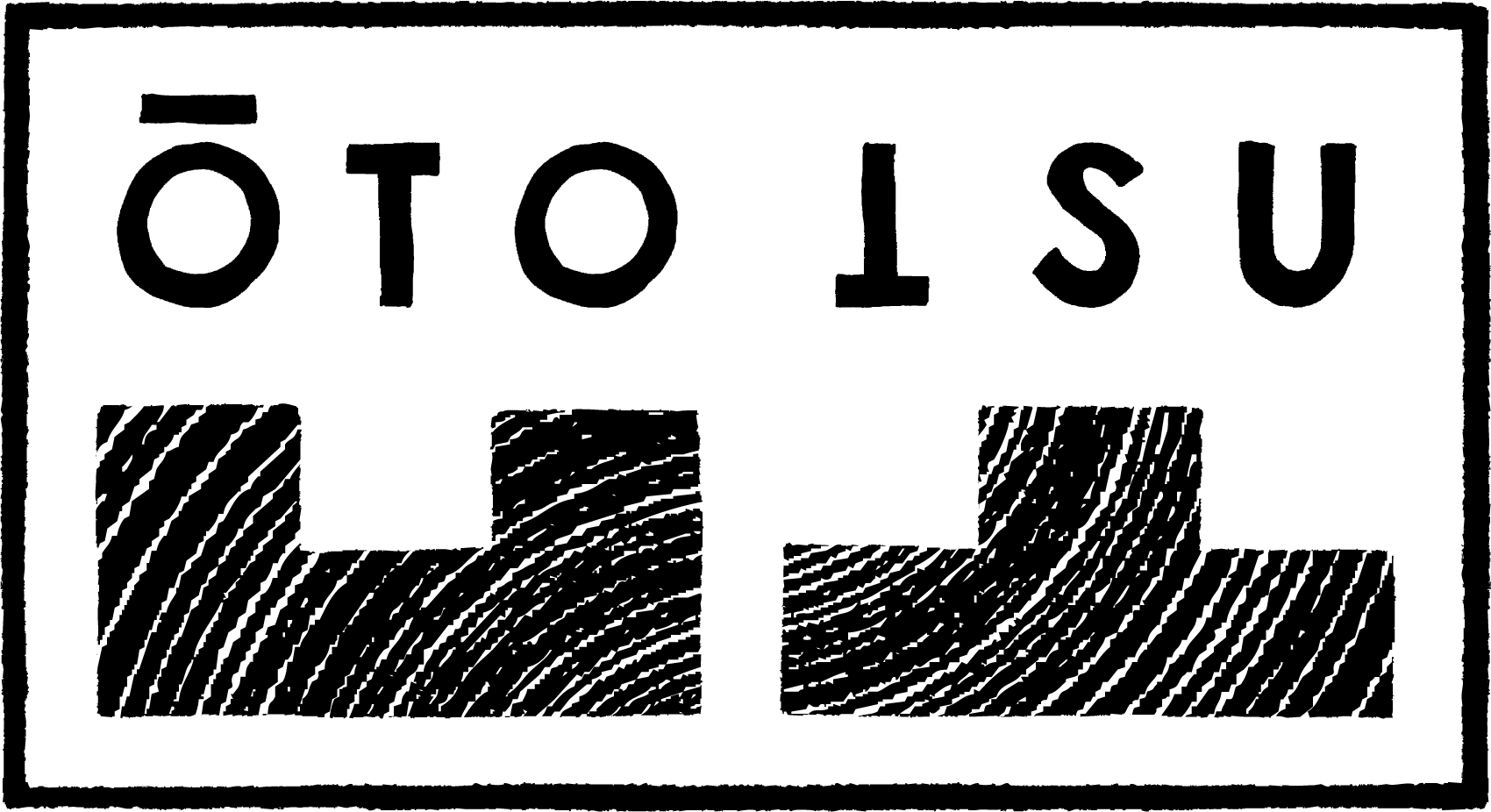全国に先駆けて独自の発展を遂げる宇都宮シーンの中核を担うバンド、Someday’s Goneのニューアルバム『INDIE MANNERS COLLECTIVE』が凄いことになっている。90’sエモやパンク、ミクスチャーやシティポップ、ヒップホップからインディーポップまでを縦横無尽に散りばめた楽曲に、メンバーがリスペクトする豪華プロデューサー陣を配した最強の全20曲。彼らはいかにしてこのマスターピースをものにしたのか? 西谷隼(Someday’s Gone)、ヒダカトオル(THE STARBEMS)、TGMX(FRONTIER BACKYARD)、渡邊忍(ASPARAGUS、ex. CAPTAIN HEDGE HOG)によるスペシャル対談で、その内幕を探ってみよう。
インタビュー・テキスト : 宮本英夫 撮影:工藤成永 編集:上野雅浩(OTOTSU 編集担当)
 TGMX
TGMXいま何歳だっけ?
 西谷
西谷30です。
 ヒダカ
ヒダカ30前後って、俺の印象としてはバンドっぽいものをあまり聴かない世代という感じなんだよね。ヒップホップも聴くし、ボカロっぽい打ち込みにも抵抗ないとか、30から下の世代にはそういう印象がある。
―実際、どうなんですか。西谷さんのルーツというと。
 西谷
西谷ルーツはJIMMY EAT WORLD、The Get Up Kidsとかですね。宇都宮という街が、そういう音楽がすごい好きなんです。BEAT CRUSADERSの『P.O.A.』も、中学生の時に買いました。
 ヒダカ
ヒダカ宇都宮は特殊なエリアだよね。HELLO DOLLY(ライブハウス)チームが、そういうのをずーっと好きでやってるみたいな感じ。タガミ(TGMX)くんたちの影響を受けた連中がちょっと残りながら、バンド文化を、それこそCALENDARSとかの影響で、Someday’s Goneとか、Lucie,Tooとか、ほかのエリアではあまり見ない密集度というか、「こんなにまだバンドが盛んなんだ」って。
 西谷
西谷確かに、宇都宮はバンドが多いです。同じ遊び場に集まってるイメージですね。
 ヒダカ
ヒダカ面白かったのが、俺がプロデュースした曲に、ガヤ(声の効果音)を入れるって言って、CHUCK TAYLORSとか、ライブ終わりのバンドマンが20人ぐらい来たよね。
 西谷
西谷みんなで同じブースに入って、シンガロングして。
 ヒダカ
ヒダカで、コーラスに参加したバンド達の音を聴くと皆それぞれ全然違ってて。それがうらやましいなと思った。ジャンルとか関係ないんだよね。
 TGMX
TGMX僕も栃木出身だけど、(Someday’s Goneは)ずっと知ってる後輩じゃないんですよ。でも話してみたら、僕の知り合いのバンドが好きで、ビークル(BEAT CRUSADERS)が大好きで、ASPARAGUSが大好きでっていうことで、だんだん繋がってきた。
 西谷
西谷Niw! Recordsに入ってからですね。タガミさんのように、好きな先輩とお話ができるようになったのは。
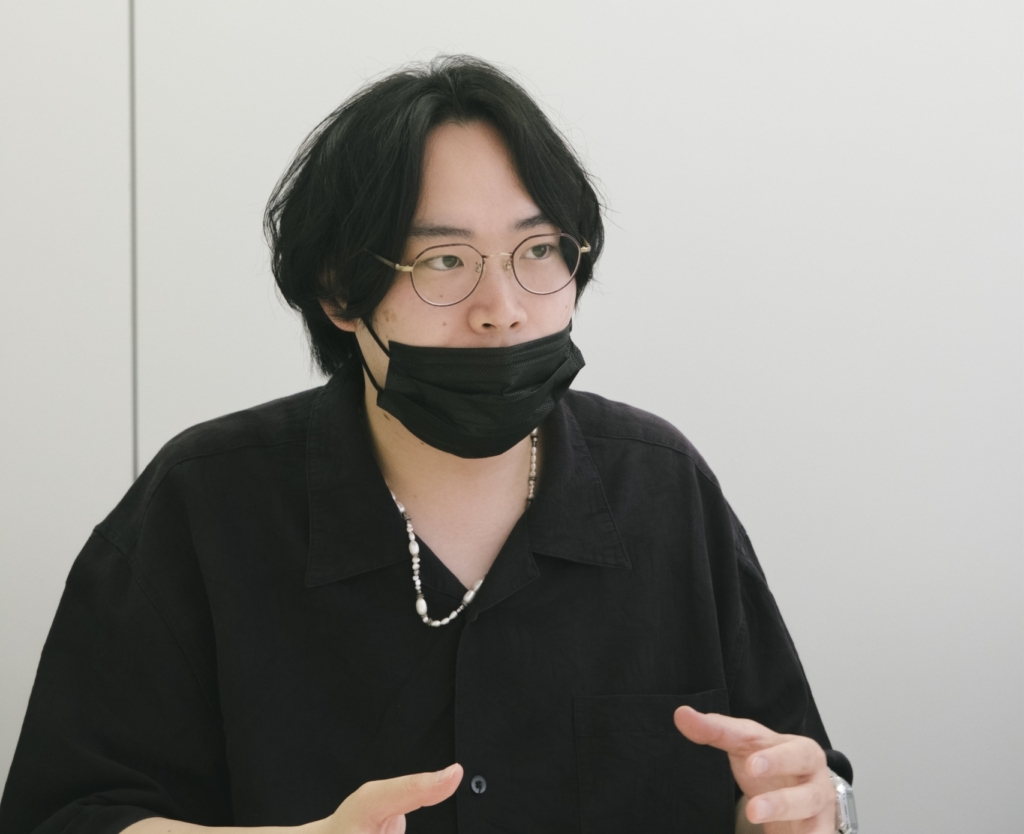
―今回、尊敬する先輩に1曲ずつプロデュースを頼むという企画は、そもそもどんなきっかけで?
 西谷
西谷バンドって自分らだけで物事を完結させがちですけど、ヒップホップはいろんな人とやるじゃないですか。ああいうのをバンドでやるとどうなるんだろう?というイメージはありました。もともとFed MUSICの(久樂)陸さんに、シングルのプロデュースとミックス、マスタリングをずっとやってもらってたこともあって、楽曲の自分らで詰め切らない部分が良くなるってすごい思ってたんで。いろんな人とやったらどうなるんだろう?と思って、頭に浮かんだ順番に上から声をかけていったら、全部決まっちゃいました。
 ヒダカ
ヒダカしかも、えらいのは、プロデュース料は自腹なんですよ。
 西谷
西谷自腹です!
 ヒダカ
ヒダカそんなのいないでしょ。普通はレーベルに頼んで、予算的に無理だってなったらあきらめるんだけど。
 TGMX
TGMXこのメンツ、人数はなかなか頼めないですよ。
 ヒダカ
ヒダカだから、相当ディスカウントしましたよ(笑)。
 西谷
西谷ありがとうございます!みんなサラリーマンでしっかり働いてるので、そのお金を切り崩して。
 ヒダカ
ヒダカいちばん正しいやり方じゃないですかね。妥協してない。お金が理由だったら、自分で払うからいいよって、インディーとしていちばん正しいというか。レーベルに潤沢に予算があるわけじゃないって、わかってやってるから。
 TGMX
TGMX90年代式インディーっぽい感じだね。
 西谷
西谷もともと「INDIE MANNERS COLLECTIVE」というイベントを始めたのがきっかけで、このタイトルになったんですけど。ずっと宇都宮に住んでると、居酒屋さんや服屋さんと仲良くなったり、いろんなハブができて、自分らの音楽を通してそれを繋いでいく、みたいな活動ができたらいいなと思っていて。それをCDにするならこういう形になるのかな?という思いもあったりして。
 ヒダカ
ヒダカEZ DO MARKETっていう服屋兼飲み屋があって、すごいオシャレなんですよ。REC中のケータリングもそこに買いに行って、服屋なんだけど、真ん中にテーブルがあって中で飲んでいいよって。面白いでしょ?

 TGMX
TGMXというか、ヒダカくん、宇都宮行ったんすか?
 ヒダカ
ヒダカ行きましたよ。
 TGMX
TGMXヤバいね。俺はもう「おまえらが来い」って。僕がよく使わせてもらっているスタジオ、エンジニアなら作業が予想出来るなと思ったので。
 ヒダカ
ヒダカそこの予算、大丈夫だったの?東京と宇都宮じゃ、スタジオ代も違うから。
 西谷
西谷それもタガミさん経由で、お願いしていただいて。
 ヒダカ
ヒダカディスカウントしてもらったんだ。
 西谷
西谷してくれたと思います。今回、自分らでHELLO DOLLYで録った曲も、HELLO DOLLYの久保(店長)さんにレコーディング代をディスカウントしてもらって、全部やっていただきました。
 TGMX
TGMXタイトルを『DISCOUNT』にすればよかった(笑)。みんなに頭上がんないね。
 西谷
西谷上がんないっす。
 ヒダカ
ヒダカ売れないとヤバイね(笑)。
 TGMX
TGMXみんなのディスカウントが乗ってるからね(笑)。

―曲とプロデューサーのマッチングは、どんなふうに考えていったんですか。
 西谷
西谷作ってる時点で「この曲だとこの人に合いそうかな」というものを、2曲ずつぐらい投げたりしました。
 ヒダカ
ヒダカ「INDIE MANNERS COLLECTIVE」って、俺が書きそうな曲だもんね。
 TGMX
TGMXヒダカくんのやつ、「ビークルじゃん、これ」と思った。
 西谷
西谷あはは。やった!
 ヒダカ
ヒダカだから、めちゃめちゃビークルっぽくしましたよ(笑)。音決めに相当時間かけたもん。ちょっとインディーっぽくしたけどね、メジャーのビークルよりは。
―TGMXさんの曲「All The Small Things」は?
 西谷
西谷タガミさんの曲は、カッチリしたバンドサウンドに打ち込みも載せてる、みたいな楽曲だったんですけど、オケを全取っ換えされました。
 TGMX
TGMXだいたいいつもそうなんだけど、まずは100%TGMXでやらせてもらうんですよ。「良ければ使ってください、ここからマイナス、修正していってください」というやり方です。存在感ないプロデュースはあんまり誘ってもらった意味がないのかなって思うので、ある程度は自分の手垢を残したいし、誘ってくれた理由はたぶんそこだと思うから。でも話をしているうちに、彼は最近の音楽もよく聴いていて、話が合うところもあったんで、じゃあこの曲はそっちで行こうと。話を結構しましたね。
 ヒダカ
ヒダカあえてバンドっぽくなさを出してる。
 西谷
西谷すごい反応良かったです。そもそも俺らがこんな曲できると思ってる人がいないんで。
 TGMX
TGMXアレンジをこうしたらいいんじゃね?という時に、リファレンス(参考音源)をくれたアーティストって誰だっけ。
 西谷
西谷Twenty One Pilotsとか、あのへんですね。
 TGMX
TGMXそうそう。あと、The 1975とか。僕がやりそうなラインだなって。
 ヒダカ
ヒダカバンドだけどそんなにバンドっぽくない。弦楽器の音圧がわりと薄い。The 1975の新曲、めっちゃ薄いもんね。Twenty One Pilotsも、ギターがほぼ聴こえない。
 西谷
西谷聴こえないっすね。
 TGMX
TGMXお二人は(ヒダカ&渡邊)はギターチームだと思ったから、僕はそうじゃないやつをやった方がいいかなっていう感じ。
 ヒダカ
ヒダカそこらへんは、今のバンドキッズの悩みどころでもあるんだろうなと思ってて。あんまりラウドにギターを歪ませちゃうと、うるさいと感じちゃうし。自分もたまにあるから。ヒップホップ寄りでロックっぽいことをやってる子たちも最近増えてきて、そういう子たちはトラップとかを聴いて、XXXテンタシオンとかを聴いてるから、ギターがそんなに歪んでなくて、ジャングリーな感じで、そのバランス感を生でやるのは実は難しい。
 TGMX
TGMX特に日本だとね。
―あ、遅れていた忍さん、来ましたね。
 渡邊
渡邊どうもどうも。お待たせしました。
―西谷さんから見て、どんなプロデューサーだったんですか。「Eighteen」を録った時の忍さんのやり方は。
 西谷
西谷忍さんのスタジオで録らせてもらったんですけど、個人的に、あんなに限界までテイクを録ったのは初めてです。録れるまで録ろうというレコーディングを、今までやったことがなかったので、それを初めて経験しました。それまで、(録ったあとに)直されるのが当たり前だったんで。
 渡邊
渡邊今は経費とか時間の問題とかで、なるべく早く済ませて、エディットして、結果が良ければいいじゃんという感じじゃない?それは全然いいんだけど、ただ僕がやってるASPARAGUSとかは、人力が好きで、しつこくやるのが好きなんで。
 ヒダカ
ヒダカ気合で決めそうだよね。特にドラマーが(笑)。
 渡邊
渡邊それに慣れてるのと、あと今回の音源を聴いた時に、最初は生っぽさプラス打ち込みみたいなアレンジが入ってて、それを生っぽい方向にシフトしようってなった時に、だったらなるべく人力で、揺れとかあいまいな部分もOKにしたほうがいいんじゃないか?と。直すときれいになるんだけど、「らしさ」みたいなものが出にくくなるから。今は直すほうが主流だっていうから、じゃあ俺の時はちょっと頑張ってやってみない?みたいな感じ。
 ヒダカ
ヒダカ何テイクぐらい録ったの?二桁は行ってる?
 渡邊
渡邊全然行ってる。
 西谷
西谷歌は100回ぐらい歌った気がします。
 TGMX
TGMXそれはすごいな。
 渡邊
渡邊僕、自分のレコーディングでも100回ぐらい歌うから。歌ったあとにテイクを選ぶ時に、ひとつの言葉を替えたり、そういうこともやるし、どっちのやり方も持ってるけど、今回はこういうやり方のほうが本人たちも自信がつくかな?と思ったんで。「もう辛いです」ってなったらやめようと思ってたけど、でもけっこう楽しんでやってくれたから。
 西谷
西谷すごい楽しかったです。
 ヒダカ
ヒダカタガミくんは、どういうやり方をしたの?
 TGMX
TGMX俺はメールでやりとりをたっぷりしてからスタジオにデータ流し込みですよ。
 渡邊
渡邊データのやり取りで?
 TGMX
TGMX最終的にはスタジオで調整はやったけど。
 ヒダカ
ヒダカ二人とも関東に来させてる。宇都宮に行ったのは俺だけ?
 渡邊
渡邊ダカさんがいちばん熱意あるよ。それにしても、アルバムのボリューム、すごいよね。しかもちゃんと工夫を凝らしてて、飽きさせないようにしてる。
 TGMX
TGMX俺はさておき、ヒダカくんと、忍と、TA-1(KONCOS、LEARNERS)とか、これだけの人をよく集めるよなって思った。
 渡邊
渡邊TA-1はどの曲をやったの?
 西谷
西谷6曲目の「Yellow」と、最後の「Bender」という曲です。
 渡邊
渡邊ああやっぱり。この2曲、Niw!っぽいなと思って聴いてた。
 ヒダカ
ヒダカTA-1のやつ、渋谷系っぽいね。そっちに寄ったなと思った。
 西谷
西谷いいってことですか?
 TGMX
TGMXいい。曲の幅がすげぇなと思った。こういうのも有りじゃない?コード進行が鍵盤的な、TA-1の色が出てる。
 渡邊
渡邊いいよね。あと、違う曲(10曲目「Bubble」)の、女の子の声は誰?
 西谷
西谷あれは地元の友達です。
 渡邊
渡邊あれもすごい良かった。あと、ラップやってる人は?
 西谷
西谷あれも友達です。「27Club」でラップやってもらいました。ラッパーで、バンドやってる子で。
 渡邊
渡邊それも面白かったね。西やんは器用な男だから、器用さがすごく出てるし、イントロの入り方もちゃんと考えて、物語っぽく作ってから入って行くとか。しっかりアルバムとして作ってるんだなってすごく思った。
 ヒダカ
ヒダカたしかに俺がプロデュースした1曲目とか、頭にSEっぽいのが入ってて。たぶん普通にえらいプロデューサーさんだったら、「これ取れ」って言うよ(笑)。
 西谷
西谷あれはNo Use for a Nameのパクリです。「Biggest Lie」という曲が蓄音機の音から始まるんで、それを自分のアルバムでもやりたくて、無理やりぶちこみました。
 TGMX
TGMXいいね、そういうストーリー。
 ヒダカ
ヒダカそういう青さは、ちゃんとそのまま残してあげたい。俺もインディーズの頃、ジャケットに自分で英語の文字を書きたいとか、今考えるとなんでそんなこと言ったのかわかんないんだけど、結果やって良かったなと今すごい思うし。
 渡邊
渡邊こだわりですよ。
 ヒダカ
ヒダカそういうの、あとで振り返ると楽しいからね。これは絶対生かしてあげたいなと。
 渡邊
渡邊サブスク時代を、いい意味で無視してる感じもいいじゃないですか。サブスクだと、あそこを待てない人もいるから。でもそういうことを気にしないで、自分たちの作品として全部入れてるなというのが、素晴らしいなと思った。あと7曲目の「2000」のイントロのオマージュ感も、懐かしくて良かった。1曲目から5曲目までの間は、激しい感じというか、マシン・ガン・ケリーじゃないけど、そういうニュアンスもあって、6曲目「Yellow」以降は新しいチャレンジもあって。前も話したけど、バンアパ好きでしょ?
 西谷
西谷好きです。
 渡邊
渡邊好きな感じがメロディに出てるんだよね。特に6曲目以降に。それがスッと入ってくる、それもいいなと思った。俺が言うのもえらそうだけど、アルバム通して、いいよね。飽きさせない気持ちがすごく出てる。
 ヒダカ
ヒダカ逆に言うと、西谷ならではのメロディ癖みたいなものが、あんまりないと言えばないから。あるんだろうけど。
 西谷
西谷ああー。なるほど。
 ヒダカ
ヒダカ俺とかシノッピ(渡邊忍)とかタガミくんは、もうわかるじゃん。「この人の曲だな」っていう感じが、意識しなくても出ちゃう。
 TGMX
TGMX節(ぶし)ってやつね。言われてうれしいかどうかは別として。
 ヒダカ
ヒダカ曲を発注される相手によっては、それを入れてほしいんだろうなって、わざと強めに入れちゃう時もあるし。そこで「西谷と言えば」みたいなところを、今後どういうふうに出して行けるか。メロディとかコード感とか、歌い方でもいいかもしれないし、何かしら自分印みたいなところがあればとは思う。
 西谷
西谷ああー。そうかー。
 渡邊
渡邊さっきも話したけど、すごい器用だから、何でも吸収ができる。好きなものがちゃんと出せるというのが得意な部分でもあるだろうし、ヒダカさんが言ったように、おのれ節みたいなものも、これからもっといろんな音楽を聴いて、もっと好きなものが増えれば、それがミックスされて出てくるのかなと思ってるけど。

 ヒダカ
ヒダカあと、英語詞もちゃんと翻訳を頼んでるんでしょ?元OCEANLANEの…。
 西谷
西谷はい。ハジメ(Hajime Takei/The Coastguards)さんに頼んだ曲もあります。
 ヒダカ
ヒダカ「INDIE MANNERS COLLECTIVE」の歌詞も、すごくいいんですよ。確かに自分でも歌いそうな歌詞でもあるなと思ったし、「絶対やめません、絶対あきらめません」みたいなことを、宇都宮でちゃんと叫びたいんだなっていうのがすごい伝わるから。おのれの住んでる街でこれを歌わなきゃいけない使命感みたいなものを、ちゃんと英語の文法としても合っていて、海外の人が聴いてもいいようにしてるのはすごいなと思った。これも自腹なんでしょ?
 西谷
西谷自腹です(笑)。
 ヒダカ
ヒダカCDプレスと流通はレーベルで、プロデュース代とかは自分たちでまかなう。最初にも言ったけど、インディーとして正しいやり方だよね。
 TGMX
TGMXサウンドも、古いものと新しいものがあって、やり方も、古いものと新しいものとどっちもあって。30歳でこの感じは、新しいなと思う。俺たちだったら、どっちかしかできなかったと思う。
 渡邊
渡邊時代背景もあるのかなと思うよね。今の時代、レーベルがそこまで経費をかけられない時に、自分たちはどうするか?を考えて行動したところに、すごく時代を感じるというか。
 ヒダカ
ヒダカリスナーでさえ、そこに気づいている人は多いからね。
 渡邊
渡邊それで応援したくなる人もいるだろうし、かといって、完全におのれだけでやるとなったら、こんな取材もなかっただろうし。レーベルの力と、自分たちで行動する部分と、どっちもあって、今の時代にマッチしてるのかなと思いましたね。
 西谷
西谷ありがとうございます。
―そして、CDが出たらリリースライブ。なんと、今日のメンバーが全員出演するライブが決まりました。西谷さん、発表してください。
 西谷
西谷10月15日にリリースイベントをやります。「INDIE MANNERS COLLECTIVE」という、宇都宮のライブハウスを使ったサーキットイベントで、お三方にも出ていただきます。僕ら、この街をどうしていくか?というところに焦点を当ててるので、文化として俺らの活動が街に残っていけば、もしも俺らが活動できなくなっちゃっても、残って行くであろうという気持ちも込めて、やっていけたらなと思います。
 ヒダカ
ヒダカえらいよね。俺は千葉を出ちゃってるし(笑)。横浜もバンド数はあるけど、こんなに縦と横が繋がっていかないでしょ?
 渡邊
渡邊そうだね。
 TGMX
TGMX栃木も、俺らの時代にはあまりなかったんだよね。バンドが少なかったというのもあるけど、CALENDARS以降だと思う。
 ヒダカ
ヒダカうらやましいよね、宇都宮は。移住しろって言われたら嫌だけど(笑)。
 TGMX
TGMXやめたほうがいいって言いますよ(笑)。
 西谷
西谷ええー、そんなぁ…(笑)。
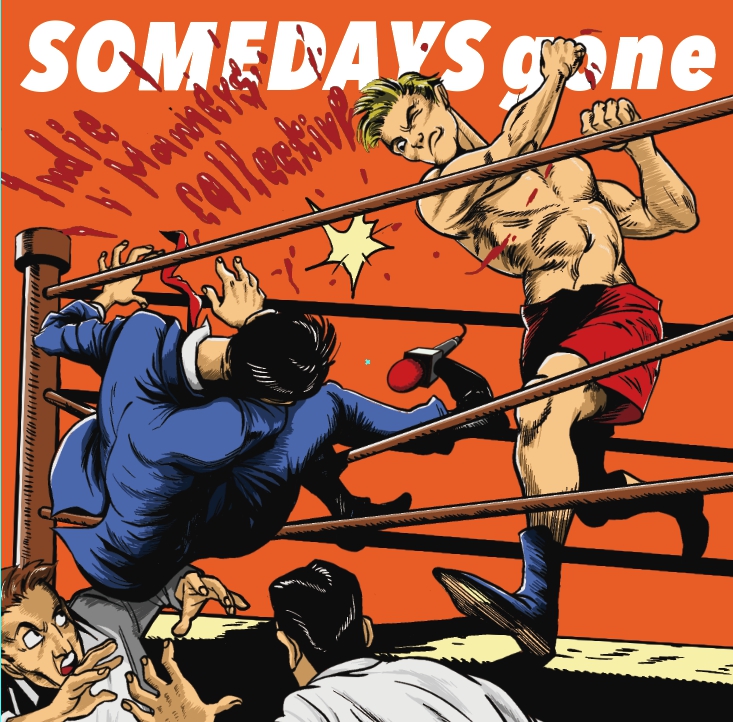
INDIE MANNERS COLLECTIVE
Someday’s Gone
2022.07.20 RELEASE
Niw! Records
- INDIE MANNERS COLLECTIVE
- Eighteen
- In Bloom
- Authentic
- All The Small Things
- Yellow
- 2000
- Interlude: moss
- Wasted on you.
- Bubble
- Slowdown
- 27Club (feat. AKI GOTO)
- Third time’s the charm.
- Don’t Let Go
- Falling Apart
- Sleepwalking
- Spacewalking
- Letmego
- Masterpiece
- Bender

2022.10.15(sat)
Someday’s Gone pre. 宇都宮2会場サーキット
“INDIE MANNERS COLLECTIVE”
会場:
●HEAVEN’S ROCK宇都宮VJ-2
●HEAVEN’S ROCK宇都宮2/3(VJ-4)
OPEN / START:TBA / TBA