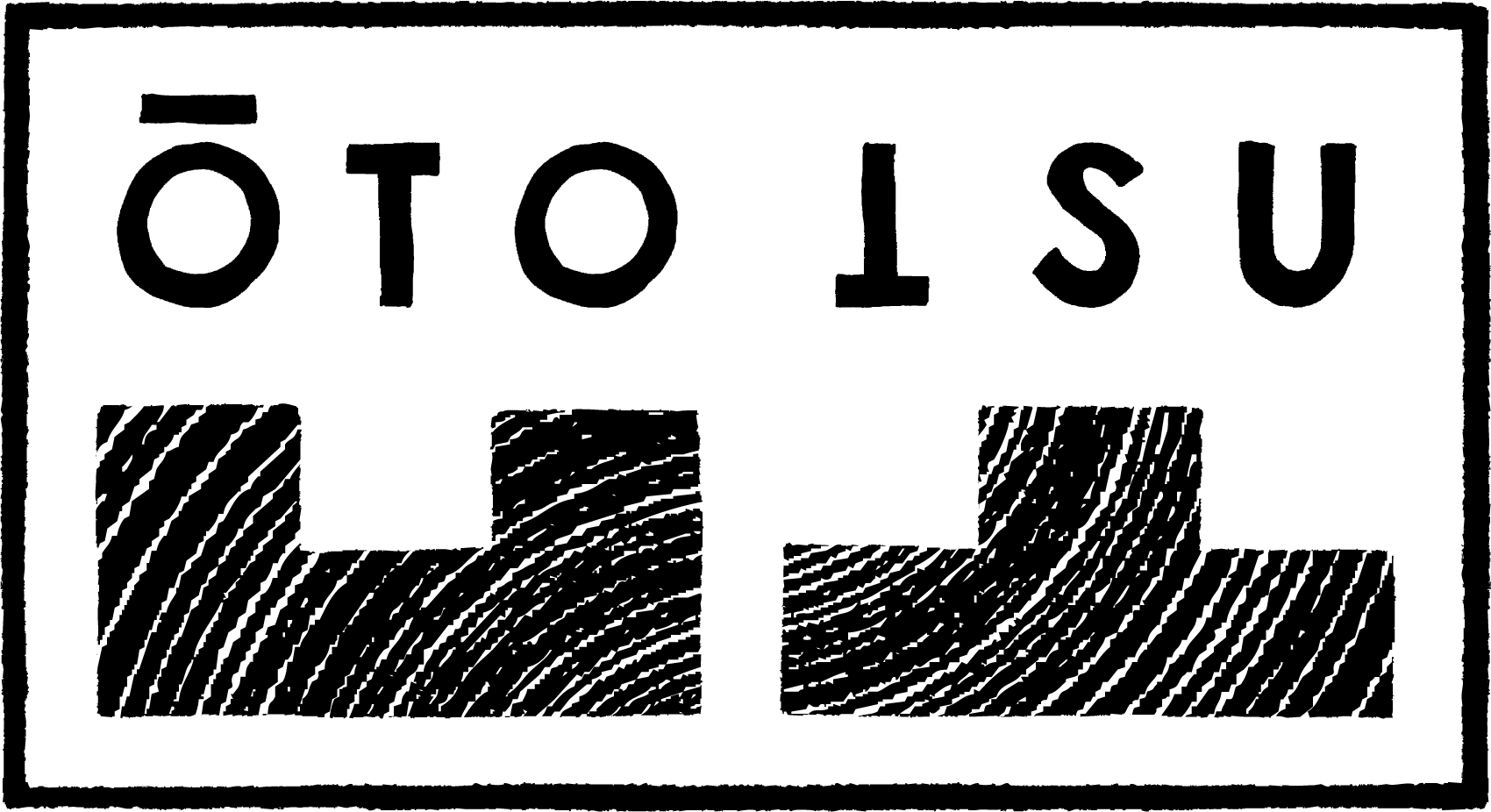強靭なライヴ・パフォーマンスや幾多のWEB ZINEなどでのレビューなど、国内のみならず海外でも”Tokyo Samurai Doom”として認知度があがっているHEBI KATANA。昨年からはTOKYO DOOM FESTを共同主宰し、活動の幅を大きく広げつつある彼らが、待望のニュー・アルバム『Imperfection』を完成させた。この4作目となるニュー・アルバムについてメンバー全員に語ってもらった。

HEBI KATANA are
Nobu : Guitars, Vocals
Laven : Bass, Vocals
T.T. Goblin : Drums
Text by Yasushi Saito (BxTxHx RECORDS)
編集:汐澤(OTOTSU)
●まずは前作『III』(2023年)リリース後の活動について教えてください。
Nobu : 2024年の1月から❝レコ発❞と銘打ってライヴを行なっていました。都内近郊はもちろん、岐阜や滋賀・彦根、大阪、名古屋、Tokyo Doom Festなど様々な場所やイベントでプレイしました。また7月には初のイタリア/フランス・ツアーも敢行しました。全6公演と、期間は短いツアーではありましたが、連日のライヴで現地のファンやバンドと交流できたこと、メンバーと寝食を共にしたことは、かけがえのない経験となりました。特に最終日のジェノヴァ公演は、バンド史上に残るライヴとなりました。Bandcamp上に音源をアップしていますので、是非チェックしてみてください!
https://hebikatana.bandcamp.com/album/live-in-genova
夏以降もコンスタントにライヴを行ない、ドゥーム/ストーナー系イベント以外にも、様々なジャンルのバンドとステージを共にできたことは、とても良い刺激になりました。実はそれらのライヴの機会を利用して、新曲も披露していました。フロアの反応をダイレクトに見ることのできる貴重な機会なので、ライヴを経てアレンジに還元することができた新曲もあります。先にレコーディング日程を抑えていましたので、逆算して秋の終わりころからプリプロに入ったと記憶しています。なかなかにタイトでしたが、進捗をメンバーとも確認しながら進めていきました。
●このトリオ編成で2作目になりますね。メンバー間のコミュニケーションはいかがですか?
Goblin:かなり良いですよ。前作『III』より団結しています。やり甲斐があります。
Laven:メンバー間の結びつきは、これまで以上に強くなったと思います。当初から相性は良かったですが、1枚のアルバムと1年間のツアーを通して、このラインナップはとてもタイトになりました。お互いにコミュニケーションを取りやすいです。
Nobu:ライヴの回数を重ねたり、雑談やビールを飲んだり…….そういう時間が、メンバーの結束を強めたと思っています。それにより言いたいことをしっかり伝えることができるようになりました。より良い作品にするためにも、時には良くないフィードバックも言い合えることが大切だと思いますね。
●本作の制作はいつ頃から進行しましたか?
Goblin:確か、去年の8月頃だと思います。
Laven:『III』の完成後、すぐに新曲とリフの準備ができたので、次作への作業がスムーズにできました。プリプロの過程では、これまで以上に一緒に作業をしましたね。今回アルバムに収録されている曲は、そのテーマに代表される感情を表しています。
Nobu:曲作りに関しては、隙間時間を活用して……(笑)。古い曲だと2024年の初頭に書いていた曲もありますね。アイデアが浮かんだら、なるべくメンバーに聴かせられるレベルのデモの形までたどり着けるようにしています。アイデア自体は出ないときは全く出ないですし、細かにiPhoneのボイスメモなどに口でリフを吹き込んだりと、コツコツとやっているのが現状です(苦笑)。なので、時期でいうと2024年の前半にデモの制作、後半からアレンジ/プリプロという感じです。
●本作は「侘び寂び」や「不完全さの美」、「円相」といった、日本独自の精神世界が題材となっているようですが、どのようにしてこのテーマに辿り着いたのですか?
Goblin:今回のアルバムのテーマを考えている時、Nobuの閃きで“侘び寂び”というのはどうか?と提案がありました。2ndアルバムの『無常』に繋がっていて面白いと思いましたね。
Laven:Nobuがソングライターとして思い描いたテーマとアイデアで作り上げ、それが最終的にこのアルバムで聴ける曲に現れた感じです。
Nobu:2024年の後半頃、ある程度楽曲のマテリアルが揃ってきたところで、全体像を把握しようと思いました。その際に「楽曲に共通するテーマやコンセプトは何か?」としばらく考えていて、ふとした瞬間に「侘びさび」はどうかと思いついたんです。自分の知る限り、そのようなテーマを掲げるドゥーム・バンドもいなかったですし。
昨今のAIや技術の進化を目の当たりにして「それとは逆のものって何だろう?」って考えました。ライヴやレコードといった「アナログ」なものも、もちろんそうなんですが、音楽以外にも少し視野を広げて、例えば古い寺院や廃墟、公園の自然だったり樹木だったりと想像を膨らませていきました。その時に仮に現代のテクノロジーが完全なものだとしたら、その逆に位置するのが「侘び寂び」や、その「不完全さの美」なのでは?と思い至ったんです。過去の作品はどちらかというと曲ごとの単発でのテーマや、言葉の響き/ノリや韻を重視していたこともあり、本作では一本筋の通ったテーマが欲しくてコンセプトを固めていきました。その際に参照したのが、松尾芭蕉や谷崎潤一郎といった古典です。はるか以前の時代の方々の言葉ですが、現代においてより一層自分には響いてきましたし、楽曲の持つイメージにも合致したので、コンセプトを固めていきました。ちなみに芭蕉記念館とその周辺は散策してたりします(笑)。 現代では、様々な場面で完璧さや答えを追い求めすぎて、息が詰まりそうになる場面が少なからずあると思います。それでも一歩引いて、その不完全さやあいまいさ、あえて光ではなく暗闇に価値や美しさを見出すそのような古典の世界観は、現代を生きる自分には衝撃的でしたし、きわめて日本的な価値観だとも思います。そういった先人の知恵をリスペクトしつつ、ヘヴィ・サウンドとの融合という形でチャレンジしました。あとこれは、後になって感じたことですが、Tokyo Samurai Doomというキャッチフレーズが広まっているのは感じていましたし、ありがたいことなのですが、中身が伴っていないな…….と自分で感じることがありました。楽曲の歌詞やコンセプトとしても、中身を伴わせたいという気持ちがありました(苦笑)。 海外のリスナーに楽しんでほしい気持ちも、もちろんありますし、日本のリスナーにも、安直なジャポネスクと捉えられないようにしたいという気持ちがありました。結果的に成功しているかどうかは、聴いていただいた方の判断にゆだねられているので、自分ではどうしようもないですが……。
●今回のジャケット・アートも秀逸ですね。デザイナーへはどういったリクエストをしていましたか?
Nobu:アートワークは前作『III』と1st『HEBI KATANA』(2020年)でもお願いした、インドネシアのDoomolithというアーティストに依頼しました。彼はバンドの世界観を完全に把握していますし、ダークでドゥーミーなアートワークはバンドのイメージにも合っています。今回は、いつも通りの蛇や刀に加え、和のテイストという依頼をしたのですが、これがなかなか難しく、最初はお互いの認識のズレを修正するのが難しかったです。なので日本古来の墨絵や、意外なところでボサノヴァのAntonio Carlos Jobim『Wave』や、ジャズのシンプルでモノトーンなアートワークを参考として伝えたらうまくハマって、今のような形に仕上げてくれたんです。非常に気に入っています。ぜひフィジカルで入手してほしいですね。
Laven:日本の 「和」という考え方が、今回の私たちのアートに大きな影響を与えたと思います。
Goblin:白の背景に円相に蛇ってなかなか無いかなと!
●前先に引き続きレコーディングはVoid)))Labの稲荷 龍飛 氏の手によるものですが、作業はやりやすいですか?
Goblin:大変やりやすいですし、安心感もあります。稲荷さんのアドバイスも参考になりました。有り難いです。
Laven:稲荷さんと仕事をするのは大好きですね。私がこれまで使ってきたスタジオの中で一番気に入っています。彼は僕らのサウンドを熟知していて、素早く簡単に調整できるんです。また彼はアナログでやるのが大好きで、それが僕らのサウンド全体にとても貢献していると思いますね。
Nobu:はい。とてもやりやすいですし、作業はスムーズです。稲荷さんもこの手のサウンドに造詣が深いですし、前作の作業を通してこちらの良いところも、悪いところも(笑)わかってくれていますので、今回も非常にお世話になりました。昨今ではリモートでミックスを行なうことも多いでしょうが、今回は三人揃って同じ空間でスピーカーから放出される音を聴きながら確認できたことがとても良かったです。
●サウンド面での変化はありましたか?
Laven:前作『III』から今まで、ほとんど同じだと思います。しかしながら個人的には、以前よりもベース・サウンドについて少し考えることができ、よりカスタマイズされたサウンドを作ることができたので、より満足しています。
Goblin:自分のテーマはヴィンテージ”風”ですね。『III』はドラムがかなり前に出ていてそれはそれで良いんですが、より繰り返し聴けるアルバム及びサウンドにしたかったんです。今回はRushの故ニール・パートや、The Policeのスチュワート・コープランドっぽさもあるかな。ライヴ感に浮遊感、実験的な要素、初期のプログレッシブ感もあり、とても満足しております!
Nobu:基本路線は大きく変わっていないと思います。使用ギターやアンプヘッドも前作と同じOrange Ampでした。稲荷さんがプレイや楽曲に合う機材をとっさにセッティングしてくれんです(笑)。強いて言うと、クリーン・トーンの場面が増えたので、そのサウンド・メイクに時間をかけましたね。歪みとは比べ物にならないほど、繊細でごまかしがきかないので、稲荷さんには今回も大いにサポートいただきました。
●本作に収録されている曲は、結構シンプルなイメージですね。
Nobu:そうかもかもしれないですね。制作中はそんなに意識をしていませんでしたが、歌のメロディーがよりハッキリしているからかもしれませんね。演奏面では意外と場面転換があるので、実際にプレイすると回数などは、たまに見失いそうになることもありました(笑)
Goblin:一見シンプルに見せかけて、実は複雑さも見え隠れしている曲もありますよ。
Laven:曲のイメージは、多くの人にすぐに伝わると思いますね。その点では、悪いことではないと思います。
●かといって単調にならず、楽曲の構成も良く練られていると思います。
Nobu:ありがとうございます。間延びしないようにリフの長さや、つなぎ目などは意識したかもしれません。構成やバートの長さはリズム隊の二人に任せている部分も多いです。二人の意見も大いに参考にしつつ、組み立てていきました。
Goblin:かなりミーティングしましたよ。楽曲のアレンジや構成を模索しながら意見交換をしました。
Laven:長尺のプログレッシブな曲にふけらなかったことには同意しますが、今までのHEBI KATANAの作品の中で、最もプログレッシブな作品だとも思います。アレンジの決定にはいつも細心の注意を払っていますね。今回のアルバムでは、それを皆さんに評価していただけることを願っています。
●ギターリフも楽曲毎にメリハリのあるイメージですね。
Nobu:リフに関しては、やはり曲の肝になる部分ですので、口ずさめるくらいシンプルかつ効果的にするべく意識していました。普段と違う音階で挑んだり、新たなリズムや他の楽器との絡みを考えたりなど。気に入っていただけたら嬉しいです。
実はリフはギターを弾いている時ではなく、映画を見終わったときや、自転車に乗っているとき、散歩しているときによく思いつきます(笑)。何でしょうね、おそらく体のリズムと連動しているのでしょうか。あとギターの指板に制限されないというか、プレイヤー的な目線に縛られないようにしています。より柔軟な発想が浮かぶ気がしていて、それを数日寝かせて、ギターに置き換えて翻訳してみる、というのは本作だけでなく、結構前から行っていますね。
Goblin:前回よりもよりメリハリが効いていますね。Nobuが作るリフ 曲もそうですけど、全体を通して押し引きがハッキリしていて。いつも凄いなと思っています(笑)。
Laven:Nobuのリフはいつも大好きです。彼はリフ・マシーンで、100%信頼しています。
●特に静の部分でのヴォーカル・パートの表現が素晴らしいですが、どのように感じていますか?
Nobu:静の表現は1stアルバムの頃からインストゥルメンタル・ナンバーやアコースティック・ギターの使用などを通して意識していたのですが、なかなかに技量や経験が追い付かない部分もあり……本作では改めて力を入れましたね。ヘヴィな部分も静の部分も、お互いを殺さずに良さを引き出せることを念頭にアレンジを進めましたので、そう言っていただけると嬉しいですね。もともとLed Zeppelinが大好きなのですが、彼らは史上最もダイナミクスを巧みに操るバンドとも認識していまして、そういうエッセンスに少しでも近づきたくて試行錯誤しました。曲でいうと「What Is and What Should Never Be」(『II』収録)や「The Rain Song」(『Houses of the Holy』収録)などからは大いに学ばせてもらいました。
Goblin:新たな一面が現れたなと。
Laven:このアルバムの長所は、これまでのアルバムにはなかったヴォーカルのハーモニーだと思います。私にとっては、HEBI KATANAのサウンドの大きな進化を象徴していますね。
●ベースとドラムのドライヴ感も心地良いです。どのようなことにポイントをおかれていまいしたか?
Laven:Goblinと私は、以前にも増してしっかりとしたグルーヴで固めることができました。ルーズでメランコリーなコーラスと対照的に、ドライヴ感のあるリズムを簡単に作ることができました。Goblinのセンスと、私のセンスが合わなければできなかったことですね。
Goblin:ありがとうございます。個人的にポイントはライヴ感、喜怒哀楽だと思います。リズムを敢えて無視したり、ジャンルに囚われずHEBI KATANAらしさを重視しながら、自分が持っている武器で叩きました。ベースはシンプルながらドライヴ感があるので、シンプルな所はシンプルに、ですね!レコーディングはクリック無しで、スネアは新しく手に入れたモノでやりました
Nobu:傍から見ていても、リズム隊の二人の結束は固くなったと思います! 様々な場面で二人でディスカッションもしていましたし、ステージで歌っているときは彼らの姿は見えないのですが、映像で見返すと二人がアイコンタクトを多用してたりとか(笑)。

●収録曲について教えてください。
- Bon Nou – 煩悩
アコースティックなイントロから疾走感のあるリフへの移行が見事なオープニング・チューンですね。
Nobu:実はこのイントロのクリーン・トーンでのフレーズは、アルバムの重要なテーマになっています。最後まで聴いていただけたら分かると思いますが、今回はそのようなアルバム単位でのつながりや、構成を特に意識しました。昨今ではサブスクリプションなど、曲単位で聴くスタイルも増えているとは思いますが、CDやレコード、カセットを買って聴いてくれるファンってやっぱりアルバムの流れとか……もっと言うとA面/B面の配置とか、「B1曲は勝負曲だ!」など楽しんでいると思うんです。少なくとも自分はそうですね(笑)。話を戻すと、曲もジャムの要素が強く、疾走パートもそうですが、後半のドゥーミーなパートもアイコンタクトしながらタイミングを合わせていきました。ちなみに本作でもクリックは一切使っていないです。ドラム録りの時は、実際にギターもベースも本テイクのつもりで弾いて、歌ってもいます。今までのHEBI KATANAにはないタイプの楽曲ですし、インパクトもあると思い、冒頭に収録しました。
Goblin:HEBI KATANA史上最も実験的かつ激しい曲。オープニングに相応しい曲ですね
ライヴで披露したいです。
Laven:ソフトなオープニングとアグレッシブなメイン・リフのコントラストが好きですね。
- Dead Horse Requiem – 走馬灯
本領発揮のドゥーミ―なリフが印象的なヘヴィ・ナンバーだと思います。
Laven:この曲はリフが素晴らしいですね。とてもヘヴィで、ファンに伝統的なドゥーミーなトラックを聴かせてくれます。
Goblin:これぞドゥーミーかなと。程良くダーク。後半の展開はなかなかスリリングですね。
Nobu:やはりこのような、うねるリフは不可欠ですし、プレイしていて単純に気持ちいですね。今回は後半にテンポ・チェンジをしたり、アルバムのコンセプトに合うように、ややメランコリックな要素も差し込みました。
- Praise the Shadows – 陰翳礼賛
全体的に愁いを帯びたサウンドとギターリフが秀逸なナンバーですね。
Laven:この曲は、NWOBHMを自分たち流にアレンジしたものです。クラシカルなリフ、クラシカルなスタイルを、HEBI KATANAのカラーで仕上げました。
Goblin:NWOBHMっぽいリフとヘヴィなビートながらも、サビがキャッチーなんです。個人的にはギター・ソロに注目してもらいたいですね。
Nobu:メンバーと話していたのは、「HEBI KATANA版NWOBHMのようにできたらよいよね!」ということです。オーソドックスなコード展開ですが、適度に歪ませて、サビは思い切ってキャッチーに展開してますね。ちなみに本作では、Lavenがほぼ全曲でハーモニーを入れています。たしか、2024年のイタリアでも演奏して、オーディエンスの反応を見ながら、ライヴで鍛え上げて完成に漕ぎつけました。
歌詞の面では、谷崎潤一郎の『陰翳礼賛』にインスパイアされました。今読んでも衝撃的な本ですし、本来は不完全で、見過ごされてしまうものの中に、風流や価値を見出していく考え方は、このアルバムのコンセプトの根幹だと思います。
- Doomed Echoes from Old Tree – 木霊
抒情的なナンバーで、特に中盤のエモーショナルな展開が良いですね。
Goblin:注目ポイントは歌のハーモニーですね。ほぼ全編コーラスが多用されていて このアルバムで1番ヘヴィなのかも。
Laven:このレコードのメインテーマを如実に表していますね。「侘び寂び」というテーマが透けて見えます。
Nobu:ほぼ全編ハーモニーが入っていますね。もともとThe Beatlesが大好きで、このように二つの声が混じって、一つの楽器のように響くスタイル(「Drive My Car」など)は、ずっとやりたかったので、今回形になって良かったです。最近のバンドだと、Uncle Acid and the Deadbeatsもハーモニーが俊逸ですよね。意外なところではBlink-182なんかも、二人の個性的なヴォーカルが交互に歌ったり、ハモったりして、ジャンルは全く違いますけれど、好きで聴いています。とにかくメロディーが良い楽曲は好きですね。自分の声とLavenの声が、いい意味で全然違うことも良かったです。得意とする音域が違うので(自分が割とロウ、彼はミッド~ハイが得意)、そのあたりもスイート・スポットを探りながら進めていきました。歌詞に関しては、とある神社と森林があるスポットをモチーフに書き進めていきましたね。「諸行無常」や「自分の存在とは何か」など、求道的なテーマを盛り込んでいます。
- Blood Spirit Rising – 諸行無常
力強いリフが牽引するキラー・チューンですね。リード・ヴォーカルをLavenさんが担当されているのは何か理由がありますか? 中盤のベース・ソロも印象的です。
Laven:このリフが私に語りかけてきて、すぐに歌うべきメロディーのいいアイデアが浮かびました。自分がこの曲を歌えたことに感謝しています。私にはメロディーに対するビジョンがあり、この曲でそのビジョンを披露することができました。改めてこの曲にフィーチャーされたことに感謝しています。私のベース・ヒーローはクリフ・バートンなので、自分のベース・ソロで長い曲を書けることは、大きな満足感を与えてくれます。以前よりも、難解なベース・パートで、私たちのサウンドが進化することを願っています。
Nobu:これはThe Lavenナンバーですね! メイン・ヴォーカルに、ベース・ソロと、彼の見せ場がたくさん盛り込まれています。今後のライヴでも重要な曲になっていくでしょう。一時期、Aメロ⇒Bメロ⇒サビというオーソドックスな曲展開だけでなく、Fメロくらいまで登場する楽曲を追っていたことがあります(笑) 。やはり70sにはそういうのが多いですよね。具体例を挙げるとBlack Sabbathの「A National Acrobat」(『Sabbath Bloody Sabbath』収録)とか。それをノートとペン片手にメモを取りながら、何度も聴いて、そこから新しいアイデアを得ようとしたり。この楽曲は前半は王道のシャッフル・リズムにヘヴィ・リフの曲ですが、後半に思い切った転調とリズム・チェンジを入れて、どうなるか試していきました。長めの楽曲ですが、各パートの流れを大切に、意味のあるものにできるように練っていきましたね。Lavenのヴォーカルに関しては、以前から歌ってほしかったですし、実際素晴らしい声を持っているのも分かっていて、さらに本人も歌いたいということでしたので、自然に決まりました。歌詞も彼が書き上げています。アルバム・コンセプトを見事に汲み取ってくれて、本作のハイライトとなる楽曲だと思います。あと聴きどころは、ベース・ソロはもちろん、短いながらも、しっかり主張するドラム・ソロですね。
Goblin:このアルバムのキラー・チューンです。Lavenが歌いたいと伝えてきて、キーもLavenに合わせて。後半のベース・ソロが哀愁溢れて、気付けばスリリングな展開になっていきました。また今迄に無いエンディングも新鮮だと思います。
- Yu gen – 幽玄
どこか牧歌的かつ雄大なイメージの楽曲で、HEBI KATANAの新境地的な楽曲だと思います。
Laven:この曲は本当に私に語りかけてきます。この曲が象徴するフォークのルーツ、そしてクラシック・ロックのルーツが大好きですね。Led Zeppelinのようなバンドにオマージュを捧げています。もちろん単になぞるだけではないですが。
Nobu:何度も言うようですが、今回はアルバム単位で一つのコンセプトを捉えていまして、人間に例えるなら、やはり気持ちのアップダウンがあるわけで。それを表現したかったです。ヘヴィなパートが動であるならば、もちろん静の部分もあるのが自然だろうなと。そういうコンセプト的な理由もありますが、単純にクリーン・トーンで楽曲をつくってみたいという気持ちもありました。この曲に関しては、ヘヴィになるところをより映えさせるために、静かなところはとことんメロウでソフトにしました。バンドにとっても新たな試みでした。歌詞的には、「リラックスするはずが、やはり旅を続けてしまう」松尾芭蕉の心情を、自分なりに想像して書き上げていきました。
Goblin:そうですね。今まで無いパターンの曲ですね。優しく歌うNobuのヴォーカルに、時にヘヴィなセッション。これぞメリハリ曲かなと。個人的には7曲目の「Yume wa Kareno – 夢は枯野」とセットで聴いて欲しい曲です
- Yume wa Kareno – 夢は枯野
本作のハイライトともいえる6分超えの大作で、構成も良く練られていると思います。
Goblin:この曲は3部構成になっていて、かつ長く感じないのが特徴かなと! 6曲目の「Yu gen – 幽玄」に通じる部分もあったり、昔のプログレッシヴ・ロック的要素もあったり。全体的に言えることなんですけど、ノスタルジックな気持ちになるかと思います。個人的にこの曲は大好きですね! 神社巡りをしながら聴くのをおすすめします!
Nobu:「Blood Spirit Rising – 諸行無常」と同時期、Fメロくらいまである楽曲を中心に聴いているときに、つかんだアイデアをもとに作っていきました。後半は、楽曲タイトルにもなっている芭蕉の辞世の句、「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」の、その駆け巡っているスピリットそのものというか、魂というかその心情をサウンドで表現しました。レコーディングでは一番苦労した曲かもしれません。アルバムの締めの曲ですし、エンディングにかけてのアレンジも結構苦心しましたね。なお、ギター・ソロに関しては稲荷さんや、齋藤さん(BxTxHx RECORDS)にもアドヴァイスをいただき、とても助けられました。
Laven:アルバムのラストを飾る曲で、力強いダイナミズムを持ち、このアルバムのテーマをリスナーに伝えることを目的としています。レコードのフィナーレとして、この曲はその目的を十分に果たし、コンセプトをうまくまとめていると思いますね。
●本作リリース直後には TOKYO DOOM FEST VOL.2 が控えていますね。今回のイベントの見どころを教えてください。
Laven:もちろん、Tokyo Samurai Doomというブランドを世界に示したいですが、でも一番は来てくれるみんなに素晴らしいショーを見せたいですね。
Nobu:今回は規模を大幅に拡大して、計4日間の開催です。出演バンド数も増えていますし、海外から出演するバンドもいます。観たことのあるバンドでも、この組み合わせ/ラインナップならではの、化学反応も絶対ありますし、楽しめる内容になるはずです! ぜひお越しください!
チケットと詳細のURLを貼っておきます。
https://hebikatana.wordpress.com/tokyo-doom-fest-vol-2/
Goblin:そうなんですよ。個人的には5/24(土)のFuzz Light Year、Demon and Eleven Children、Thunder Horseに注目です。5/25(日)はメタル色が強いのも面白いかなと。どれも凄いバンドばかり! 是非いらっしゃってください!
●イベント以降の予定はどうなっていますか?
Goblin:9/14(日)に小岩bushbashで自分の個人企画及びHEBI KATANAの新譜記念のレコ発をやります。是非!
Laven:アメリカ・テキサスのバンド、Thunder Horseと日本各地で短いツアーを行う予定です。来年は日本以外の国にも行きたいですね!
Nobu:TOKYO DOOM FEST VOL.2のあと、間を開けずに東名阪でのレコ発ツアーを行います。東京は東高円寺二万電圧で、TOKYO DOOM FEST VOL.2にも出演する海外勢を迎えてのライヴです。名古屋はお世話になっているGrind Freaks主催で、”Imaike Doom Feast”として海外勢、関東勢、名古屋勢が一堂に会する特濃イベントです。大阪はHEBI KATANAで初めて関西でライヴを行なった心斎橋・火影でのライヴです。個人的にはまた火影でライヴができて、とても嬉しいですね。 どの日程も、今から非常に楽しみにしています。もちろんツアーには新譜のCDも持っていきますので、会場でもゲットできます! アルバムを聴き込んでいただいてから参戦するも良し、ライヴかどんなものか、あえて予習なしで臨むのも、もちろん良しです!ぜひ、自由に楽しんでください!!
●リスナーへ向けて一言お願いします。
Laven:ファンの皆さんが私たちの音楽を聴いてくれることにとても感謝しています。心を込めて曲を作っているので、ファンから好意的な反応をもらえると、信じられないくらいうれしいですよ。これからもずっと応援してくれることを願っています!
Nobu:本作は楽曲はもちろん、歌詞の内容やコンセプトにもこだわりました。今までにないアイデアがたくさん詰まった4thアルバム、ぜひよろしくお願いいたします! またライヴ会場でお会いましょう!
Goblin:早くも4作目『Imperfection』が完成しました。ヴィンテージ感に侘びさびとヘヴィ・サウンドの融合。HEBI KATANAの新たな一面を体験して下さい。ライヴでお逢いしましょう!
Release Information

Imperfection
HEBI KATANA
UFBL14

■BIOGRAPHY
2020年 東京で結成。同年末に1stアルバム『HEBI KATANA』をリリース。王道のドゥーム/ストーナー・サウンドと暗黒かつメロウなヘヴィ・ハードロック・サウンドで、海外ウェブジンやレビューサイトなどマニアを中心に話題となり、”Tokyo Samurai Doom”として認知度を広げる。
2022年にはETERNAL ELYSIUM/STUDIO ZENの岡崎幸人氏をプロデュースに迎え、2ndアルバム『Impermanence – 無常』をリリース。イタリア盤もリリースされ、国内外で好評を博す。
2023年末には3rdアルバム『III』をリリース。日本のみならず、ドイツ、ポーランド、UKからのリリースも実現した。
また東名阪、岐阜、彦根、札幌、沖縄での公演も精力的に行い、Tokyo Doom Festへの出演、さらにはイタリア/フランス、南米チリでの海外公演も敢行し、世界規模での活動を展開。本作リリース後も、国内外での積極的なライブ展開を予定しており、今後のさらなる飛躍が期待される。
■DISCOGRAPHY
◆Album
2020 HEBI KATANA
2022 Impermanence – 無常
2023 III
2025 Imperfection
◆Singles & EP
2020 Directions for Human Hearts (Single:CD-R)
2021 Northern Lights High (Single:CD-R)
2021 Pain Should I Take (Single:Digital)
2022 Tokyo High Life Vol. 1 (EP:Digital)
2022 Live EP 2022 (EP:Digital)
2023 840 Jam (Single:Digital)
2023 Orange EP (EP:CD-R)
2023 Hallelujah Anyway (Single:Digital)
◆Live Albums
2022 Hokage Headache (Digital)
2023 Live Demo at Wildside (Digital)
2024 Live Bootleg (Digital)
2024 Doom N’ Bloom 2024 (Digital)
2024 Live at Tokyo Doom Fest Vol.1 (Digital)
2024 Live in Genova (Digital)
◆Other
2020 Directions for Human Heart (Demo:Digital)
2023 Early Demo Compilation 2020-2021 (Compilation:Digital)
2024 『III』 Naked (Demo/Compilation:Digital)
■SNS
Official website:https://HEBI KATANA.wordpress.com
X:https://twitter.com/HEBI KATANA
Instagram:https://www.instagram.com/HEBI KATANA/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCFmefE6QupT176yxLh2-m9w
Bandcamp:https://HEBI KATANA.bandcamp.com/
Facebook:https://www.facebook.com/HEBI KATANA
■LIVE INFORMATION
●2025/05/24(土) 両国SUNRIZE
Tokyo Doom Fest Vol,2 – day2
https://HEBI KATANA.wordpress.com/tokyo-doom-fest-vol-2/
●2025/05/30(金) 東高円寺二万電圧
https://den-atsu.com/
●2025/05/31(土) 今池HUCK FINN
GRIND FREAKS -imaike doom feast-
https://huckfinn.co.jp/
●2025/06/01(日) 心斎橋火影
Thunder Horse -Japan Tour 2025- Osaka
http://musicbarhokage.net/schedule6_2025.htm
●2025/7/5(土) 東京TBA
●2025/7/21(月・祝) 東京TBA
●2025/09/14(日) 小岩BUSH BASH
Farewall To The Heroes Vol.5
〜 HEBI KATANA 4th album ”Imperfection” Release & 35th Birthday Anniversary Party〜
●2025/10/18(土) 札幌TBA