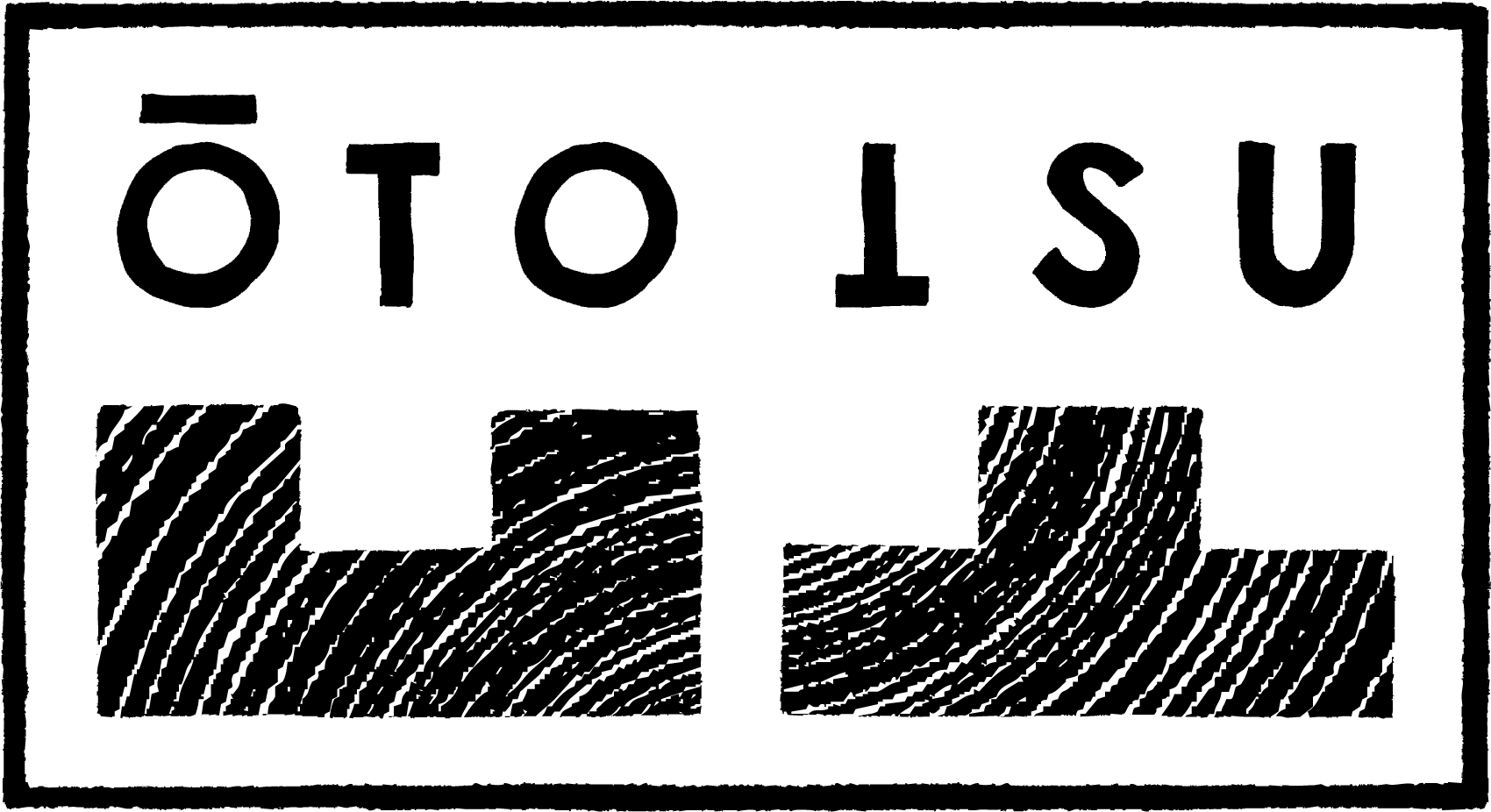今年(2023年)4月、林哲司がプロデュースを手掛けた「BRAND NEW MEMORY」で活動歴12年目にしてメジャーデビューを飾ったGOOD BYE APRIL。以来、非常に精力的かつ彼ららしい動きでファン層を拡大しているところだが、バンドのフロントマンである倉品翔のソロ活動もまた、今年に入って新たな段階に入った感がある。
倉品はもう何年も前からバンド活動と並行してソロ活動を行っており、地元の長野県を始め、各地で弾き語りのライブを長く続けてきた。そして初めてソロ曲を作品としてまとめたのが、2019年12月からライブ会場限定で販売していたCD『風の眼』(配信開始は2021年)だったわけだが、そこから段階を経て、彼自身のなかでもソロで表現したい音楽の世界観が徐々に明確化。miida(ミーダ。シンガー/ギタリスト、マスダミズキのソロプロジェクト)とコラボして今年8月にリリースされたシングル「ふたりは夏雲 feat.miida」は、切なくも夏の風情を感じさせる曲で、ラジオでも多数オンエアを獲得した。この曲を聴いて倉品翔というシンガー・ソングライターを認識した人、あるいはこの曲を好きになってGOOD BYE APRILを聴き始めたという人もいたくらいに、いい結果を残したのだ。
そして11月22日にはニューシングル「風はパーマネント」を配信リリース。これがまた素晴らしい楽曲で、ソロワークが完全に軌道に乗ったことを感じさせる。
バンドがアグレッシブな動きを見せるなか、倉品はどうして、どんな思いで、ソロ活動を行っているのか。「ふたりは夏雲 feat.miida」、そして新曲「風はパーマネント」にどんな思いを込めたのか。ソロ活動に焦点を絞って聞いたが、結果としてバンドに賭ける思いも伝わってくるインタビューとなった。
取材・文:内本順一 / 編集:伊藤晃代(OTOTSU 編集担当)
写真:瀬能啓太
― Hugh Keiceがリミックスした「missing summer」の韓国語ヴァージョン、林哲司さんのトリビュート盤『A Tribute of Hayashi Tetsuji –Saudade』に収録された「SUMMER SUSPICION」(杉山清貴&オメガトライブのカヴァー)、それにメジャー2ndシングル「サイレンスで踊りたい」とリリースが続いている上、2マンツアーがあったり、EPOさんとのコラボライブがあったりと、このところかなりアグレッシブな動きを見せているGOOD BYE APRILですが。
 倉品翔
倉品翔はい。頑張り時ですね(笑)
― ファンの層も広がったのでは?
 倉品翔
倉品翔そうですね。「林さんの楽曲のファンだったので聴いてみたら好きになりました」という人がかなり多かったですし、EPOさんのファンの人もそう。林さんやEPOさんの曲を好きで聴いてこられた僕らより上の世代の人たちから、とてもいい反応をいただけている。音楽的な親和性があるからこそなんでしょうけど。
― 林さんにしてもEPOさんにしても、1回限りのコラボで終わらず、これからもAPRILとの関係が続いていきそうな予感がする。まさしくそれは音楽的な親和性があるからで。
 倉品翔
倉品翔そうなんですよ。自分たちの好きな人とばっか繋がれているのが大きくて。メジャーデビューの年だからということでの作戦としてではなく、音楽性あっての濃い繋がりができていることがすごく嬉しいんです。
― そんなふうに非常に充実したバンド活動が進むなか、倉品くんはソロ活動も並行してやっている。バンドが行き詰まったときにソロで動いて空気を循環させるというアーティストは少なくないけど、倉品くんは、バンドはバンド、ソロはソロという感じで、これまでも両方走らせてきたわけで。
 倉品翔
倉品翔バンドに何かあるからソロをやっているんじゃないか、っていうふうに見られたくないんですよ。
― ソロではソロで表現したい楽曲を制作して、フットワーク軽くあちこちで弾き語りライブをやっている。それは決してバンド活動の片手間なんかじゃないってことを、ちゃんと伝えておきたいよね。
 倉品翔
倉品翔ほんと、そうなんです。
― あっちは仕事でこっちは遊びみたいなことではないでしょ?
 倉品翔
倉品翔そういう意識はないですね。ただ、バンドに対してはやっぱり責任感が強くあって。それはずっとそうなんです。自分が(バンド結成の)言い出しっぺである以上、バンドとしてちゃんと結果を出さなきゃいけないし、それを自分の人生の大命題として20代の頃から生きてきたところがあって。
― 結成当初からそういう意識を持っていたの?
 倉品翔
倉品翔始めたての頃は、もう一回バンドをやれて嬉しいっていう純粋な喜びだけでしたけど、やっていくうちにバンドというものが自分には向いてないんじゃないかと悩みだして、やめちゃったほうがいいんじゃないかって考える時期もあったんです。長い間、その葛藤が続いていましたね。でも自分が言い出しっぺだし、みんなの人生を預かって……預かってじゃないな、引きずりこんじゃったから、結果が出るまで責任を持って踏ん張らなきゃなと。その感覚は今も抜けてないです。
― でも責任感だけでは、インディーで12年間も続けられないわけで。
 倉品翔
倉品翔可能性が途切れなかったんですよ。もしかすると諦めポイントもあったのかもしれないけど、やっぱりみんながそれぞれちょっとずつ成長しあえる関係性だったから。まだ全然伸びしろがあるじゃん、こんなこともやれるようになったじゃん、っていうことの繰り返しで、それがどんどん大きくなって今に至っている感じなので。
― 「もうここまでだな」と思う瞬間がなかった。
 倉品翔
倉品翔なかったんです。それは幸せなことだったと、今になって思いますけど。
― バンドをそういう思いで続けてきて、じゃあどうしてソロもやっているんですかって思う人もいるかもしれないけど、そう訊かれたら?
 倉品翔
倉品翔もともとソロは趣味から始まっているんですよ。僕は家で曲を作っている時間が大好きで。ひとりで打ち込みとかをしているのが楽しくて、その延長線上でソロをやっている。というのと、3~4年前からシティポップだったり80’sだったりとバンドでやりたい方向性が明確になるに連れて、自分がほかに昔から好きで聴いてきた音楽……例えばサイモン&ガーファンクルのようなフォーキーなものだったりをバンドでやる感じではなくなっていったというのもあって。当面こういう曲はバンドでやらないだろうな、だったら自分で趣味的にやればいいじゃん、っていうところで始めたのがソロなんです。
― バンドの音楽の方向性が明確になったことにより、ソロではこういうことをやりたいという気持ちも同時に強くなっていった。
 倉品翔
倉品翔そうです。別ベクトルのやりたいことがそれぞれにある。でも例えば20年後とかにそれが混ざっちゃってもいいと思っているんですよ。歳をとったら、今ソロでやっているようなことをバンドでやれるようになるかもしれないし。今は明確に自分のなかで分かれているから、両軸でやれるなっていう。どっちも楽しくやれる。そういう健全なマインドです。
― APRILは柔軟性の高いバンドだけど、それ以上にソロだとフットワーク軽くやりたいことがなんでもできるってところもあるのでは?
 倉品翔
倉品翔気楽さはありますね。バンドにおいての曲作りは、衣装を着る感じというか、ちょっと余所行きの服を着て出かけるようなマインドで、もちろんそれはそれですごく楽しいんですけど。ソロはそういうんじゃなくて、部屋着のまんまをポロッと見せられる場所としてある。もともとひとりでいるのが好きなんですけど、そういう自分をそのまま見せられる気楽さというか。
― 両方あるからいい。
 倉品翔
倉品翔うん。でも、どっちかが欠けたら困るというよりは、どっちも楽しいからやっているって感覚ですね。
― こんなことはありえないけど、もしも今誰かにバンド活動の場を取り上げられたら……。
 倉品翔
倉品翔あ、それは困る。バンドは志半ばですからねえ。自分には向いてないんじゃないかと思っていた時期もあったけど、今はもう生涯バンドとしてやりたいというところまで来ているから。一生やりたいバンドになれたので。
― ソロのほうは?
 倉品翔
倉品翔ソロ活動ができなくなったら心の健康が保てない、とはまったく思わないです。単純にやりたいことがもういっこあったからやっているって感じなので。
― 曲作りに関しては、「さあバンドの曲を作るぞ」「ソロの曲を作るぞ」というふうに別の意識で書くものなの? それとも、特にそういう意識を持つことなく、曲ができてからこれはバンド、これはソロというふうに振り分けるの?
 倉品翔
倉品翔両方ありますね。ただバンドの曲は、“こういうシチュエーションで流れたらいいなぁ”といったイメージありきで作ることが最近多くなりました。それとあと、チームの総意として“次はこういうことをやったらいいんじゃないか”“こういう曲をリリースするのがいいんじゃないか”というのを持って、それに沿うように作ることも増えた。純粋に自分が今やりたいことの比重とチームとしてのそれとの割合が、以前とは変わってきていますね。ソロの場合はそういうことを何も考えず、自分の心のなかのちょっとした衝動を曲にしている。ポロッと出てきたものが曲になるということが多いです。
― バンドでやるつもりで作ったけど、しっくりこなくてソロでやることにしたという曲もあったりする?
 倉品翔
倉品翔あります。バンドでやりたいと思って持っていった曲が、ほかの3人はそんなにピンときていなくて、だったら自分が趣味全開でやったほうが面白くなるなと思ってそうした曲もあるし。
― 具体的に言うと?
 倉品翔
倉品翔『satellite flying alone』に入れた「River」がそうですね。あの曲はバンドのデモに紛れ込ませていたんですけど、あまりにもピアノ弾き語りの作りだったからか、これをバンドでやるというイメージがみんなのなかに湧かなかったみたいで。
― 前にも言ったけど、「River」は僕の一推し曲で。個人的には倉品翔ワークのなかでもベスト3に入るであろう大名曲であると信じて疑わないんだけど。
 倉品翔
倉品翔言ってましたよね。嬉しかったです。僕も『satellite flying alone』のなかで、できたときに一番手応えがあったのが「River」なんですよ。これはとんでもない曲ができてしまったと自分では思ったんですけどね。
― いや、本当に素晴らしい曲なので、これは長く歌い続けてほしい。
 倉品翔
倉品翔そうですね。自分が歳を重ねたら重ねた分だけよさが出る曲だと思うので。
― いい曲ではあるけど、現在のバンドのモードではなかったということだね。
 倉品翔
倉品翔そう。そのときそのときでバンドはバンドのモード、4人の旬のモードというのが不思議とあるんですよ。昔からそうなんですけど、示し合わせたわけでもないのに“これを今やるべきだ“という考えが一致する。それがまた半年経つとガラッと変わったりもするのも面白いところで。
― バンドで出す曲はなるべく大衆性を持たせようといった意識はあったりする?
 倉品翔
倉品翔ソロではポピュラリティーみたいなことを意識していないんですけど、バンドはとりわけメジャーデビュー以降、もう一度そこを見つめ直しているフェーズだったりしますね。『swing in the dark』を作っていたときはそういうことではなくて、バンドでそのときやりたかった面白いことを片っ端からやったアルバムだったんですけど、今年、林さんと「BRAND NEW MEMORY」を作ってデビュー曲として出してからは、もっと多くの人たちに届けるんだというところを今一度軸にもってきている。それが今年のバンドのモードだった気がします。
― それをやることが楽しいんだよね。
 倉品翔
倉品翔楽しいし、やりがいがありますね。でもそれは『swing in the dark』でのトライがあったからこそだと思っているんです。その一歩先に、今年の僕たちの曲があったというか。自分たちの考える普遍的なメロディと、今のアレンジ力をガッチャンコしたら、バンドはもっと先に進めるという確信があるから、ワクワクしながらそれをやっているところなんです。
― そうしたバンドの曲に対して、ソロ曲においての傾向を言葉にすることはできますか?
 倉品翔
倉品翔ひとつはフォーキーってことですね。もうひとつは孤独感。あるいは心の脆弱性みたいなもの。そのへんがキーワードかなと。
― パーソナルってことだよね。誰かになって歌うのではなく、自分自身の心の動きだったり揺れだったりを歌うという。
 倉品翔
倉品翔そうです。ソロをやる意義というのはそれしかないとも言えますね。気飾ることはバンドで十分やれる。ソロではさっきも言ったように普段着の自分を見せる。“部屋にひとりでいるときの僕はこれです”“昔から僕はこういう人間なんです”みたいな感じです。
― しかも心象風景を表現するにあたって、必ずしも歌詞は必要じゃなかったりもする。つまりインストゥルメンタルの曲もあって、そのあたりが自由なのもソロ表現ならではで。
 倉品翔
倉品翔そうですね。形式に捉われない。サウンドにしても、バンドだと当然バンドサウンドになるわけですけど、ソロだったらトラックメイカーの人とコラボするとかってこともやりやすいし。形式における自由度の高さは、やっぱりソロのほうがある気がします。バンドはというと、『swing in the dark』は打ち込みの曲も結構あったんですけど、今年になって肉体感をすごく大事にするようになっていて。4人のグルーヴを今は前面に出していきたいので、トラックっぽい曲ができたら、それはソロでやる感じですね。
― 肉体感。それは今年のライブを観ていて、すごく伝わってきた。
 倉品翔
倉品翔今年はそういうプレイヤビリティを作品にもしっかり投影できているという実感が、メンバーみんなにあると思います。

― では、ここからこれまでのソロ作品を振り返って聞いていきたいんだけど、ディスコグラフィ的には7曲入りのミニアルバム『風の眼』が最初だったよね。配信開始は2021年だけど、ライブ会場ではもっと前にCDで販売されていた(2019年12月に販売開始)。音楽性としてはそれこそフォーキーで、70年代のニューミュージック的でもあって、当時とても新鮮に感じたのを覚えている。インストゥルメンタルの曲も入っていたし。
 倉品翔
倉品翔最近聴き返していて、財津(和夫)さんのソロみたいな感じもあるなって思いました。
― 「rush」というピアノ弾き語り曲がまさにそんな感じだったよね。
 倉品翔
倉品翔ですね。
― それから2022年に何曲かシングルで配信したあと、今年2月に配信リリースしたのが5曲入りEP『satellite flying alone』(これも会場限定でCDを先行発売)で。『風の眼』同様、これも制作の全工程をひとりでやった作品だったけど、サウンドは少し変化していた。
 倉品翔
倉品翔『風の眼』は、ちょっとしたオリジナルアニメーションをバンドで作ったときの挿入音楽として録音したインストとか、そのときそのとき単発で作っていた曲を寄せ集めたものだったんですよ。それはまあ、ひとりで作ったから小ぢんまりしたものだったんですけど、結果的に統一感はあったんです。そうやって統一感が出ることがわかったから、今度はより孤独感みたいなところにフォーカスして、寄せ集めじゃなく作ってみようと。それが『satellite flying alone』で、そのとっかかりとなったのが「astronaut」という曲だったんです。
― あの曲も素晴らしい。「River」もだけど、あの曲もかなり手応えがあったのでは?
 倉品翔
倉品翔何がきっかけでできたかは覚えてないんですけど、確かポロッとでてきて、デモの時点でもう完成形に近いものだったんです。ものすごく孤独感が出ている静かな曲。月面を歩いているときの足音をイメージして打ち込みをしたり、風の音をシンセで録ったりしたのがうまくいって、確かに手応えがありました。
― 「benjamin」はフォーキーで、それこそサイモン&ガーファンクルっぽさのあるいい曲だった。あれもバンドでは考えられない曲だよね。ソロでこそ、っていう。
 倉品翔
倉品翔そうですね。個人的にああいう曲も大好きなんですよ。
― そんなEP『satellite flying alone』ができたことで、ソロワークに自信と弾みがついたというところもあったのでは?
 倉品翔
倉品翔ひとつ明確な型が見えたという意味での手応えは確かにありました。でも逆に言うと、当時やりたかったソロの形はこれで一通りやれたなっていう感じもあったんです。自分のなかではね。だけど今年に入って、ソロはソロで一緒にやっていきたいと言ってくださる人が増えたんですよ。特に出版のある方と別の会社のある方がすごく評価してくださっていて。バンドとしてのよさもあるけど、ソロでしか出せないよさもあるから、本格的にやればいいじゃないかと言っていただいた。で、自分としてもバンドと両軸でどっちも楽しくやれそうだから、“やります!”と。
― 趣味的に始めたことだけど、趣味以上のものにしていこうという意識が芽生えた。
 倉品翔
倉品翔うーん。曲を作る上での意識はそこまで変わったわけではないんです。だけど、そういう声をいただかなかったら、次のソロを出すのはもっとゆっくりだったと思う。趣味のペースでのんびりやっていたと思うけど、でもソロはソロで年間計画も立ててちゃんと動かしていこうという意識には僕もなりましたね。
― “ソロアーティスト・倉品翔”の確立を自分のなかで意識した。
 倉品翔
倉品翔今年になるまでは、そう思ったことがなかったんですけどね。あくまでもバンドのなかのひとりで、ソロもたまにやっていますという程度の意識だったけど、確かにそこは変わったと思います。
― 曲で言うと、「ふたりは夏雲 feat.miida」からってことだよね。
 倉品翔
倉品翔そうです。あの曲は、実はバンド用のデモの1曲として作ったんですよ。バンドでゲストヴォーカルを迎えた曲を出すのはどうかという話が出て、そのイメージのもとに作っていたんです。でも林さんとのデビュー曲(「BRAND NEW MEMORY」)の次に出す感じではないよねってなったときに、だったらソロの曲としてしっかり作りこもうってなって、作り上げる過程でミズキちゃんの声が絶対合うなと思ったのですぐに相談した。そこから1ヵ月くらいで完成させました。
―この曲にミズキちゃんのヴォーカルが最高にマッチしている。倉品くんのヴォーカルとの相性もバッチリだし。
 倉品翔
倉品翔もともとmiidaの音楽が好きだったし、miidaの音楽にも無機質な寂しさみたいな感じがあるじゃないですか。風も感じるし。だから音楽的に親和性を感じていたんです。そういう楽曲が映える声だなと思っていたので、すごくイメージが湧いて、一緒に歌ったらいいだろうなと。
― 歌詞はその前から書いてあったの?
 倉品翔
倉品翔1コーラスはなんとなく先にできていたんですが、ミズキちゃんの声質ありきで、ちょっと切ないストーリーがいいなと思って。男女の離別がテーマなんですけど、そこにフォーカスして書き上げていきました。
― “無機質な寂しさ”と言ったけど、確かにふたりの声には共通するトーンがある。いかにも熱のある声ではないけど、だからといって冷たいわけではなくて。
 倉品翔
倉品翔色で言うなら、青っぽいというか。暖色ではない気がしますね。
― 歌詞もパキっと明快な感情ではなく、まだ愛もあって未練もあるけどこのままではいられないという気持ちをふたりが通じ合わせている。それだけに切なさが滲むという。
 倉品翔
倉品翔ミズキちゃんが言っていたんですけど、たまに誰かの曲にフィーチャリング・ヴォーカルで入るときも、自分がどう歌ったら曲の世界に入り込めるかをすごく考えて取り組むらしくて。この曲も最初にテストでワンコーラス歌ってもらったんですけど、その時点でもう僕の思い描いたイメージ通りだったので、何も言うことがなかったです。まず自分の歌を家で録って、それをミズキちゃんにデータで送って自由に歌ってもらうというリモートのやり取りだったんですけど、本当にこの曲の世界に入り込んで歌ってくれたんだなぁと思いました。
― 歌詞は“ふたり”を“夏雲”に例えたところが秀逸だし、そこに倉品くんらしさも出ている。
 倉品翔
倉品翔なんかこう、海辺の町の空が景色として浮かんでいたんですよ。で、“ふたりは~、夏雲~”ってメロディに乗っかって言葉が出てきて、そっか、ふたりは夏雲か、夏雲みたいにはぐれちゃう恋人の歌なんだなってメロディに教えられて、そこからストーリーを書きました。
― 夏雲を浮かべるのが倉品くんらしい。日々都会の夜に紛れて生きている人だったら、その発想は出て来ないわけで。
 倉品翔
倉品翔そうですね(笑)。 自分のいるべき場所は時間の流れがゆったりしたところという思いが未だにあるので。ソロで曲を作ろうと思うと、自然とそういう景色が浮かんでくる。それは未だに都会を自分の居場所だと思えていないってことの裏返しなのかもしれないです。
― この曲も新曲の「風はパーマネント」も、ジャケットの写真は自然のスナップだし。
 倉品翔
倉品翔どっちも自分で撮った写真を使っているんですけど、「ふたりは夏雲」は波打ち際の写真を90度回転させたら真ん中で砂浜と水辺にぱっくり分かれた世界が見えて、これは離別を表現できるなと。
― なるほど。そしてニューシングルの「風はパーマネント」。これもまたソロ曲らしいゆったりしたテンポ感で、季節的にもしっくりくる。これはどんなふうに生まれたの?
 倉品翔
倉品翔僕の携帯に「“風はパーマネント”って言いたい」というボイスメモが3つか4つ残っていたんですよ(笑)。その言葉にメロディもなんとなく付けていたんですけど、その度に変わっていて、そのまま寝かせてあったんです。で、それをちょっとずつビルドアップしていって、これならいけるかもっていう感じになったときにちょうど次のシングルの打ち合わせがあったから、聴いてもらったら“いいじゃん!”ってなったという。そこから構成を決めて歌詞を書いてアレンジを詰めてっていう作業をしました。
― 「何も 何も変わらないで 続いてほしいと願う日に限って いつも不意に終わりが来て~」という出だしからよくて。この感じ、すごくよくわかる。実感から書いたの?
 倉品翔
倉品翔ずっと思っていることなんですよね。だからこの出だしはすんなり書けた。で、「風はパーマネント」というキーワードは先にあったんですよ。そもそもパーマネントというワードが好きで。パーマネント=半永久。風ってそういうものだなというところで自分のなかではしっくりきていたんですけど、ただそれを歌詞にしてうまく説明するのが難しかった。
― どんなときにも風は吹いている、っていうことかな。
 倉品翔
倉品翔はい。自分が落ち込んでいたりするときに窓を開けると、いつもと変わらない風が吹いていて、それが救いになるみたいなことってあるじゃないですか。そういうふうに感じる瞬間が、これまで生きてきたなかでけっこうあったなと思ったんです。たぶん死ぬまでこういう感じなんだろうなと思って、それをなんとか言語化したいと思って書きました。
― 好きな人と別れたり、誰かが遠くへ行ってしまったりして、昨日とは違うはずなのに、外には今日も同じ風が吹いている、みたいなことだよね。
 倉品翔
倉品翔そう。淡々と続いていくじゃないですか、日常って。それって残酷でもあるけど、それが救いになることも確かにあって。でもそういうところに視点が行くときって、大抵自分が落ち込んでいるときなんですよね。嬉しいときや楽しいときには、別に吹いている風のことなんて気にならない。だからこう、落ち込み気味のときに吹いている風を感じて、また日常に戻れるはずだと救われた気分になったりするっていう。これまでのそういう実感を曲にしたって感じです。
― 「開いて、閉じてまた開いて 優しかった言葉 たまに見返している」と歌っているでしょ。これは好きだった人からもらったメールを、携帯なりPCなりを開いて読み返しているという描写なのか、それとも手紙を開いて読み返しているのか。あるいは過去に繋がる時間の扉を開いたり閉じたりしているということなのかと、いろいろ考えたんだけど。
 倉品翔
倉品翔そこは聴く人それぞれの捉え方でいいと思って、あえてちょっと抽象的にしています。自分はiPhoneなのでその画面を開いて消してっていうことなんですけど、ノートなり手紙なりを想像してもらってもいいし、それこそ時間という概念でも捉えられる。あ、でも、「だから今日は思い立って 手紙を出そうか」って書いているから、僕も手紙を想像しながら書いていたんでしょうね。メールが似合う曲ではないし(笑)
― そう。この曲の主人公は、初めは「夢みたいに消えてなくなるんだ」ってことに寂しさを感じているけど、進んでいくうちに「今日は思い立って 手紙を出そうか」って気持ちになるんだよね。「出そう」ではなく「出そうか」だからまだ完全に決意しているわけではないけど、少なくとも初めの気持ちよりも前向きになっている。そうやって、少し意志を持つようになるところがいい。
 倉品翔
倉品翔なんか、このくらいの年齢になると、曖昧な気持ちをそのまま言葉にしたいっていうのがどんどん強くなっていて。昔好きだった人への気持ちも、少しずつ自分のなかで変化する。でもその人を思う気持ちは残り続けている。だから、出そうとしている手紙にも「好きでした」とかそんなことを書くんじゃなくて、たぶんとりとめもないことを書くんでしょうけど、でもそこには特別だと思っていた気持ちがうっすら乗ってくる。そういう手紙をイメージしていました。
― ああ、なるほど。
 倉品翔
倉品翔だから最後の「I Love You」という言葉も、好きだー!っていうことではなくて。愛というものの概念が年々自分のなかで大きくなっていて、例えばそれは恋愛だけじゃなくて、慈しむ気持ちも「I Love You」だったりするし。
― 思う気持ち、ってことだよね。「元気かな」というのも「I Love You」に含まれる気持ちのひとつだし。
 倉品翔
倉品翔そうですそうです。変わりゆく日々であっても、変わらずに残る思い。それを書けたらいいなと思って。
― 楽器は今回も全部自分でやっているんだよね。サウンド面で意識したことは?
 倉品翔
倉品翔アコーステイックギター弾いて、ベースも弾いて、鍵盤も自分で弾きました。自分的に一番面白かったのは、普段あんまり使わないようなエレキギターの音を使っているところで。スライドギターとアルペジオ、両方入っているんだけど、どっちもエフェクティブ。知り合いから借りっぱなしのダンエレクトロが家にあって、そのちょっとペラいんだけどいい音っていう質感がこの曲に合ったんです。
― 基本的にソロの曲は音がシンプルに聴こえる。この曲も楽器の使い方に凝ってはいても、それが主張して前に出たりはしないという。
 倉品翔
倉品翔そうですね。音数が多い印象を与えたくなかったので。隙間があったほうがいいなと思って、そういうサウンドメイクを意識しました。
― 作者としてはこの曲がどういうふうに聴かれたら嬉しい?
 倉品翔
倉品翔ソロで作るのは基本的に寂しさのある曲たちなので、聴く人の孤独感とかちょっとした心のくぼみにスッと入っていく曲であったらいいなと思います。あと、パーマネントって言葉を使っているように、自分が歳を取ったときにもこの曲はそこにあるというイメージが、曲を作っているときからあったんですよ。だから聴く人が人生を重ねたとき、この曲がどう聴こえるんだろうって想像したりもするし。
― 今何度か聴いたらどっかに追いやるんじゃなくて、年齢を重ねるなかで時々聴き返したくなる曲だと思えるし、それが楽しみだよね。自分と共に育っていく曲という感じがする。
 倉品翔
倉品翔そうあってほしいですね。この前、EPOさんともお話したんですけど、自分が歳をとってからも聴きたい音楽っていうのがあって。EPOさんの音楽がまさにそういうものなんですよ。例えば「音楽のような風」とかが僕にとってのそういう曲で。自分のソロも、そういうものでありたいと思う。おじいさんになって静かな暮らしをしているなかで流れたらいいなっていう、そういうイメージで作っているところがありますね。だから、長く聴いてもらえたら嬉しいです。
― ゆっくりでもいいから、落ち着いた暮らしを好む人たちに広く届いてほしいね。じわじわっと。
 倉品翔
倉品翔そうですね。バンドはアグレッシブに。ソロはじわーっと。伝わる人に伝わってほしいです。

GOOD BYE APRIL
“What a Harmony EXTRA FINAL”
2024年1月8日(月・祝)
東京・新宿LOFT
開場17:30 / 開演18:00
自由席 5,500円 / 後方立見 4,500円(+1Drink)
▼ チケット発売中
イープラス:https://eplus.jp/goodbyeapril/
ローソンチケット:https://l-tike.com/goodbyeapril/
チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/goodbyeapril/

風はパーマネント
倉品翔
2023.11.22 RELEASE
DOBEATU
日本情緒を感じるオーセンティックなメロディを心地良いビートとスモーキーなトラックで包み込み、日々の暮らしに寄り添う普遍的な郷愁音楽を届ける長野県出身のシンガーソングライター<倉品翔>日常に潜む哀しみ、儚くて愛おしいものを大切に撫でるように紡がれた楽曲「風はパーマネント」。70~80年代の古き良きポップミュージックを血肉にした、唯一無二のメロディメイカーであり、その創作を奥行き深く表現するヴォーカル・パフォーマンス能力の高さは「ネオ・ニューミュージック」の枠に収まらない魅力を発揮し、今年メジャーデビューした所属バンド<GOOD BYE APRIL>の他にも様々なアーティストへの詞曲/編曲/歌唱提供を行っている。