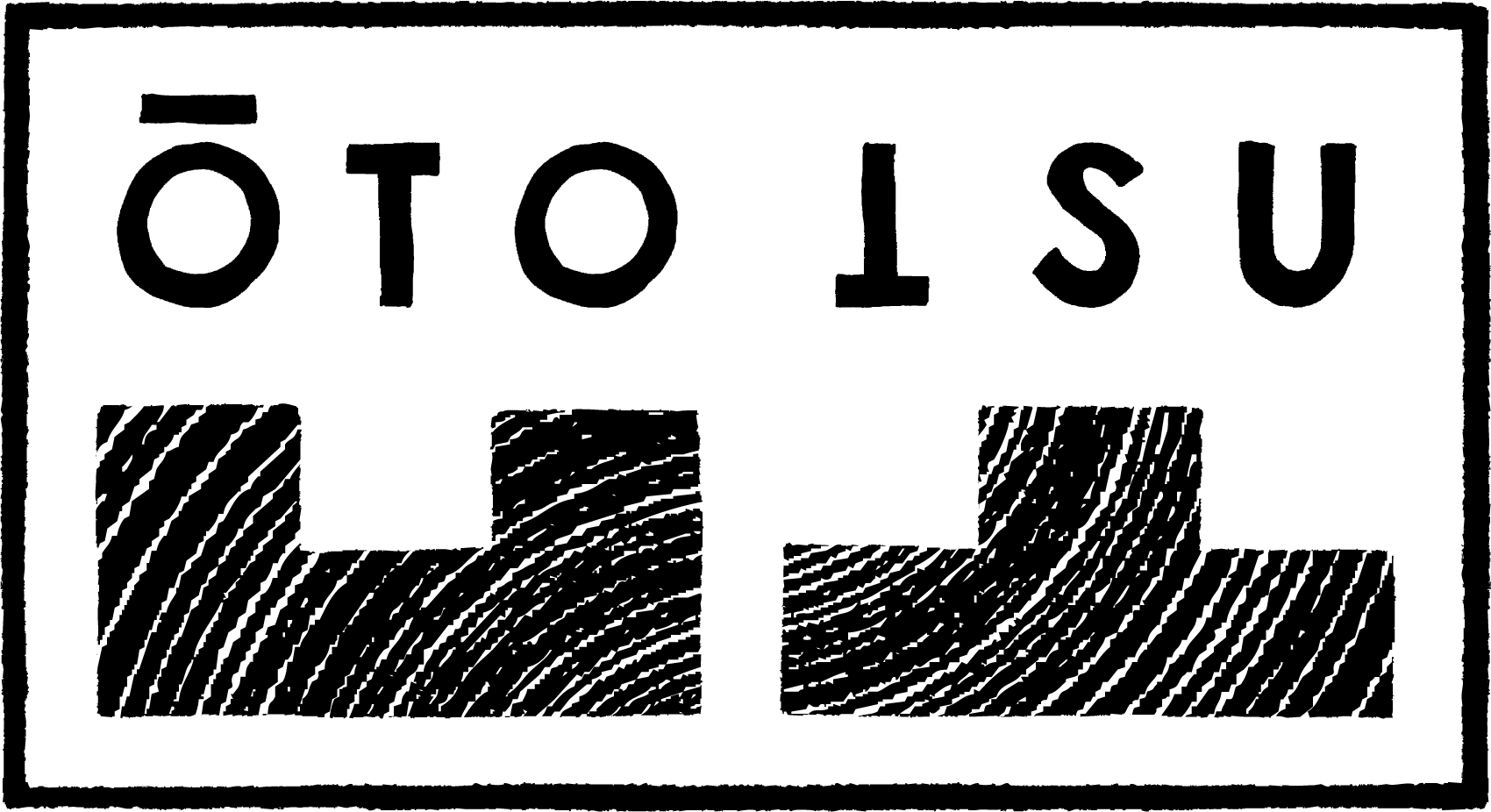2010年代のアルゼンチン発のモダン・フォルクローレの新たな発信地=ラ・プラタを代表する次世代グループとして高い評価を集めたナディス(Nadis)の中心人物であり、マルチ奏者/プロデュ―サーとしても豊かな才を発揮してきたフアン・イグナシオ・スエイロ。ミナスのハファエル・マルチニやマリア・シュナイダーからの影響も高度に消化した器楽アンサンブルで新世代の台頭を印象付けたデビュー作『Alquimia Planetaria』(16年)、より歌の比重を増した『トランスムータ』(18年)というナディスでの2作を経て、初のソロ名義で届けられたアルバム『オラクロ』は、より肩の力の抜けたメロディアスかつシンガーソングライター色の強い作風で新境地を示した会心作となっている。
これまでにモノ・フォンタナ、ギジェルモ・クレイン、アカ・セカ・トリオのドラマーのマリアノ〝ティキ〟カンテーロ、メリーナ・モギレフスキーといった現代アルゼンチンを代表する音楽家たちに師事して多くを学び、教育者としても優れた鍵盤奏者のフェデリコ・アレセイゴルの助手としてラ・プラタの大学で働きながら音楽家として活動してきた彼の本領が新たな形で発揮されたソロ作が完成するまでの過程、多彩なゲスト陣、ジョニ・ミッチェルやチャーリー・ガルシア、武満徹の名前まで飛び交う幅広い影響源や音楽観について、本人にたっぷり語ってもらった。
インタビュー・構成:吉本秀純
通訳:宇戸裕紀
●
――本人名義での初アルバム『オラクロ』は、あなたが率いてきたナディスと比べると、かなりシンガーソングライター色を強めた作品となっています。ナディスも2作目の『トランスムータ』は歌の比重が増していましたが、やはりどこか器楽的かつバンド的な音だったのでかなり変わったと思うんですが、これまでの活動を経て『オラクロ』に至った経緯を聞かせてください。
「このアルバムはパンデミックの子供というか、パンデミックの影響がとても強い作品です。というのも、2019年の終わりに(勤めている)大学からウシュアイアに異動しないかという申し出があったので、それまで長く住んでいたラ・プラタからウシュアイアに移り住んだんですよ。それが、今までやってきたベース、ドラム、ピアノの演奏スキルを磨く良い契機になったので、さらに深めていって、 ウシュアイアに滞在しながらこの作品が完成していきました。音色などを深めていって、ナディスをさらに進化させたような印象です。器楽的な部分と歌の関係については、自分の中ではそこまで変わってはいなくて、今までと同じように歌と器楽的な要素が合わさったものを作ってるつもりですけど、そういう印象を持たれたのなら嬉しいことです」
――ご自身で書かれた『オラクロ』の解説を読むと、20年6月くらいからアルゼンチン南端のウシュアイア(注:ブエノスアイレスから3,000キロ南に位置する)で録音を始めたと書いてあったので、わざわざ行ったのかなと思っていたんですが。そうではなくて、ちょうどパンデミックが始まる直前に移り住んでいたんですね。
「今はもうブエノスアイレスに戻っていますけどね。ちょうどパンデミックの頃には(ウシュアイアで)ホテルでピアニストとして働かないか?というオファーもありました。そこにはスタンウェイのピアノが置いてあって、オーナーさんが、オペラなども好きなすごく音楽好きな方でした。今作に参加している歌手のルシア・ボッフォはウシュアイア出身で、(フアンがプロデュ―スを務めた)彼女のソロ作もそこで録音することができたし、コロナ禍にありながら音楽に浸ることができたのは素晴らしい経験でした。他にも多くのウシュアイアの音楽家たちと共演できたし、ナディスの2作目に参加していた歌手のフアナ・サリエスとも一緒にやりましたよ」
NOMADE | Lucia Boffo (bandcamp.com)
――じゃあ、移住したっていうのが、まず大きかったんですね。
「はい。最初は自分1人で始めてたんですけど、進めていくうちにだんだんコラボが増えていって、クレジットを見てもわかるように、最終的にはたくさんの人が参加してくれて。それが自分の好きなスタイルなので、たくさんの人に参加してもらっていい作品になってると思います」
――『オラクロ』の制作はどんな感じで進んでいったんですか?
「最初は、3曲だけ録音する予定でした。6曲目の「Impresión increíble」、7曲目の「Zamba Amanecida」と12曲目の「En el fin, espero」ですね、それだけを録音する予定だったんですけど、 長く続くロックダウンですごく時間があって、 しかもウシュアイアという街はすごく南極に近い場所で、夏とかはずっと日が落ちない場所なんですね。逆に冬はずっと暗かったりして、家に閉じこもるしかなかったので、時間があった中で他の曲もできていった感じです」
――結果としていろんなゲスト歌手やプレイヤーが参加してますが、ベーシックの部分ではほとんどの楽器をご自身で演奏してるのが、今までとはかなり違うと思います。そういうスタイルを取った理由は?
「ウシュアイアでは、引っ越したばかりであんまり人も知らなかったし、ロックダウン中には新しい人を知ることもできなかったので、自分でやるしかなかったというのが一番大きいですね。実はナディスの時にもピアノだけを演奏していたわけではなくて、作曲する時にベースやドラムを自分で演奏しながら、どんな感じにしようかなという作り方をしていました。なので、その時の経験は、今回のアルバムにすごく役に立っています。
また、自分の中で一番のリファレンスというか、参考になったのがモノ・フォンタナが今までやってきたことでした。もちろん自分にとって雲の上の存在のような人ですが、彼もピアニストであるだけではなく、ドラムやビブラフォン、ギターも自分で弾くことがあったし、頭全体が音楽で出来ているような人なので。彼が残してきた足跡をすごく参考にしたところもあります」
――なるほど。モノ・フォンタナもソロ作では多くの楽器を自身で演奏していますね。
「私は2年間、彼に師事しました。今はビジャ・デボートというとても近所に住んでいます」
――制作プロセスにはモノ・フォンタナの影響を感じますが、音楽的には冒頭でも言ったようにあなたのシンガーソングライター的な資質が際立っているように思います。『オラクロ』におけるあなたの歌には、アカ・セカ・トリオのフアン・キンテーロやプエンテ・セレステのエドガルド・カルドーゾに通じる魅力を感じますし、曲によってはスピネッタみたいなメロディやコードワークも聴き取れます。そうしたナディスとは異なる点、またシンガーソングライターで影響を受けた音楽家がいれば、改めて聞かせてもらえますか?
「ありがとうございます! 今名前を挙げてくださったような方々は、おっしゃる通りに私の中に生きています。あと、親がよく聴いていたのが、キューバのシルビオ・ロドリゲスとか、ジョニ・ミッチェル、チック・コリアなど。それらの人達も自分の中にずっと生きている存在です。より新しいところでは、ブラジルのハファエル・マルチニやアントニオ・ロウレイロ。彼らも自分にとってすごく大事な存在です。また、より身近な存在ではアナ・アルケッティ(注:ラ・プラタの音楽シーンを代表する歌手/鍵盤奏者で、マリアノ・カンテーロの妻でもある)は、今でも私をいろんな人と繋いでくれる恩人です。
あと、パンデミックが残してくれたものは、自分の中では大きかったと思います。他の音楽家たちと協力して『オラクロ』を作り上げていけたのは、パンデミックがあったからこそで。遠ざかるんじゃなくて、近付けるんだと、みんなで協力してやるんだと、そういった一体感が生まれたからこそ作れたアルバムじゃないかなと感じています」
――パンデミックのおかげで、むしろ様々な都市にいる音楽家たちをリモート録音で繋いだカラフルな作品になったと。
「そうですね、このアルバムの非常に重要な要素が、家にいながら旅行するように作っていけたことで。例えばベース奏者のフェルナンド・シルバはパラナという街にいたし、フルート奏者のファン・パブロ・ディ・レオーネはブエノスアイレス、ルシア・ボッフォはドイツのベルリンから録音に参加しました。自分がいたのはほとんどウシュアイアですが、弦楽四重奏のパートだけは20年8月にちょっとロックダウンが緩んだ頃にブエノスアイレスに戻って録音しましたね」
――ゲストの人選について聞かせてください。ルシア・ボッフォとホアキン・メリーノは、あなたが作品プロデュースを手掛けたシンガーですし、楽器プレイヤーでもアカ・セカ・トリオのマリアノ“ティキ”カンテーロ、ファン・パブロ・ディ・レオーネに、あとはジャズのフィールドで知られるサックス奏者のラミロ・フローレスなど。近年のアルゼンチン音楽における様々なタイプの名手が集結してるような感じです。
「最初から特定のアーティストを選んでいたわけではなく、それぞれの曲に基づいて、どのアーティストに協力してもらうかを考えていく過程で決めていきました。最初から決めていたのは、ギタリストのエルネスト・スナへールとマリアノ“ティキ”カンテーロ。彼らがいなければこの音楽の響きを決めることはできなかったので、2人はとても重要な存在です。
また、サックス奏者のラミロについて話すと、彼に参加してもらった13曲目の〝Azul〟は、ウシュアイアにある湖の深い青の色から着想を得ています。この曲において私が大きな影響を受けたのが、一番好きなシンガーソングライターであるジョニ・ミッチェルによる、サックス奏者のウェイン・ショーターも参加した『風のインディゴ(Tubulent Indigo)』(94年)というアルバムでした。彼女の作品には絵画的な要素があり、そこから大きな影響を受けました。
6曲目でルシアに参加してもらったのも彼女しか考えられないと感じていたからで、彼女の歌声には特別な親密さがあります。これまでにたくさんの方々とコラボレーションしてきましたが、自分が様々な編曲やプロジェクトに関わってきた経験があるからこそ出来たことだと思います」
――確かに、適材適所でゲストが起用されていますね。また、このアルバムを聴いていて、もちろんモダン・フォルクローレの要素も強くあるんですが、アメリカやイギリスのシンガーソングライターからの影響も感じられたので、ジョニの話が出てきたのには納得です。
「私はフォルクローレを意識して取り入れているつもりはありませんが、先ほどお話したようなアカ・セカ・トリオのフアン・キンテーロ、あるいは自分が大学生の時によく演奏していたカルロス・アギーレなどの影響はあると思います。また、ポルトガルからよくアルゼンチンに来ていたマリオ・ラジーニャや、師事していたフェデリコ・アレセイゴルという人物からも大きな影響を受けました。特に、フェデリコはアルゼンチンのリズムと新しい音楽を創造してきた人物ですし、私の音楽に影響を与えたと感じています。昔から聴いてきたクチ・レギサモンやエドゥアルド・ラゴスなどの60~70年代に活躍した人達の音楽からも影響を受けていますし、周囲に存在するものが自然に影響を与えています。
自分たちの世代に感じられるのが、ビートルズとかジョビンとか、アルゼンチンの外の音楽にばかり目を向け過ぎていたこと。自分たちの国の音楽になかなか目を向ける機会がなかったんですよね。でも、それに負い目を感じるところもあって、もっとフォルクローレに目を向ける必要性を感じているし、このアルバムにもそれが現れていると思います」
――あー、多くの日本の音楽家も同じような問題に直面していると思います。
「タケミツ(武満徹)の本を読んでいても気が付きましたが、世界中で同じような問題が起こっていて、西洋の音楽ばかり追うようになってしまって、自国の音楽に注意が向かなくなっていることがありますよね…。しかし、自国の音楽に目を向けてみるとチャーリー・ガルシアとかスピネッタとか素晴らしい音楽家がたくさんいるし、俯瞰して見てみれば、良い音楽が自分たちのすぐそばにあることがわかると思います」
――チャーリー・ガルシアの音楽には、いつの時期の作品にもアルゼンチンらしさが濃密に感じられますし、それがかっこいいと思いますよ。
「ニューヨークでチャーリー・ガルシアがレコーディングしていても、必ずアルゼンチンらしさが出ています。彼はアルゼンチンの音楽の歴史そのものだと思っています」
――出来上がったアルバムを改めて聴いた際に、あなた自身が感じたことなども聞かせてもらえますか?
「私が今まで慣れていたやり方は、録音前にたくさんのリハーサルを行ってからスタジオに入り、録音するというスタイルでしたが、今回は違いました。部分的に音源を送ってもらい、その度に聴いては録音を重ねるというスタイルでした。このスタイルの変化により、個人的には精神的な負担が軽減されましたね。時間的にも余裕があり、心地よく制作が進められました。このアルバムを聴くと、瞑想しているような気分になり、この2~3年の制作プロセスを思い出します」
――今回は以前ほど緻密にスコアを書いて、というやり方ではなかったんですね。
「最初に自分ひとりだけで始めた時は、何も書いていませんでしたね。ただ、ゲストに頼む時には、スコアを書きました。今はライブで演奏することもあるために、スコアを残しています」
――アルバムのタイトル『オラクロ』の意味や、ジャケットのアートワークについても聞かせてください。
「〝オラクロ〟という言葉には〝未来を予測する〟という意味があります。私の作品を通じて、人々が癒され、受動的に聴いて終わりではなく、アクティブにこの作品と関わってほしいという思いが込められています。また、アートワークは、エンジニアのマルコスのパートナーであるソル・コフレセスによって制作されました。彼女の作品には内面との一体感が感じられます。敬愛する音楽家であるマリア・シュナイダー『Thompson Fields』(15年)のジャケットを見た時のように、当時いたウシュアイアの街の様子が(頭の中に)広がるようなジャケットにしたかったんですけど、そう思っている時に出会ったのが、このソル・コフレセスというウシュアイア出身で子供向けのイラストを描いているアーティストの絵で。イラストを見た瞬間に、この人の作品にしたいと思いました。
マリア・シュナイダーの作品に触れていて感じるのは、彼女は聴く人との一体感を強く求めているということです。彼女の作品を買うとコードが付いていて、それを入力すると作品が完成するまでのプロセスが見れたりとか、アートワークに関しても中身との一体感をとても重視しているように思います。私も同様に聴き手との一体感を大切にしていますし、彼女の存在は大きな影響を与えてくれました」
――最後に、日本のリスナーに伝えたいことはありますか?
「日本とアルゼンチンの間には非常に密度の高い音楽の交流があります。そのプロセスがあった上に私のこのアルバムを聴いてもらえることに、とても感謝しています。日本の方々がアルゼンチンの音楽を熱心に聴いてくれることに感謝しています。多くのアーティストが日本に行って演奏していますが、私もいつか日本に行って演奏できればホントに光栄です!」

Artist : JUAN IGNACIO SUEYRO
フアン・イグナシオ・スエイロ
Title : Oráculo
オラクロ
レーベル : THINK! RECORDS
フォーマット : CD
ライナーノーツ解説:吉本秀純
価格 : 2,640円 (tax in)
JAN : 4988044096851
品番 :THCD637