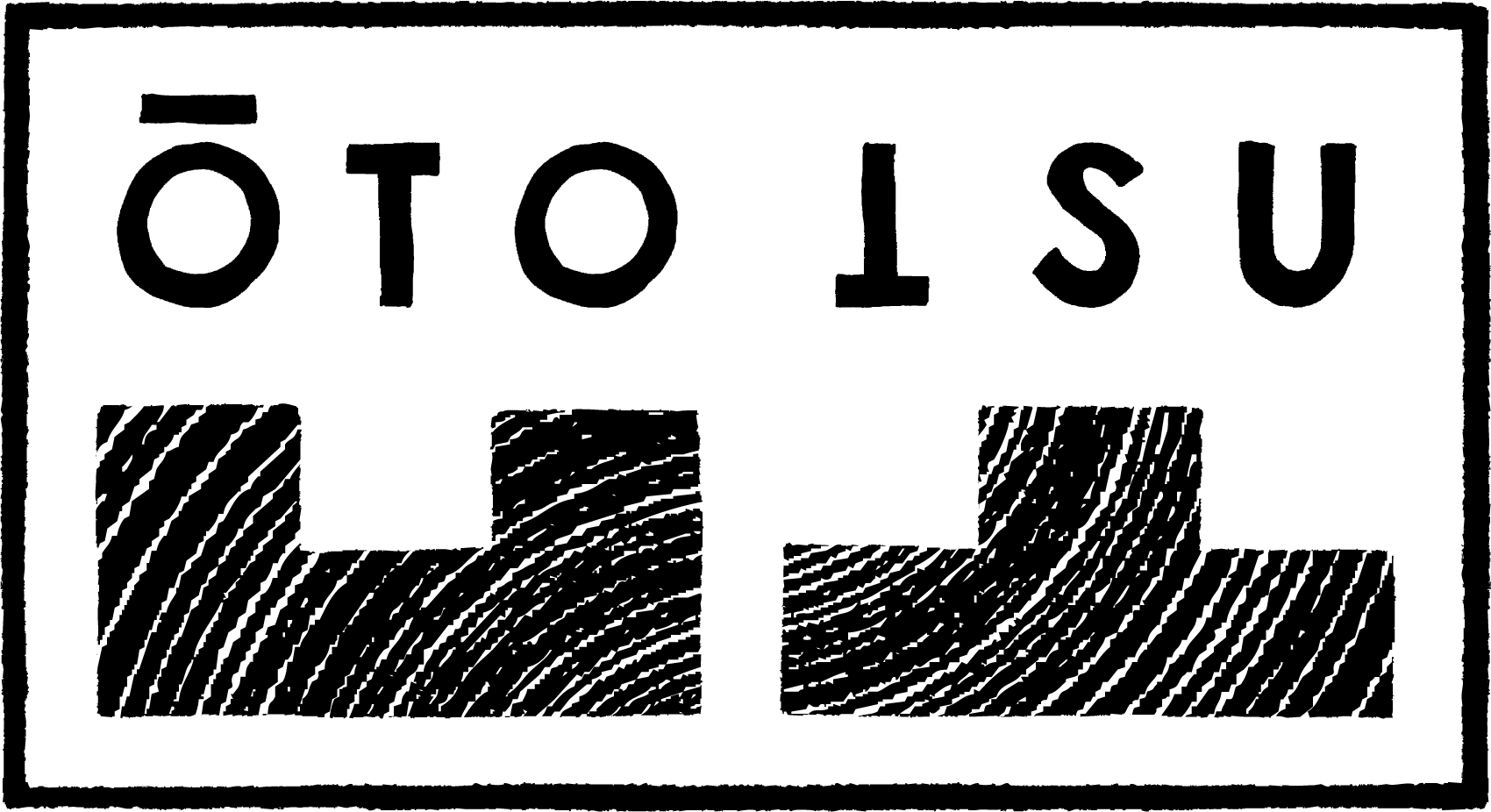低い歌声でありながら、柔らかくて、丸みがある。自在なスキャットなどジャズシンガーとしてのスキルを持っていながら、その歌はボサノヴァにもよく合うし、ブルーズ的な表現もできるし、ポップスとして聴くこともできる。これまでプロジェクトのJAZZLETTERや、バンドSUBCITYの一員としてライヴ活動を行なってきた矢崎恵理(プロジェクト及びバンド活動は現在も継続中)。誰もが聴いた瞬間、その歌声の個性と魅力に引き込まれるであろう下北沢生まれの若いシンガーだ。
そんな彼女の1stアルバム『it』が9月28日に等々力ジャズレコーズよりリリースされる(配信は9月7日)。全曲に参加してプロデュースやホーン・アレンジも手掛けているのは、Silent Jazz Caseなど複数のプロジェクトで活動し、ジャズ・ヴォーカルのヒット作のプロデュースを多数手がけてきた島裕介だ。
アルバム『it』には、矢崎が大学時代から書き溜めてきたオリジナル曲と、ジャズ・スタンダードや、ボズ・スキャックズ、大貫妙子、さらには細川たかしの曲に至るまでの多彩なカヴァーをバランスよく収録。日常のちょっとした瞬間を切り取ったオリジナル曲のユニークな歌詞にも、カヴァー曲の解釈の仕方にも、ほかとは違う個性がはっきり表れ、ひとつのジャンルで括ることのできない大きな可能性と才能が感じられる。島裕介同席のもと、矢崎にこれまでのことと1stアルバムに込めた思いを聞いた。
インタビュー・文 : 内本順一 編集:山口隆弘(OTOTSU)
――生まれも育ちも下北沢だそうですね。
 矢崎
矢崎そうなんです。下北沢はライヴハウスが多いので、中学・高校の頃はよくロックバンドとかも観に行っていました。
――どんなバンドを?
 矢崎
矢崎中高生の頃によく下北沢で観ていたのは、おとぎ話とか、andymoriとか。女性シンガーだと二階堂和美さんがすごく好きなんです。
――もともと音楽的な家庭環境に育ったんですか?
 矢崎
矢崎父親がクラシックやジャズやビートルズを好きでよく聴いていました。趣味でヴァイオリンもやっていたので、私も幼少の頃から習っていて。でも中学のときにヴァイオリンよりも歌を歌いたいと思い、それからジャズシンガーの西村知恵さんとの出会いがあって、ジャズ・ヴォーカルを習うようになりました。
――西村知恵さんからエラ・フィッツジェラルドのCDを渡されたことが、ジャズの世界に入っていくきっかけになったそうですね。
 矢崎
矢崎そうなんです。ボイトレから始めて半年くらい経ったときに、「このなかから次に練習する曲を選んできてね」と渡されたCDがエラ・フィッツジェラルドのベスト盤で。その中から「Cheek to Cheek」を選んだ。それが初めての練習曲でした。
――今回のデビュー作『it』にも収録されています。
 矢崎
矢崎これまで何百回と歌ってきている曲なので。この曲はAメロからCメロまであるんですけど、面白いのはセクションごとに情景が変わっていくところです。Bメロでは「私は山に登ることや、川に釣りをしに行くことより、あなたと踊ることが好きだ」と軽やかに、ポップに歌われる。でもCメロに入ると情熱的かつロマンチックに「私と踊って」と言いだすという(笑)。その構成が面白くて好きなので、軽快さを出して歌いたいと思いました。
――この曲に限らず、矢崎さんの歌には独特の軽やかさがある。それは明確な個性だと思いました。
 矢崎
矢崎50年代くらいのアメリカのミュージカル映画を好きになって、そればかり観ていた時期があったんですよ。『雨に唄えば』を観て、真似して歌ったりとか。ミュージカル映画のセリフから何からコピーしたりして。それが沁みついているのかもしれませんね。
――ジャズ・ヴォーカルを習いながら、大学は音大ではなく美大(武蔵野美術大学)に進まれたんですよね。そのときはまだ音楽で生きていこうと決めていなかったんですか?
 矢崎
矢崎限定せずに、何かを表現したいという気持ちだけがあったんです。私は油絵学科だったんですけど、美大のなかでも油絵学科は表現方法の幅が広くて。例えば日本画学科なら日本画を描く、彫刻科だったら彫刻をするというのが基本としてあるわけですけど、油絵学科には現代アートをやっている人がいたり映像をやっている人がいたりと、油絵だけを描かないといけないというふうではなかった。音大に進むことも考えたんですけど、そうすると毎日音楽を勉強して歌わないといけなくなるなと思って。幅広く自由に表現できそうなのは美大の油絵学科だなと思い、そこに進みました。でも結局ジャズ研に入って、歌ばかり歌っていたんですけどね。それでも油絵と音楽の両方をやることで、違う視野の広がりが得られたのはよかったと思います。
――絵を描くことと、ジャズを歌うこと。似ているところってありますか?
 矢崎
矢崎ジャズ的な歌い方とドローイングが似ているように思います。ジャズは同じ曲を同じミュージシャンで演奏して歌ったとしても、毎回変わっていく。そのときの体調とか場所とか雰囲気によって、同じ曲なのに楽しく感じられるときもあれば哀しく感じられるときもある。ドローイングもまた同じ筆を使って同じ対象をスケッチブックに描いても、その時々で滑らかに手が動いたりそうじゃなかったりして、同じ絵にはならない。それが面白いところだし、近いところでもあるのかなと。
――毎回変化するのが表現のよさであり面白さだと。
 矢崎
矢崎そう思います。あと、画材によっても、油絵は描きながら変化させていくことができる。水彩画だと一回間違ったら取り返しがつかないけど、油絵はその上にまた塗ったり、画面の上で絵の具を混ぜながら作っていくことができるので自分に合っているんじゃないかと思いますね。
――なるほど。そして大学の頃からジャズバーで歌うようにもなり、2020年にはジャズドラマーの橋詰大智さんが率いるプロジェクト、JAZZLETTERに参加することになった。JAZZLETTERがどのような活動をしているか説明してくださいますか。
 矢崎
矢崎JAZZLETTERは、ジャズを始めとするブラックカルチャーをより幅広い世代の人に届けたいというコンセプトの元に結成されたチームで。ミュージシャンだけでなく、ムービーを撮る人、スチールを撮る人もいて、YouTubeチャンネルで演奏動画やMVなどの作品を発信したり、ライヴハウスやクラブでのイベントやライブを通して音楽を届けています。
――実際、幅広い世代にジャズが届いているという感触はありますか?
 矢崎
矢崎ありますね。JAZZLETTERとしてYouTubeチャンネルを始める以前と以降で、聴いてくださる層が変わったように思います。「吹奏楽でやった曲だったので聴いてみたら、すごくかっこよかったです」というような若い人のコメントがついたり。そこではジャズを深く聴いたことのない人でも聴いたことのあるようなスタンダードを歌ってアップしているんですけど、反応はとてもいいですね。
――それから矢崎さんはSUBCITYというバンドでも活動されていますよね。
 矢崎
矢崎JAZZLETTERが十数人のチームで、そのうちミュージシャンの5人がSUBCITYなんです。SUBCITYはオリジナル曲を中心にライヴ活動をしています。
ーー矢崎さんは、これまでどんなシンガーに影響を受けてきたんですか?
 矢崎
矢崎ジャズ・ヴォーカルの方だと、まずエラ・フィッツジェラルド。それからアニタ・オデイが好きで。
 島
島ああ、やっぱり。
 矢崎
矢崎「やっぱり」ってよく言われます(笑)。あとはナンシー・ウィルソンとか。

――最近のジャズ系のシンガーで好きな人は?
 矢崎
矢崎キャット・エドモンソンが好きですね。
――彼女の歌声も特徴があって、軽やかで、ジャジーでありつつポップな感触もありますね。矢崎さんの「まるくなって」を初めて聴いたときも、自分がまず惹かれたのはやはり柔らかで個性的な歌声でした。ご自身が歌声の個性について意識したのはいつ頃ですか?
 矢崎
矢崎どちらかというと、自分の声をずっとコンプレックスに感じていたんですよ。中学生のときに歌が好きで歌いたいと思って始めたんですが、高い声が全然出なくて。友達とカラオケに行くと、みんなaikoさんとか西野カナさんとかの歌を普通に歌うわけですけど、私だけ高い声が全然出なかった。それで練習して、喉を壊したりもして。今でもキーは低いですけど、あの頃はもっと出なかった。
――その低い声こそが自分の個性なんだと気づいたきっかけは?
 矢崎
矢崎男性ヴォーカルの曲を練習していて、しっくりきたときに、これでいいんだなと思えたんです。ビリー・ジョエルの曲とかスティーヴィー・ワンダーの曲が、意外としっくりきて。
――では、ポップやロックやソウルよりもジャズに合う声だなと思った瞬間はありましたか?
 矢崎
矢崎大学生のときにフュージョンのバンドに誘われて、エレキ系の楽器が爆音で鳴るなかで歌ったことがあるんですが、あまり声量があるほうではないので、楽器の音が強いと声が埋もれてしまう感覚がありました。ジャズバー的なところで、アコースティックで歌っているほうが、どちらかというと歌いやすかったし、声が馴染んだ。ああ、私はこっちだなと思いましたそこから西村知恵さんにいろいろアドバイスしていただきながら、ジャズ・ヴォーカル的な歌唱法を勉強した。教本を買って、コピーもたくさんして、自分で録音しては聴くことを繰り返していったんです。
――島さんとは、どのように出会ったんですか?
 矢崎
矢崎3年前くらいに梅ヶ丘の珍品堂というライヴ・バーでライヴをやったんですけど、そのときにベースの深尾久徳さんが島さんを呼んでくださって。島さんはフルートを吹いてくださったんですけど、聴いてビックリしたんですよ。その日に初めてお会いして譜面をお渡ししたのに、本番での演奏がもう自分がその曲で表現したかったことを超えていた。ああ、これがガチのプロかと思って感動したのをよく覚えています。
――島さんは、矢崎さんのヴォーカルにどんな印象を持ったんですか?
 島
島ヴォーカルって、あらゆる楽器のなかでも努力が一番反映されにくいものなんですよ。努力よりも、もともと持っている才能がものを言う。矢崎さんはもともと持っているものが違うというか、さっきの話じゃないけど、アニタ・オデイみたいだなと思いました。日本のジャズ・ヴォーカリストのなかにはアメリカ人の真似をして歌い上げるような人もいますけど、僕はそれって日本人にあまり合わないと思うんですね。そういう意味で言うと、矢崎さんは日本人らしい歌い方で個性を出せる。素晴らしい才能だと思いましたね。
――それで、島さんから一緒にレコードを作りましょうと誘ったわけですね。
 島
島そう。そのライヴが終って、わりとすぐに。僕はレーベル(等々力ジャズレコーズ)を持っているので、やりたいという気持ちがあれば話をしましょうと提案しました。実際に動き始めたのは、その1年後くらいでしたけど。
――そうして島さんのプロデュースによる初めてのアルバム『it』がここに完成しました。矢崎さんの手によるオリジナル(8曲)とカヴァー(5曲)とがバランスよく収録されています。オリジナル曲を書くようになったのはいつ頃なんですか?
 矢崎
矢崎大学3年のときでしたね。
――ジャズ・ヴォーカリストとしての意識のもとに書いていたんですか?
 矢崎
矢崎いえ、正直に言うとそんなに自分をジャズ・ヴォーカリストだとは思っていないところがあって。そこまでジャズに拘っているわけではないんです。今は、ジャンルはなんでもいいかなって感じで。でも19歳の頃は逆に、歌うということについて考えすぎていたところがあって、英語で歌うことは果たして自分にとってベストなのかどうかと考えたりもしていた。歌いやすいのは英語なんですけどね。日本語だとサウンドに対して歌がのっぺりしてしまうことがあるので。だけど普段は日本語を喋っているのだから、やっぱり日本語でオリジナルの曲を書くべきじゃないかと思って。初めは、ジャズはジャズ、カヴァーはカヴァー、オリジナルはオリジナルって分けて考えていたんですが、最近はそれもなくなって、結局全部一緒かなって感じになってきました。
――カヴァーであっても自分なりに咀嚼して歌えば自分の表現になる。
 矢崎
矢崎そうです。むしろカヴァーをするときのほうが、自分の解釈、自分の表現方法を考える必要があるので、簡単じゃないというところもあったりしますし。
――ご自分では、シンガーという意識が強いですか? それともシンガー・ソングライターという気持ちが強いですか?
 矢崎
矢崎シンガー・ソングライターというよりは、シンガーかなって思います。自分で書いた曲じゃないものを、どう歌って自分のものにするかを考えるのが好きなので。
 島
島最初のリード曲をオリジナル(「まるくなって」)にして、次に「北酒場」のカヴァーを出したんですけど、「北酒場」がプレイリスト・インしたんですよ。こういう意表をついたカヴァーで知ってもらうのが、今は大切なんだろうなと思っています。原曲とは真逆のアレンジと歌い方になっているので、個性も際立つだろうし。
――まさかのボサノヴァ・アレンジによる「北酒場」ですからね。原曲の「北酒場」とは違う国に酒場がありそう(笑)
 矢崎
矢崎そうですよね(笑)。私はお酒を呑みに行くのが好きなんですけど、コロナ禍でお店がやっていなかったときに家が居酒屋であるかのようにイメージして呑んでいて、「北酒場」を聴いていたんです。で、これをボサノヴァでやったら面白いんじゃないかと、ふと思って。それで島さんにも入っていただいて、ライヴで歌うようになりました。
 島
島アルバムの制作前に4回くらい一緒にライヴをやったんですが、毎回曲を変えてやってみて、そのなかからアルバム曲をピックアップしました。レコーディングする前にライヴで試してみたいというのがあったので。もともと候補曲はたくさんあって、そこから20曲くらいに絞り、さらに絞ったのがアルバムに収録した13曲なんです。
 矢崎
矢崎オリジナル曲は、このアルバムのために作ったというよりは、大学生活から今に至るまでの思い出深い曲、自分にとって大事な曲をかき集めた感じなんです。だから、ある意味これまでの集大成とも言えるアルバムで。
――レコーディングは、島さん(トランペット、フリューゲルホーン、フルート、トロンボーン)、中村宗仁さん(ギター)、田代卓さん(ベース)、矢崎さんの4人でされていますね。
 矢崎
矢崎中村さんは大学時代からいろいろ一緒にやっていて、以前からアレンジもやってくれていたんです。このアルバムのアレンジも全てやってくれています。田代さんはJAZZLETTERでベースを弾いているという繋がりで。みんな本当に優しくて、私の好きなようにやらせてもらえる雰囲気にしてくれるので、安心してレコーディングできました。自主制作での配信リリースは以前ありましたけど、CDを制作するのは今回が初めてだったので、そういう意味では少し緊張したところもありますけど。
 島
島でも2日間で全部歌いきったよね。ヴォーカリストとして優秀だと思いますよ。時間かかる人はかかりますからね。ピッチ修正とかもまったくしていないし。
 矢崎
矢崎自分にできること以上のことはできないという割り切りがあったので(笑)

――それでは収録曲のいくつかについてお聞きしたいと思います。まずリード曲の「まるくなって」。等身大の歌詞がいいですね。
 矢崎
矢崎自分にとってリアルでないことは書けないし歌えないと思っているので、気張らずに書きました。日記くらいの感じです。
――「まるくなって 四角くなって 形を変えて着いていく あなたに着いていく」という歌詞がかなりユニークです。
 矢崎
矢崎相手や周りの人に自分を合わせてしまう優柔不断な感じを思って書いたんですけど、リリースしてみたら意外とポジティブなことを言っているように感じられるという感想が多くて、じゃあよかったなと(笑)。私自身、人に自分を合わせちゃうところが昔からあって、もっと堂々としていたいと思っているんですけど。
――でも、優柔不断に見られたときに、「いや、形を変えているだけだから」って言えたらいいですよね。
 矢崎
矢崎そうそう、ものは言いようですよね(笑)
――4曲目「ボヘミア遊休声歌」のリラックスした感じも矢崎さんらしくていい。「遊休声歌」という造語も面白いですね。
 矢崎
矢崎去年、勤めていた会社をやめる際に有休消化したんですけど、その言葉にかけて付けました。時間があって、予定を決めずに散歩をしたり、古本屋さんの棚を全部見たり、お参りしたり、ベンチで休んだり。こういうのって最高だなぁって思って書いた曲です。
――矢崎さんの歌詞は、まさしく日常のちょっとしたこと、ちょっとした気持ちの動きや景色を描写していて、日記に近いし、エッセイふうでもありますよね。
 矢崎
矢崎日常生活で、たまにちょっと感動したときとかに言葉がでてくるので。確かに日記のようなものですね。油絵を描くときのテーマも一緒で、日常のなかで見つけた素敵な情景や感情をテーマに描いているんです。歌詞はなるべくありきたりじゃない言葉で、いかにありきたりな日常を書けるかが、自分なりのテーマだったりしますね。
――自分が気に入っている1曲は、7曲目の「うらないの朝」だったりします。ブルーズっぽいフィーリングながらも矢崎さんらしい柔らかさがあるのがいいなと。
 矢崎
矢崎これは1年ちょっと前に作った曲で、初めは弾き語りっぽく作ったんですけど、中村さんが「ブルーズでやったらどう?」とアイデアをくれて、やってみたらいい感じになりました。もともとスウィングジャズばかり聴いてきて、コテコテのブルーズはそんなに聴いてこなかったんですけど、自分なりのブルーズを意識して歌ってみたんです。
――表題曲の「it」。「いま歌うように 描くように 感じる」という一節が、まさしく矢崎さんにとっての確信のようなものですよね。
 矢崎
矢崎確かにそこは自分らしさが出ていますね。
――9曲目は「たかのだいの夜」。たかのだいというのは……。
 矢崎
矢崎美大の最寄り駅が鷹の台なんです。西武国分寺線の駅なんですけど、出たところに真っすぐな道があって、そこを歩いて学校に通っていた。だから、これも日記みたいなものですね。
――歩きながら何かを見たり感じたりして出てくる歌詞が多いんですね。「わたしの朝」は青山通りを歩いているし、「ボヘミア遊休声歌」は2個手前の駅で降りて歩いているし。
 矢崎
矢崎言われてみると確かに(笑)。
――10曲目は大貫妙子さんのカヴァーで「横顔」。この曲を選んだのは?
 矢崎
矢崎大貫さんのライヴアルバムのほうの音源を初めて聴いたときにすごくいいなと思って、ライヴでちょこちょこ歌っていたんです。島さんのホーン・アレンジも素晴らしくて。
 島
島リズムセクションはわりと原曲通りなんですけど、ホーン・アレンジでちょっと変えてみようと。
 矢崎
矢崎歌は自分が曲に寄り添うように歌いました。原曲とは変えようと気張りすぎると、失敗することが多いので、無理に変えないようにしようと。これは自分でもかなりしっくりきましたね。
――続いてボズ・スキャッグスの「We’re All Alone」。前から好きだったんですか?
 矢崎
矢崎好きでした。大学の頃にはア・カペラで歌ったこともありましたし。いろんな捉え方ができる曲ですよね。壮大な曲としても捉えられるし、すごく個人的な歌として捉えて歌うこともできる。そういう幅のある曲だなと。初めはカチっとした感じで歌っていたんですけど、島さんから「もっと自分なりの揺れを表現してほしい」と言われて、ラフに歌ってみたんです。
――13曲目の「Keep Climing With My Family」はとても素直に家族への思いを書いた曲ですね。
 矢崎
矢崎本当にシンプルなメッセージの曲で。途中でラップしているところがありますが、あそこは実際に家族と八ヶ岳を登山しているときに、歩きながら曲でも作ろうってなって、鼻歌をiPhoneに録音して作ったものなんです。
――家族に対して「いつもありがとう」と素直に言葉にするのって、ちょっと恥ずかしかったりしませんか?
 矢崎
矢崎大学の卒業制作で、自分の恋愛をテーマに50枚くらい絵を描いて展示したんですけど、そのときの恥ずかしさに比べたら、たいしたことないです。私にとっては恋愛の曲を書くことのほうが恥ずかしい。
――へぇ~。そういうものですか。
 矢崎
矢崎はい。でも確かにここまでストレートに家族に対する気持ちを歌った曲は少ないかもしれないですね。
――こうして1stアルバムが完成して、今どんな気持ちですか?
 矢崎
矢崎変に片意地張らず、かっこつけようともしないで自然に作れた気がしていて、それはすごくよかったなと思います。島さん始め、メンバーが支えてくれたおかげですね。だからリラックスして聴いてもらえる作品になったんじゃないかなと。これからも日常のなかで「美しい瞬間だな」と思えたときの心の動きを切り取って作品にしていきたいし、そうやって長く歌い続けていけたらいいですね。

it
矢崎恵理
2022.09.07 RELEASE
TODOROKI JAZZ RECORDS