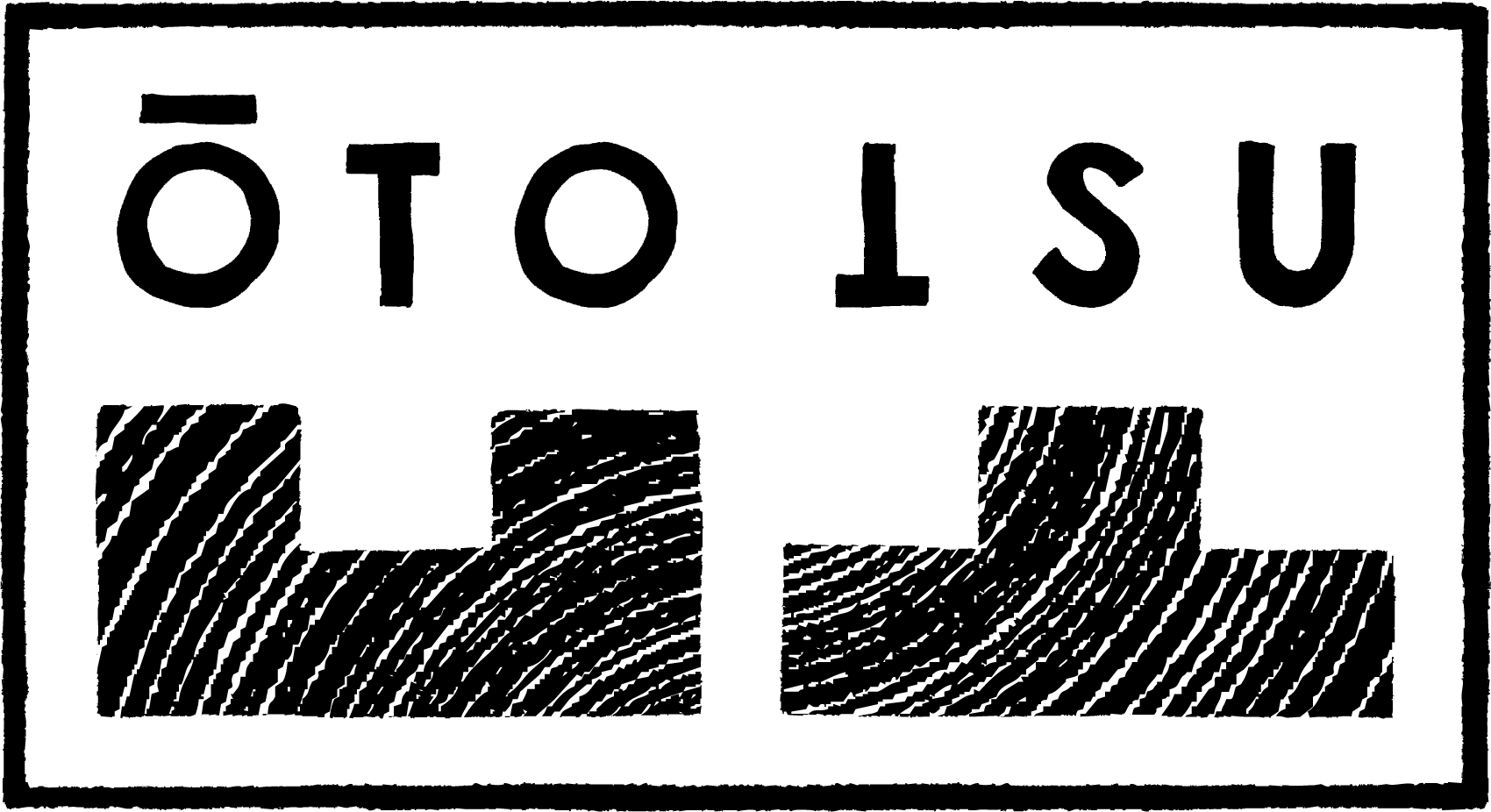『ミュージック・フォー・ブラック・ピジョン』は、デンマーク出身のヤコブ・ブロが、ニューヨークでジャズを学び、自分の音を探求する過程を追ったドキュメンタリーであると共に、彼が出会ったミュージシャンたちの姿も丁寧に描き出している。
どのように企画、製作された映画だったのか、ミュージシャンたちとの間にはどんなストーリーがあったのか、そして、映画を通して何を得られたのか。この映画を巡るバックグラウンドについて、ヤコブ・ブロ本人から語ってもらった。(原 雅明)
構成:原 雅明 – Masaaki Hara
編集:篠原 力 – Riki Shinohara(OTOTSU)
通訳:染谷 和美 – Kazumi Someya
協力:鍵谷 あゆみ – Ayumi Kagitani

ミュージック・フォー・ブラック・ピジョン ——ジャズが生まれる瞬間—— (原題:Music for Black Pigeons)
監督:ヨルゲン・レス、アンドレアス・コーフォード
字幕:バルーチャ・ハシム
制作年:2022年
制作国:デンマーク
上映時間:92分
出演:ヤコブ・ブロ、リー・コニッツ、ポール・モチアン、ビル・フリゼール、高田みどり、マーク・ターナー、ジョー・ロヴァーノ、ジョーイ・バロン、トーマス・モーガン、マンフレート・アイヒャー、他

映画が製作された経緯
——『ミュージック・フォー・ブラック・ピジョン』が制作された経緯から教えてください。
「2007年、8年頃だったと思いますが、『Balladeering』のレコーディングをニューヨークでやってるところに、監督のアンドレアス・コーフォードが訪ねてくれたのです。彼はデンマークで有名な映画監督でしたが、元々ジャズが好きな人で、その時ハイチに赴任していたのもあって、私たちのセッションに興味を持ちました。その時、ヨルゲン・レスも観光客として来ていたので、一緒に撮影をしたいという話になったのがきっかけです」
——映画は単に演奏風景を捉えるだけではなく、それぞれの言葉や日常の様子も大切に描かれています。それは当初から意図していたことだったのでしょうか?
「いいえ。実はこの映画には変遷があって、最初は、ツアーに同行するという話で始まったんです。ちょうど、ニューヨークで録った3部作(『Balladeering』『Time』『December Song』)がノルディック・カウンシル音楽賞にノミネートされたタイミングで、トーマス・モーガンやビル・フリゼールとフェロー諸島やグリーンランドを周るツアーがあったので、それを撮影したのです。だけど、撮ってみると、少し物足りなかったんです。エディターのアダム・ニールセンからの提案で、いろいろ記録したものから良い瞬間を選び出してパッチワークみたいな形で仕上げていくことになったんです」
——シーンや構成に、要望や指示は出したのですか?
「こちらからは何も訊くこともなく、映画は撮られていきました。アンドレアスたちは映画制作者ですが、すごく音楽的なところがある人たちなんです。私も若い頃からそういった彼らの作品が好きで観ていて、特にヨルゲンが60年代のバド・パウエルを撮ったショートフィルム『Stop for Bud』はお気に入りでした。だから、彼らから声がかかった段階でとても嬉しかったのです」
——完成した映画を観た時の感想を教えてください。
「いろいろなことを思いましたが、まずは感謝の思いです。 14年間の自分の人生が綴られているだけではなく、コラボレーターの姿もあって、中にはもう亡くなってしまった人もいて、そういう意味では本当に特別なものができたと思いました。自分の20代後半から今に至るまでの姿が記録されていることもありがたく思いました。最初に観たのがヴェネツィア国際映画祭だったので、お客さんが1500人ぐらい入っている前で大きなスクリーンに自分の顔が映ったのは好きではなかったです(笑)。でも、上映が終わったら、スタンディングオベーションが10分近くも続きました。素晴しかったです」
——映画の描き方については如何でしたか?
「自分の音楽がとても良い形でプレゼンされていると思いました。自分の曲は、書き込む部分と即興の部分のバランスを大切にしているので、どちらをどれだけ盛り込むかというところがきちんと描かれていると思いました。あと、共演者の自由を大事にしている部分も描かれていて、自分の音楽的な志向が良い形で表れていると思いました」

出演者の紹介
——映画に出演している方々についての紹介をお願いします。
リー・コニッツ
「リーとはレコーディングの時に初めて会ったんです。先ほど話した書き込む部分と即興の部分のバランスというのは、リーの音楽がきっかけで考え始めたんです。実は、ベン・ストリートとビル・フリゼールを想定した曲があって、それをレコーディングするときには、リーとケニー・ホイーラーを招く予定でした。ホーンが2本あるので譜面にもきちんと書きました。でも、ケニーが当日具合が悪くて来られなくなって、リー一人の演奏になったんです。その時、リーは僕の書いた譜面をなぞるのではなくて、自分で解釈して演奏し始めました。それは、僕にとって啓示的なことでしたね。もちろん、偉大なプレイヤーですが、あの音が僕のささやかなスケッチの中で鳴っている感覚がとても嬉しかったのです。そのレコーディングがきっかけで、どれだけ最初に決めておくか、どれだけスペースを残しておくか、そういうことを考えるようになりました。サックス奏者はたくさんいる中で、一音を鳴らしただけでリーと分かる、そんなことがなぜできるのだろうと、本当に思います」
ビル・フリゼール
「ビルは最初の頃から僕のことを応援してくれていました。僕のアルバムのプロモ盤をポール・モチアンがビルに聴かせたところ、すごくいいって言ってくれたそうです。音楽に対する理解が自分と通じるところがあるとも、ビルはポールに話したそうです。僕がすごくささやかな、ちょっとした音楽のスケッチをビルに送ると、彼はそれを膨らませてくれるので、それが僕の音楽で起こるのを見ることができたのは、何よりも嬉しかったですね」
ポール・モチアン
「一番のメンターです。ポールとの出会いで人生が変わったと言っていいと思います。彼との繋がりが若い頃からなかったら、リーとの共演も叶わなかったでしょう。そういう意味で、私の音楽遍歴が発展していった、その中心にいる人がポールだと言っていいと思います。彼も自分の音楽をいろんな人と組んでファミリーのような環境を作りながら、繋がりを生んだ人だったので、そういう姿を見ていたこともインスピレーションになりましたし、在り方という部分で私を定義づけてくれた人でもあると思います」
ジョー・ロヴァーノ
「独自の表現力、独自の声を持っているホーンの人で、とても影響を受けています。 本当に信じられないような実力の持ち主です。ジョーと初めてレコーディングしたのが、ポールのトリビュート・アルバム(『Once Around The Room – A Tribute To Paul Motian』)でした。その時も、本当にいろいろな影響を受けました。今度、高田みどりさんがジョーのトリオとやる予定もあります。それもとても楽しみにしています」
パレ・ミッケルボルグ
「私の父が、ルイ・アームストロングとパレ・ミッケルボルグのファンだったんです。それでトランペットをやらされました(笑)。パレと知り合ったのは14年ぐらい前です。いまは具合が悪くてライヴはやってないですが、今でも毎週のように私は彼を訪ねて話をしたりしています。そういう特別な関係にあります。パレの場合、音楽に対するアプローチが他の人と違っていて、いつも本人が言っているのが、音楽をヴィジョンとして考えていない、人生として見ていると。何かしらの人生の意味を音楽で見つけたいんだと言ってました。パレの若い頃はすごく華やかな時代で、彼もマイルスと一緒にアルバム(『Aura』)を作り、そこから独自の道を進んでいきました。彼との友情関係には深く感謝してます」

アンドリュー・シリル
「アンドリューは、フリー・ジャズの人たちとよくやっていました。例えば、3人のバンドで彼が叩いていると、ドラムだけに耳が行ってしまい、他はいいと思ってしまう時があります。 だけど、すべての音を聴いた時に、それぞれに意味を成していると思えるのです。3人が3人、それぞれ勝手な話をしているように感じても、ふっとまとめて聴いた時にちゃんと意味を成していて、その不思議な、何というか音の交わりがあるんです。例えば、絵を見て、何だかわかんないけど、何か感じるものがある、それがわかんないけれど、辻褄が合う、そんな感覚でアンドリューの音楽を楽しむことができます。彼は人間的にもとても素晴しい人です」
ヨン・クリステンセン
「私が若い頃、ECMの音楽も聴いてましたが、マンフレート(・アイヒャー)といろいろ話をするようになった頃に、ヨン・クリステンセンの名前が私の中に浮かんでは来ませんでした。というのも、その当時はもうあまり活動していなかったのです。結構苦労している人だったらしく、年齢もあって活動がなかなかできない状況でした。でも、レコーディングの話をしたときに、トーマス(・モーガン)からヨンの名前が出ました。彼はノルウェーでやったライヴを最近見たと言うので、ヨンを若い人たちの中に入れて音楽を作ることに私も興味を持ったのです。そこから、3、4年、ツアーも一緒にやりました。身体が思うように動かないこともあったんですが、音楽的にはとても面白かったです。ヨンは割とクリアなことをやっていたのが、アブストラクトなことにまた変わってきた時期で、私が一生懸命メロディーを鳴らそうとしている横で、リズムにならない音を出すので(笑)、トーマスが一生懸命に飛び交うアイデアをまとめてくれたりしました」
マーク・ターナー
「昔からいつも練習している人でした。作曲にも熱心に取り組んでいました。本当に一生懸命、自分の道を追求している人だったので、リスペクトしてましたし、一緒にやることに期待も大きかったです。マークは特にハーモニックなアプローチを追求してました。ああいう音を出せる人はいま他にいないと思います。音楽で自分だけの言葉を確立した人です。リーをはじめ、いろいろな人と共演をしてきて経験を積んで、独自の道をいま切り開いています。また一緒にやる予定があるので、それもとても楽しみにしています」
トーマス・モーガン
「トーマスは友人でもあり、彼も日本語を話すことができます。映画ではユニークな人のように描かれていますが、本当にああいう人は他に知らないです。ほぼ、私のすべてのアルバムに参加しているので、私の曲を私以上に暗記しているんです(笑)。レストランに譜面を忘れたことがあったんですが、彼は一回やっただけの曲を「大丈夫」と言って、メロディーもハーモニーも完全に演奏してみせました。時々、ステージでトーマスを驚かそうと思って、キーを変えてスタートしてもまったく苦にした様子は見せません。ハーモニックなランドスケープ的なものを私が提供しても、彼はそこからソロを展開することもできるんです。オーケストラとやった時も、彼は半音上げて演奏を始めて、当然ながらズレを生じるんですが、わざとやっていて何とかしてしまうのです。そういう意味では、トーマスは、キース・ジャレットやジョアン・ジルベルトのレベルにありますよ」
高田 みどり
「みどりさんの音楽が大好きなんです。彼女は一番新しい友達で、突拍子もないことをやらなくてもいいという美意識の持ち主です。マリリン・マズールと一緒のコンサートがあった時に、ステージの両端に二人がいて、マリリンは50個くらいあるゴングを叩いていました。2分間でその全部を叩くことができるような人です。みどりさんは1つのゴングを叩くだけで、そのゴングの音をずっと聴いていて、そのゴングにはいろいろな意味があるのだから邪魔はしません、という感じで聴いていました。それはとても刺激的なステージでした。私はいま一生懸命に日本語を勉強していますし、みどりさんとは将来的にも一緒に音楽を作っていきたいです。いま、音楽の中での東洋と西洋の融合が起こっていると思うんです。ワダダ・レオ・スミスとも曲を作っていますが、そこにみどりさんも加えたいと思っています」
マンフレート・アイヒャー
「マンフレートはヴィレッジ・ヴァンガードでの私のライヴを見て、気に入ってくれたのです。一緒にやりたいと言ってくれました。当時、私の周りはみんなECMで録りたがっていました。私はまだ若くて、マンフレートのことをあまりよく知らなかったので、恐れはなかったです。若気の至りですね。でも、レコーディングでは少しびびっていたかもしれません(笑)。その場にいるだけで一生懸命でしたから。ECMのレジェンドのサイドマンとして最初にやろうということで、トーマス・スタンコのレコーディング(『Dark Eyes』)に参加して、ツアーも一緒にやりました。その後、2015年に初めてECMからリーダー・アルバム(『Gefion』)を出しました。マンフレートはトリオのギター・プレイヤーとして、私をプレゼンしていきたかったのですが、実は私は興味がなかったのです。いろいろな人を招きたいですし、サックスも聴きたいので、ソロ楽器としてギターを弾きたいとは思ってなかったのです。だから、無理をしてやったところもあったんですが、今は感謝をしています。ECMで10枚もアルバムを作りましたからね。それまでは自分のレーベル(Loveland Records)からリリースをしてました。ECMとのコラボレーションが始まる直前に録ったのが、2024年にリリースとなった『Taking Turns』です。このアルバムもいまリリースしてくれたことに感謝しています」
これは、音楽に限らない、人生の映画
——先人から学ぶのが、ジャズの良さであり、伝統でもあることは、映画にも描かれています。一方で、自分の音、自分の表現を見つけるのが、難しい現実もあります。
「学校で学べないことが最も重要だったりしますからね(笑)。これは、音楽に限らない、人生の映画でもあります。それぞれの人がどういう風に生きて、その人がどういう音を作って、それが次の世代にどう引き継がれたかということが、きちんと語られているのが美しいです。みんなそれぞれの影響があって、そのファミリーツリーが見えてくる感じがあります。ちょっとしたニュアンスや変化がきちんと見えてくる、音がきちんと聴こえてくることも美しいと思います。私の子供が出てきたときには、うるっとくるものもありました(笑)」
——映画とは直接関係ないのですが、伺いたいことがあります。昨日(2024年11月10日)、あなたのトリオのライヴを見ました。とても素晴しい演奏でしたが、以前よりさらにギターの音が小さめで、エフェクトを使ってスペースを静かに作っているのが印象深かったです。こういうスタイルで弾くようになったのはなぜでしょうか?
「興味深い質問です。あれでも、ステージから降りた時に今日は結構弾いてしまったな、と思ったのです(笑)。常に、全体の音を聴いているんです。バンドと一緒に作り上げていく、ストーリーを紡いでいくという意識でやっています。状況次第で、自分のプレイヤーとしてのやり方が変わっていくというのもあります。ギターをそもそもソロ楽器だと思っていないんです。ランドスケープを作り上げるための手段みたいなものです。多様性のある楽器で、いろいろな使い方ができるから、セッティングを凝らして、聴くことを楽しみたいです。例えば、トランペットはソロ楽器として優れていると思いますが、それと同じことをギターでやろうとは思わないです。少なくとも、ギターはそういう楽器だとは私の耳には聴こえないのです。トーマス・スタンコと一緒にやったときはとてもエネルギーに満ちていて、そこで自分はギターでどうすればいいのかと思ったのです。スタンコは長いソロをやり、ピアノもドラムも長いソロをやりました。曲として既に完成しているので、ここにもうギター・ソロはいらないと思ったんです。スタンコにはライヴの後に言われました。「自分の居場所は自分で見つけなさい」と。それで、エフェクト・ペダルを使って、自分の周りにあるものを取り囲むような音を作るアプローチを見出したのです」


JAKOB BRO (ヤコブ・ブロ)
デンマークのコペンハーゲン在住のギター奏者、作曲家。
『ニューヨーカー』誌では、「ヤコブ・ブロのギター・スタイルを指で表現しようとするのは、空気の本質を表現しようとするようなものだ」と評されている。
バンドリーダーとして17枚のアルバムをリリースし、そのうち6枚は国際的に高い評価を受けているECMレコードからリリースされている。トーマス・スタンコとポール・モチアンの最後のバンドのメンバーでもあり、その他自身のバンドなどで世界中をツアーしている。
2024年12月には、作中にも登場するメンバーとの作品を収めた、ECMからは7枚目となる最新アルバム『Taking Turns』がリリースされた。