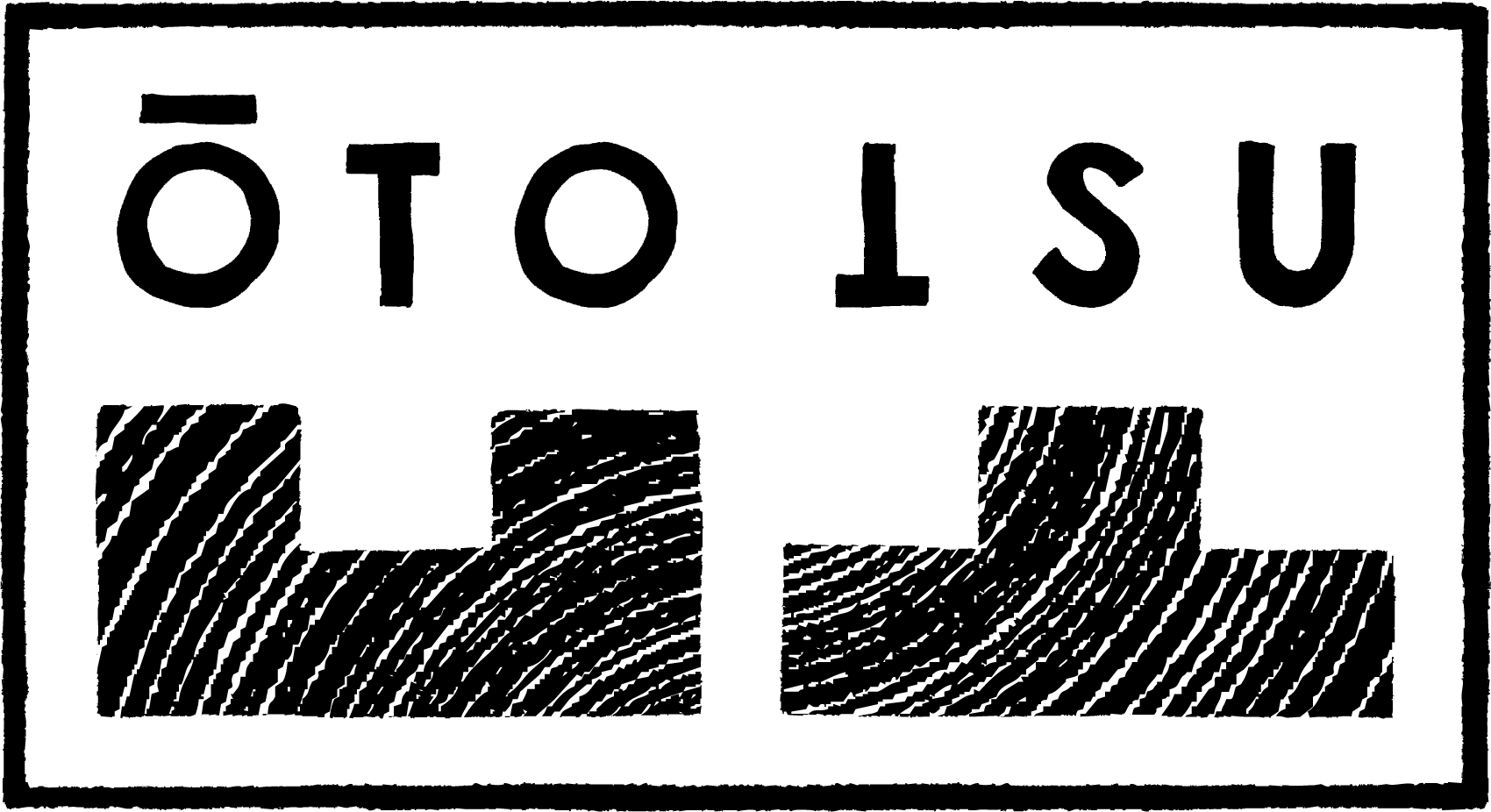富士市吉原の土着のリズムが古今東西の音楽と接続されたとき、現代の「ジャパニーズ・ミュージック」が立ち上がる。遊び心としなやかな実験精神も重要なスパイス。おてんのさんや荒神様も踊りまくる熱狂のリズム! 大石始(文筆家
静岡県富士市吉原。毎年6月に2キロにも満たない範囲で21町内のお囃子と山車が絢爛豪華に入り乱れ行われる「吉原祇園祭」。幼いころからそこで育ったメンバーによって結成された吉原祇園太鼓セッションズが、1stアルバム「Taiko!」をリリースする。お囃子や民謡、盆踊りなど、日本の”ルーツ・ミュージック”を独自の解釈で大衆的に表現するバンドやアーティストが続々と登場する中、先駆者とも言える民謡クルセイダーズのリーダー・田中克海と、吉原祇園太鼓セッションズのメンバーである内藤佑樹(ギター、篠笛、鉦)、川島麻友美(サックス)による対談が実現。セッションズのプロデューサーであるTOP DOCA(こだまレコード)を司会とし、「ジャパニーズ・ミュージック」のこれまでと現在地、そしてこれからについて、初期民クルの拠点である福生のバナナハウスで大いに語ってもらった。今回は後編をお届けする。(全2回/後編)
写真:Yotch
構成・編集:森崎昌太

Artist : 吉原祇園太鼓セッションズ
Title : Taiko!
レーベル : テンテケレコード
「ダヒル・サヨ feat. ナツ・サマー」
8/6より先行配信中!
CDはこちら
価格 3,520円 (tax in)
前編はこちら

そこからお囃子がより面白くなっちゃって。そういう色眼鏡で見ていくと、身の回りに超絶テクの太鼓おじさんがいっぱいいたんですよ。(内藤)
内藤佑樹:
お囃子っていわば打楽器でパーカッションなわけですけど、それは音楽的なものとは思わないでやっている。細野さんの音楽はリズムを細かく”ずらす”んですけど、それと同じことをナチュラルに吉原のおじさんたちはやっているんですよ。音楽的にすごく高度なことを。お囃子は結局、小太鼓と大太鼓の応酬で出来上がっていて、ベースの小太鼓に対して、相槌を打つ大太鼓がツッコむのか、もたらせるのか、といった合いの手がすべてなので、そこでノリをコントロールするのが技術なんです。それを別に音楽的とは思わず、街にいるそこら辺の酔っ払いのおっちゃんがやっているわけですよ。
田中克海:
“ずらす”とかっこいい?かっこいいというか気持ち良いのか。
内藤佑樹:
そう。もたり気味で気持ちよくなったり。逆に、川島さんの町内なんかは、もっと突っ込め突っ込めって感じで。それぞれスタイルがあって。で、お祭り本番だと山車と山車が向かい合って競り合う戦いなので、(リズムが)走って走って、むしろそれで相手に勝っていくみたいな感じで。
田中克海:
相手がいる話でもあるわけですね。

内藤佑樹:
そういう戦闘的なスタイルにいく町内もあれば、まさしく「蝶々-SAN」とか細野さんのように、チャチャチャのリズムじゃないけど、そういう気持ち良い感じを極めている町内もある。けっこう町内ごとでキャラが違うんですよ。そのキャラが、町内ごとにどんどん研ぎ澄まされていく。
川島麻友美:
けっこう自分の町内が一番、みたいのは思っている。その町内にずっといるから、そういうものだと思っているというか。 でも、それはそれで、生活の中でお祭りのその期間だけのもので。ある時、内藤さんに「音楽聴いてると全部太鼓に聴こえてきて、太鼓合うじゃんって思うんだよね」みたいなことを言われたんですよ。
内藤佑樹:
そうそう。 ファンクとか聴いていても、コンガなり、打楽器が入っているところ。音的には、小太鼓が高い音なので、ちょっとコンガと音が似ていたりするわけです。ボンゴとか。
川島麻友美:
「それがお囃子の太鼓に聞こえる」みたいなこと言われたときに、この人なに言ってんの?って思って(笑)。なんで太鼓が出てくるんだろうって感じだったわけですよ。でも、だいたいの青年がそういう感覚だから。お囃子と音楽は結びついていない。
内藤佑樹:
太鼓だからドラムとかと同じ楽器なはずなんですけどね。それで細野さんの「蝶々-SAN」を聴いている時に、これ、にくずし(お囃子の演目)とノリが一緒じゃん?みたいなものに気づいて。そこからお囃子がより面白くなっちゃって。そういう色眼鏡で見ていくと。 身の回りに超絶テクの太鼓おじさんがいっぱいいたんですよ。

田中克海:
やばいね。その眼鏡をかけちゃった日にはヤバいのだらけになるわけだ。急に周りが。
TOP DOCA:
たぶんセッションズに急に入っても叩けるもんね。あのお囃子のリディムだよって伝えれば、おっちゃんみんな叩ける。
内藤佑樹:
そうですね。基本的には僕らは吉原のお囃子を使ってやっているので。乱入できるパートも用意してあったりします。街を歩いているおじさんが篠笛の名手だったりとか、酔っぱらいのおじいさんが町内の歴史を作ったレジェンドだったりとか。そういう街なんです(笑)。
TOP DOCA:
祭りに生きている。
内藤佑樹:
僕はたまたまそれが音楽とつながっちゃって。あと、けっこう周りにヒントを与えてくれる人もいて。沼津出身のリプラス(re:plus)君っていうジャジー・ヒップホップをやっているトラック・メーカーの先輩がいて。ヒップホップのトラックはリズムを敢えて揺れるようにずらして作っていて、そのぐらいの方が気持ちいいよ、みたいなことを教えてくれて。そういうものなのか、と思って、まさしくロバート・グラスパーが2012年に出した『Black Radio』ではすごく(リズムが)揺れていたから、それを聴いて「そうか、ヒップホップ的なリズムをジャズの人がやるんだ」って知ったのが、ちょうどお祭りと音楽の関連性に気づいた時期と一緒だった。
田中克海:
おもしろい。
内藤佑樹:
その時のドラムのトレンドが”ずらす”みたいな感じでしたけど、あのお祭りの太鼓のおっちゃん、クリス・デイヴと同じじゃないか!みたいな(笑)。 「蝶々-SAN」で気づいたことがさらに補強されていった。お祭りに参加していながらサックス吹ける川島さんが身近にいたんで、一緒にやってみる?って感じで始めたら、だんだんこうなっていったという感じなんですけど。
田中克海:
最初は何人で始まったんですか?
内藤佑樹:
最初は5人。大太鼓、小太鼓、サックス、べ-ス、ドラム。打楽器の比率が高いんです。最初はギターもいなかったです。

川島麻友美:
今は9人。太鼓、太鼓、太鼓、鉦、ジャンベ、ドラム。 ベース、ギター、サックス以外は打楽器じゃないですか。
内藤佑樹:
9人中6人の打楽器まみれ(笑)
田中克海:
メンバー皆さん違う町内会なんですか?
内藤佑樹:
違います。町内が違うと別の場所で練習しているんですが、曲は似てるんです。 同じ「おだわら」っていう演目やったり、「にくずし」っていうもう一つの演目をやるんですけど、それぞれ町内ごとに”なまり”が違うので、一緒にたまたま別の町内の人が集まっても、いきなり「せえの」で完全に一緒にはできない。若干“なまり”が違っていたり、展開も違う部分があるので。基礎は似ているけど、ちょっと違う。だから僕らは最初の頃はどの町内の「おだわら」をべースにやろうか?とか、すり合わせながらやったりしていました。意外とバンドの中でお祭り内の異文化交流があったりするんです。
TOP DOCA:
民クルもセッションズもアジャテもそうだし、結局根っこになるものが日本の音楽をやっているから、今後そういった音楽をみんな見直していくのか。このあたりが第一世代としてやって、はたまたどんどん次の世代がやっていくのかなど、今後の展望はある?それは別に考えずにやっているのかな。
田中克海:
今はそう。まずは日本全国の津々浦々のやつをレパートリーにできて、どこ行っても演奏できるようにはしたい。
そういえば民謡との交流はないんですか?
TOP DOCA:
お祭りの中ではないかもね。
内藤佑樹:
そうそう。唄はほとんど残ってなくて。
TOP DOCA:
セッションズとかで民謡やったら真似になるから(笑)。
田中克海:
でも、それはそういうリディムが根幹だから。そこで何をやっても、もうそれはセッションズでしょ。
内藤佑樹:
それで言うとあれですね。民謡って本当にたくさん曲があるけど、吉原祇園祭の中でやってる演目って多分10曲ないんですね。
田中克海:
それが全部の町内に共有されているものなんですか。
川島麻友美:
全部に共有されているわけではないですね。うちの町内は知らないけど、あの町内はやっている、みたいな曲もあります。
内藤佑樹:
町内によっては2曲か3曲しかやらないところもありますね。
川島麻友美:
うちの町内はちょっと独特で、先輩がお囃子好きすぎて自分で曲作っちゃって。その新しい演目は、うちの町内の曲として継承されていますね(笑)。
内藤佑樹:
それも長く続いたら伝統になるもんね。

田中克海:
でも、そういう意味じゃ、セッションズの中ではどういうふうにバリエーションをつけてるの?
内藤佑樹:
テンポの速い「おだわら」っていう競り合いのお囃子と、「にくずし」というゆっくりのお囃子。下手するとその2つだけで祭り当日回しているぐらいのお祭りなので、バリエーションが作れない。演目の少なさというのは最初に突きつけられたと言うか。曲増やせるの?と。バンドとしては、当初演目の少なさをめっちゃ悩んだんですけど、例えばロック・バンドで8ビートが3曲続いても、それ全部同じだからダメじゃん、とはならないよね、というふうに考えてみたり。ちなみに、同じお囃子でもニュアンスが違えばいいのではないのか、というのが、自分の中の現時点の解釈(笑)。シャッフルっぽくするとか、テンポを早めて踊れるようにするとか、ファンクの味付けにするとか。だから今回のアルバムの中でも同じお囃子を違うテイストでやったりとかしています。
田中克海:
やっぱりそうなんですね。なるほどね。でもセッションズの、そういう意味じゃ特色っていうか、それこそいろんなタイプの町内で、リディムのバイブスが違うっていう意味では、セッションズの独特のノリみたいなのもあるんですか?
内藤佑樹:
たぶん、そのメンバーから出てくるグルーヴはありますね。
川島麻友美:
セッションズの中だと、お囃子ができるメンバーが8人いるんですけど。
TOP DOCA:
その太鼓の人の町内によるんだよね。
川島麻友美:
そう、だから組み合わせが変わったり、ただ小太鼓、小太鼓、大太鼓ってやるとして、誰が大太鼓をやるかによって、全く同じ曲をやろうとしても全然変わりますね。それはたぶん、その人のキャラもあるし、町内のキャラもある。
内藤佑樹:
そう、確かに人でやっている。「ノワケ」はユウキ(高橋ユウキ)がイニシアチブを取るから激しい色になる、とか。あとは、この曲は逆に激しくしないけど、調和されているお囃子のタイプの曲になる、とか。確かにメンバーの組み合わせでの変化っていうのはありますね。
この前ちょうど、今名前が出たメンバーのユウキくんが来れないライブがあって。「ノワケ」っていう僕らの一番のキラーチューンで一番ノリのいい曲があるんですけど、それはユウキ君が引っ張ってるんで、彼のアグレッシブなノリで流れていく。CDも内容はそうなっている。でも、この前違うメンバーでやったら、やっぱり雰囲気の違う「ノワケ」になったんです。
田中克海:
なるほど。でも、それはそれでね。
内藤佑樹:
そうそう。それはそれでまた違って良い。今回のアルバムの「ノワケ」はアフロビートっぽい中で太鼓が攻めている感じになっていますけど、曲頭に最初から太鼓を叩いているユウキ君のキャラがけっこう出ているんですよね。
田中克海:
そういう感じなんですね。そういうのがわかってくると、また、面白いですね。
内藤佑樹:
なんとなく考えていただけでうまく言語化できてなかったんですが、今言われてみて、メンバーの持つキャラクターとかノリで曲を作ってみるの、面白いかもしれないですね。
田中克海:
人にリズムの名前が付いているって感じがして面白いよね。

TOP DOCA:
あと、ゆくゆくは民クルと何かセッションしてもらって。
田中克海:
それこそお囃子と民謡が一緒にやったことないというか。
TOP DOCA:
やってみたいね。なんか面白いのになりそう。
田中克海:
それがリディムと考えれば、別にそう、ワールド・ミュージックの一個じゃんみたいな。そういう感じで思えばいけるのかな。でも本当、ナイヤビンギじゃないけど、そういう感じの根源的というか、あんまり他に例えようのないね。
TOP DOCA:
ハート・ビートというか。それがベースにあって、それに乗っかるといろんなものも乗っけられるからたぶん、みんなで一緒に本当にセッションできるかもね。
田中克海:
そうですよね。それ面白いですよね。ぜひとも。なんかやりたいですよね。ほんといろんなタイプの人が出てきているから、そういう人がけっこう集結するような音楽フェスとかね。面白そう。
TOP DOCA:
民クルが旗振ってくれるとスムーズですよ。それが一番早い。ぜひ。民クル祭。
田中克海:
自主企画をやったことがなくて。結局呼ばれてやっていることが多いから、やってみたいな。盆踊りは盆踊り、こういうお祭りというか、お囃子はお囃子で、お客さんの見方も違うじゃないですか。そういうのもなんとなく面白いなって思い始めているんですよね。
TOP DOCA:
盆踊りも流行っていたりとかね。いろんな音源かけたりとかしていてね。
田中克海:
完全にどこかの国の独特の祭りみたいな、ちゃんとフォーマットがあるじゃないですか、盆踊りって。無料で誰でも入れて、デカい音鳴らしてみんなで踊って。お客さんにどういうふうに参加してもらうのか、というときに、あのステージとお客さんの距離感よりは、ぐるぐるして、誰が入ってもいいし抜けてもいいし、敷居が低くてみんな楽しい。そういうのって、そういう意味じゃ、新しいというか面白いフォーマットだなって。
TOP DOCA:
そういう意味では民クルもセッションズも、みんな飛び入りですぐできるような感じでね。日本人好みな音楽なのかな。そこで改めて今、若い連中がいろいろやっていて、新しい風を感じていて。昔からあるけども、そんなにみんなやってこなかったことを、続けてやっていく形になってシーンができている。これはバーッともっといくと、たぶん途中で飽きたりとか、そしてまた復活してとかして、流れていく。そういう流れなのかなと思って。
田中克海:
わりと無限に可能性はありそうだなと。
TOP DOCA:
結局、日本のものでもあるし、それはずっと続くものだから。
オリジナルで民謡って作れるんですか?
田中克海:
新民謡っていうのがあるから。まあ、この土地の民謡がこれだって言えば、それが民謡になっていくっていう意味ではあれだけど。でも基本的に、やっぱりバトンを受け継いでいく種類の音楽だから、そういう意味では自分らはちょっと無責任なところもあるっていうか。芸術作品じゃなくて、やっぱり普段どんちゃん騒ぎするための音楽みたいな、そういう雰囲気がなくなっちゃうとね。
結局、それこそ細野さんとか坂本龍一さんとかは俺らより全然世代は上だし、日本に対するコンプレックスって、俺らよりも強いんだと思う。それでも日本人だ、みたいな感じでアプローチして、すごく芸術作品みたいなものを作ってクリエイティブ性も高い。クリエイティブなものを作るっていう気持ちが、たぶん、すごくあるんだと思うんですけど。俺らもでも、コンプレックスはある。洋楽世代っていうか。ベストヒットUSA世代だから、洋楽一番で聴いてきたから、それはもうしょうがない。とはいえ、でも上の世代の人たちよりは、ちょっと違うアプローチだと思うし、何よりみんなで楽しめるやつでやりたい。それはわりとみんな共通している。あんまり難しいのではなくね。

TOP DOCA:
さっきバトンを受け継いでいくみたいな話があって、令和の今、民クルとかセッションズがやっていて、次の元号になった時に、昔はこういう人たちがいたけれども、その次の世代が似たようなことをやっているような。さっき言ったフレディさんに色がないみたいに。それでずっと続いていくのが土着していくものなのかな、と。色ついちゃうと、結局はあれか、ってなっちゃうから。
民クルはもうちょっと”野良”っぽい感じ。そういうところがいいと思う。楽しい。自分たちが好きなところだし。(田中)
田中克海:
セッションズの皆さんはリリースした後とかの展望はありますか?
TOP DOCA:
バンド、バンドしてる感じゃなくて、やっぱり自分の生活があってのバンドだから。これを引っ提げて47都道府県行こうっていうのもないし。
内藤佑樹:
僕らは完全に流れるままいったら、面白い方向にいってしまっていて。
田中克海:
そこがまたかっこいいですよね。
TOP DOCA:
そう、生活があって、今はこうやってバンドをやってるって感じなんで。
川島麻友美:
びっくりしています。私、お祭りがあるのも太鼓を叩くのも当たり前で、やったら面白そうだねって、始めたバンドがこうなってて。なんでここに今日いるんだろう、とか(笑)。レコード出して、フェスとか出て。フェスだって、サックス1本で出ますって言ったら、もっともっとすごい人がいて。うわって思うんですけど、でも、このセッションズの中だったら、この21町内のすごい狭い中で、太鼓を叩いてサックス吹けるのは私ぐらいしかいないかな、と思えるから、なんとかいるんですけどね。
田中克海:
十分すごいですけどね(笑)
内藤佑樹:
お囃子を解釈していながらサックス吹ける人はそうそういないし。
田中克海:
でも思うのは、ミュージシャンて本当にいっぱいいるけど、やっぱりコンセプトがあるってめちゃめちゃでかい。だから、うちらもすごくカリブ音楽をめちゃめちゃ追求しているバンドじゃなくて、意外とふんわりしている。俺なんかロックなんで、どちらかというとギターがワウワウしてればずっと楽しい方だし。そういう意味では、そういうところに忠実じゃない。だから普通にそれでやると、たぶんあまり説得力はないんだと思うんです。
でも、民謡を軸にやっていますっていうことで、こうアクロバチックに座っていられるっていうか。音楽のスタイルとは別で、やっぱりコンセプトがあるかないかは、もうめちゃめちゃ大事。やっている方のモチベーションが続く。あまり辛くないっていうかね。続けていると、だんだん辛くなってきたりする時とかがある。いい曲書けないな、とか、なんでこのリズムができるんだ!とか、バック・ビートが!みたいなことがないっていう。
川島麻友美:
確かにずっと楽しいです。お囃子が好きなんですよね。やっぱり。
TOP DOCA:
セッションズは俺が見ていると、まだまだ可能性があって、まだすごく狭いところでしかやってない。もっといろいろできると思う。楽曲の他に、メンツ的にもっともっといろんなジャンルを取り入れてもいいし、クンビアとかやっても面白そうだし。ただこれはプロデューサー目線で、バンド・メンバーがそれをやりたいかどうかわからない。俺的にはもうちょっといろいろカリプソだったりだとかやりたい。そっちにいったら面白いから。
田中克海:
他の太鼓の人の音楽って聴いたりするんですか?聴くっていうか、参考とかで。
内藤佑樹:
他の人ってなかなかいないんですよ。だから本当にアジャテ(=AJATE)さんは、同じことを考える人いるんだって、すごく嬉しかったです。やっぱりアフロとかになるよねっていうのはすごく共感できるし。めちゃくちゃシンパシーを感じて、FUJI&SUNでお話させてもらって。FUJI&SUNはすごく僕らにとって大きいです。僕たちが興味を持つような方を呼んでくれてて。それはたまたま時代がそうなのか、僕らがいるからそうしてくれているのかは分からないですけど。アジャテさんはお囃子バンドあるあるエピソードも似ていましたね。

田中克海:
なるほどね。たしかに他にそんなバンドいないもんね。
内藤佑樹:
鼓童さんとかもありますけど、和太鼓に本当に集中してる方々は、大きな太鼓を使っていたり、きっと僕らとベクトルが違う。それに比べて僕らはお囃子でやっていて。
田中克海:
やっぱりストリート感はあるよね。
内藤佑樹:
そう。ストリートで行われているものなので、やっぱり暮らしと共にあるものというか、街と共にあるものっていうのがあるんですよね。
田中克海:
そこがいいですよね。そこがかっこいい。

内藤佑樹:
これはコンプレックス的なことでもあるんですけど、本当に追求して和太鼓をやっている方って、叩き方もすごく綺麗。フィジカルもあるし、すごく良い音が鳴る。でも僕らはそういうところと少し違うものなのかなと思う一面もあって。野蛮な叩き方もするし、フォームなんかも合理的な叩き方ではないかもしれないんですけど。
けっこう町内ごとの思想がガラパゴス的に醸成されているような部分があって、先輩とか声のでかい青年が「こうしよう」って言ったらそうなるみたいな。正しいかどうかというより、その町内の中での空気感が重視される。でも、それがじわじわ固まっていって、その町内の伝統みたいなことが醸成されて。太鼓の叩き方も各町内独自の方向に進化していく。
そういう意味でも、あんまり他の太鼓ってなったときに、参考があまりない。民クルさんも同じですよね。最初におっしゃっていた正解がないってのはそういうことなのかな、と。
田中克海:
東京キューバン・ボーイズとか、そういう意味ではありますけどね。江利チエミとかも。
内藤佑樹:
時代がちょっと違う感じもありますよね。
田中克海:
たしかに。別モノといえば別モノ。うちらもわりと庶民的。キューバン・ボーイズはやっぱりアップ・タウンでちゃんとしたショウをやる。ちゃんとこうタキシード着て、サラブレッドがいて。だから、民クルはもうちょっと”野良”っぽい感じ。そういうところがいいと思う。楽しい。自分たちが好きなところだし。でも、吉原の町内の話を聞いていると、まさにストリートってことですよね。ニューオーリンズのブラック・インディアンのああいう感じにも似ているよね。
内藤佑樹:
まさしくそうなのかも。ちょっとシンパシーを感じますね。マルディグラ。ぼく山岸潤史さんがすごく好きで。
田中克海:
ワイルド・マグノリアス(=The Wild Magnolias)だ。
内藤佑樹:
山岸さんのマネして、ギターはテレキャスの白いやつなんです!
田中克海:
山岸潤史の影響で?
内藤佑樹:
そうです(笑)。ファンクも、ニューオーリンズだとその地域のものと結びついていますよね。
田中克海:
そうですよね。やっぱり「蝶々-SAN」のあのリズム。
ニューオーリンズ・リズムみたいな。ワイルド・マグノリアスもそうだけど、ブラジルの、リオのカーニバルみたいな衣装を着けて、スパイ・ボーイとか役割がある。ギャングの模倣なんですよね、あれ。お前はスパイ役、お前はビッグ・チーフだ、とか。そういうフォーメーション。楽しさというか。だから、そのエリアでリズムが違うのも、たぶんあそこのプライド、アイデンティティなんだろうな。
内藤佑樹:
アイデンティティですね。
田中克海:
さっき話した岩手の獅子踊りの踊り手さんが、演出に合わせるとリズムをスクエアなリズムの取り方で踊らなければいけないが、普段踊り手はスクエアじゃなく踊るようにノっているので合わせるのが大変だと言っていたんですよね。
内藤佑樹:
セッションズも、太鼓はリズムに大きく揺らぎがあるけど、それに比べるとドラム、ベース、ギター、サックスはスクエア気味になるので、揺れとスクエアなノリの中間で太鼓と楽器隊をどこで合わせるかを曲によってコントロールしています。すり合わせてどっち寄りで落ちつかせるのかとか、よく話していますね。
田中克海:
ドラマーは大変ですね。
内藤佑樹:
そういえばアジャテさんも言っていましたね。アジャテさんは最終的にドラムレスの判断に至ったそうで。和太鼓があって、竹の楽器もあって、たぶんあれはキックとかハイハットとかのドラムをバラした役割と解釈しているから。鉦もあるし、ドラムはなくす判断をしたらしいんです。僕らは逆のベクトルで、お囃子から抜け出すために、見せ方としても、僕たちの内部の意識としても、ドラムがいた方が普段のお囃子っぽさから抜け出せるんですよ。バランス的にはめっちゃぶつかっているところがあるんですけど、でもキックは太鼓よりもっと下に居たりするから、それはそれで踊るために欲しいし。
川島麻友美:
それこそ「The Chicken」の真ん中らへんとか、私、本当にその太鼓とドラムのとこだけで一生聴いていられるなって思います。
内藤佑樹:
お囃子だけを聴いた時、普段、大人の人はあまり踊らない。でも、本来吉原のお囃子は踊れるものでもあるはずで。幼稚園に入る前くらいの小さい子だとけっこうお囃子だけで踊っていることがあるんですよね。大人になった意識が踊らせなくするのかわからないんですが。でも、さっきのショウ・アップの話じゃないですけど、ドラムが入ってベースがいてってなると、お客さんは踊ってもいいと思える。
田中克海:
たしかに。そういう意思表示にもなる。
内藤佑樹:
そうです。見た目的にも音的にも、踊っていいよと示す装置としてドラムは必要なんですよね。
川島麻友美:
最初の時は、それが戸惑う時もあったけど、最近、太鼓が握っているな、みたいな瞬間を感じることもあって。うまく言えないんですけど、太鼓が全部そのテンポとか雰囲気をうまく握っていて、ドラムがそこにうまいこと絡む。そうなってくると、さっきのフレディさんの話じゃないですけど、最初はもう一生懸命、私がメロディ吹かなきゃ、テーマ吹かなきゃ、みたいに思っていたけど、あっ、やっぱ太鼓、お囃子なんだなって。本当に最近ちょっと思ってきていて。あ、私、そのうちいなくなりたいな、ぐらいに(笑)。
田中克海:
なるほど。だんだん信頼関係できてきますしね。うちらもフレディさんなんか、最初は「やりたくねえ」ぐらいの雰囲気で、全然違う絡み方で(笑)。やっぱり信頼関係ってすぐにできないから、最初すごくフレディさんもみんなも遠慮していて。お互いに。だって、こっちだって民謡とか知らねえし、みたいなのがあったけど、ライヴやったら盛り上がる。じゃあまた次、頑張るか、みたいな感じでやっていたりして、だんだんと、こういうことなのね、と、ちょっとずつ分かってくる。みんなそうなんじゃないですか。アジャテとかも、やってみてトライして、なんだろうな?とか言いながらやっている感じがする。正解がないんですよ。
内藤佑樹:
正解がないんですよね。
田中克海:
だからまあ面白いという。