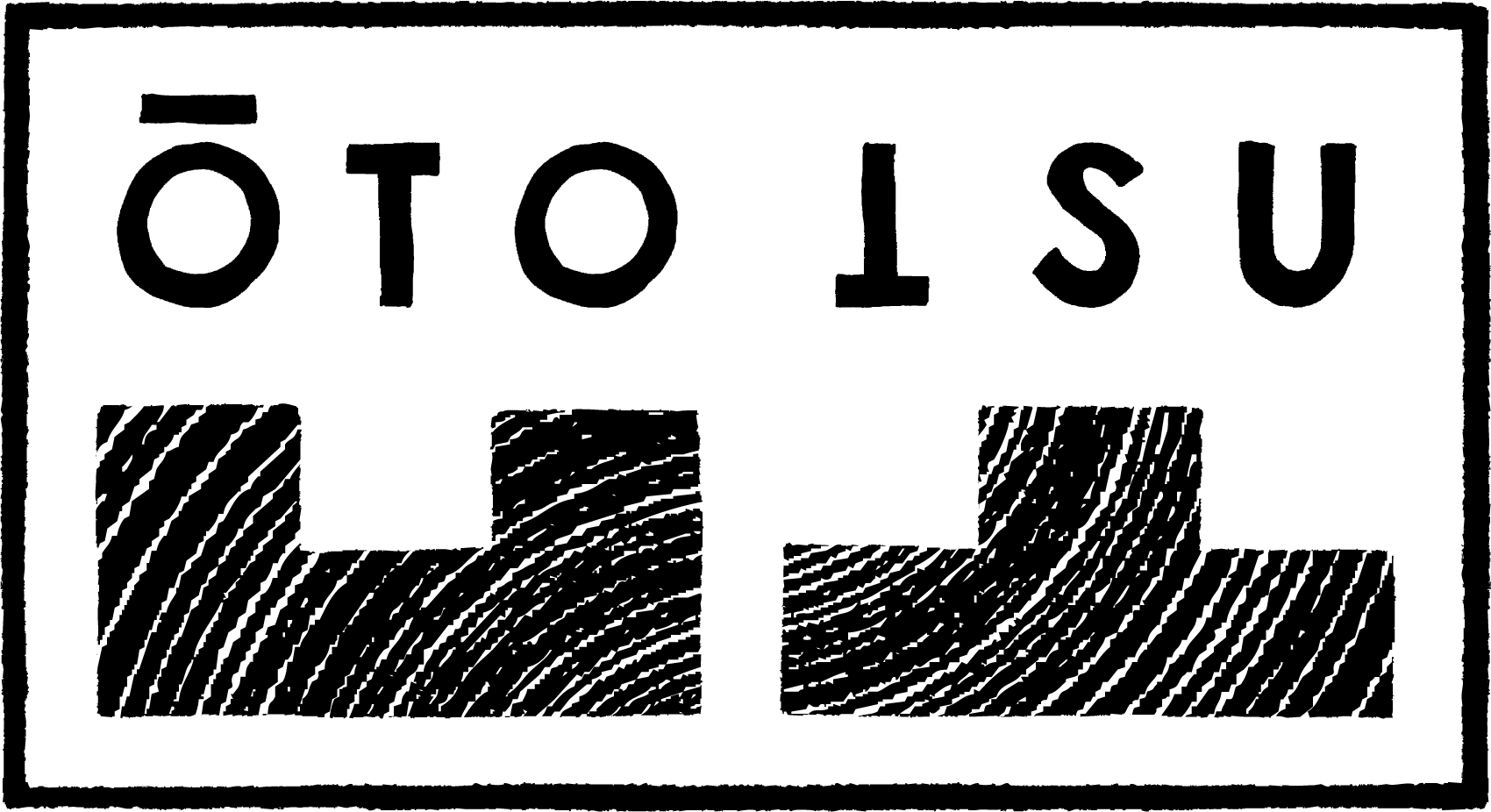2022年8月22日に亡くなったジェイミー・”ブリージー”・ブランチは、彼女が率いたフライ・オア・ダイの特別な音源を残した。ネブラスカ州オマハにあるBemis Center for Contemporary Artsにアーティスト・イン・レジデンスで滞在した際に録音された音源だ。
彼女はアート・センターの何もない空間に、楽器、レコーディング機材、照明セットを入れ、観客も招いたライヴ・レコーディングのアイデアを思い付いた。スタジオでない空間に楽器や機材を持ち込むことも、ステージを一から作ることも困難に思え、当初はフライ・オア・ダイのメンバーも反対する中で、彼女は毅然と実行に移した。オマハ交響楽団から楽器を借りることにもなり、普段は使わないゴング、マリンバ、ティンパニなども用意された。そして、観客も入れたレコーディングは無事に敢行された。
ミキシングを残すのみだったこのレコーディングは、フライ・オア・ダイのメンバーや遺族の協力のもとに、アルバム『Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war))』として完成した。ジェイミー・ブランチにこのアルバムについて尋ねることはできなかったが、『FLY or DIE LIVE』(2021年)のリリース時にCDのライナーノーツのために行ったインタビューをここに転載する。
インタビュー・構成:原 雅明
インタビュー・通訳:バルーチャ・ハシム
編集:三河 真一朗(OTOTSU 編集担当)


2022年8月22日39歳という若さで亡くなった、ダイナミックなジャズ・トランペット奏者/作曲家ジェイミー・ブランチによる、瑞々しく、壮大で、生命力に溢れた遺作となるアルバムが完成。メンバーには、チェリストのレスター・セントルイス、ベーシストのジェイソン・アジェミアン、ドラマーのチャド・テイラーが参加。
Jaimie Branch
Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war))
CD
品番:RINC109(CD)
レーベル : rings / International Anthem
OFFICIAL HP :
Jaimie Branch / Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) – rings (ringstokyo.com)
シカゴのシーンはミュージシャンのエゴよりもサウンドが第一
—— あなたの音楽のバックグラウンドから教えてください。ニューヨーク生まれで、シカゴで育ったそうですね。
ジェイミー・ブランチ:3歳からピアノを習い始めて、兄が10歳年上なんだけど、彼もミュージシャンだった。シカゴに引っ越したのは9歳の時で、学校のバンドでトランペットを演奏し始めた。高校でも音楽を演奏して、18歳の時に音大に進んだ。そのあとは、シカゴのVelvet Loungeというクラブを通して、シカゴのジャズ・シーンで修行を積むようになった。そのクラブのジャム・セッションによく参加するようになったの。
—— シカゴのジャズ・シーンの中で活動することで、演奏技術を磨くことができたということでしょうか?
そう。2004年くらいからシカゴのジャズ・シーンで演奏するようになった。シカゴのフリージャズ・コミュニティにのめり込んで、そこから今、私がやっている音楽を形成することができた。そのシーンが学校教育みたいなものだった。音大には行ったけど、シカゴのシーンの中で学ぶことが一番多かった。他のミュージシャンの作曲方法も参考になった。シカゴのシーンというのは、ミュージシャンのエゴよりも、サウンドが第一。そういう意味で、多くのことを学べるシーン。2004年にフレッド・ロンバーグ・ホルムのライトボックス・オーケストラのメンバーとして演奏したことが、このシーンに入って、たくさんのミュージシャンと交流できる初めてのチャンスになった。シカゴのJazz Record Martというレコード店で4年間働いていたんだけど、そこでもたくさんのことを学んだ。Delmarkの創始者ボブ・ケスターが経営しているお店だった。
——シカゴのジャズ・シーンとニューヨークや他の都市との違いは?
シカゴでは常に音楽が第一。ニューヨークだとアーティストのパーソナリティにもっと焦点が当てられる。でも、シカゴでは音楽性が最も重要視される。もちろん、シカゴとニューヨークの両方でも音楽性は大切だけど、シカゴでは、音楽そのものがシーンを進化させている。そして、シカゴのシーンはとてもオープン。どんなサウンドも受け入れられる。それに、シカゴのミュージシャンは話しかけやすい。シカゴのミュージシャン同士の絆があるし、ファミリー的な感覚がある。
—— ロサンゼルスからニューヨークに行って勉強する多くのジャズ・ミュージシャンは、ニューヨークのシーンがとても保守的で競争率が高いという人が多いですが、ニューヨークに住んでいて、それは感じますか?
私は、そこまでニューヨークのそういう側面について詳しくない。どういう視点で見るかにもよる。 もちろん、ニューヨークにはストレートなジャズ・シーンがあって、その世界でのトップ・プレイヤーはみんなニューヨークに集まっている。でも、その他にもいろいろなシーンがある。ニューヨークのいいところは、あらゆるタイプのシーンがあるということ。もちろん、競争はあるんだろうけど、そのゲームに参加したことがないし、参加しようと思わない。だから、あまりそういうことは心配しない。私はラッキーなのかもしれない。私がニューヨークに引っ越してからやりだしたことは、他のミュージシャンのためにライヴをブッキングすること。私の周りにしっかりとしたコミュニティを作ることで、私の音楽活動も自然とサポートしてくれる人が増えた。どこに引っ越しても、自分の仲間を探すしかないということがわかった。どんなシーンもこっちにはある、コンサバなジャズ・シーンもあるし、クレイジーなノイズ・シーンもあるし、何でもあるの。
—— ニューヨークに引っ越してから、シカゴの仲間のためにライヴをブッキングしてたということですか?
そう。ニック・マッツァレラ・トリオのためにライヴをブッキングしたんだけど、ドラムがフランク・ロザリー、ベースがアントン・ハットウィッチだった。(International Anthemの)スコットが彼らのアルバム(『Ultraviolet』)をリリースしたばかりで、彼らのニューヨークのライヴをブッキングした。私は前座として出演することになって、シカゴ出身のミュージシャンを使ったバンドを組むことにしたの。それでチャド・テイラー、トメカ・リード、ジェイソン・アジェミアンとバンドを組んで、初めてこのメンバーで演奏した。
最初に自分で採譜したトランペット・ソロはマイルス・デイヴィス
—— パンク・バンドをやっていた頃は、どの楽器をやってたんですか?
主にトランペット。ハードコア、パンク、スカ系のバンドだった。子供の頃はギターを演奏していたけど、あまりうまくなかったから、バンドでは演奏しなかった(笑)。
—— あなたの今の音楽はジャズでも、どこかパンク的なエネルギーを感じるので、共通していると思いました。
それは間違いなくある。私のルーツからそういうエネルギーは来ていると思う。
—— トランペットを選んだ理由は教えてください。
ニューヨークに住み続けていれば、私はベーシストになっていたと思う。私はアップライト・ベースをやりたかったんだけど、シカゴに引っ越してから、学校にオーケストラ部がなくて、スクール・バンドしかなかったから、トランペットかサックスを選ぶしかなかった。どちらかを演奏したかったんだけど、家族とディナーをレストランで食べた時に、私がお父さんの赤ワインをサックスの楽譜にこぼしてしまって、それでトランペットをやることにした(笑)。
—— そういう理由で(笑)?
そう。とにかく、どっちかの楽器であればよかった。あと、サックスは私にはちょっと重たかった(笑)。でも、私の兄二人、父親もトランペットをやってたし、私のあとに妹もトランペットを演奏した。9歳からトランペットを習い始めたんだけど、12歳の時に、兄から最初のトランペットをプレゼントでもらった。
——トランペットを習得する上で、あなたに影響を与えた人物や音楽は?
影響されたトランペット奏者については、まずはロブ・マズレク。高校生の時に、シカゴ・アンダーグラウンド・デュオやアイソトープ 217°を聴いて、すごく衝撃を受けたのを覚えてる。最初に自分で採譜したトランペット・ソロは、マイルス・デイヴィスの『’58 Sessions』からだった。曲は“On Green Dolphin Street”だったと思う。だから、マイルスにも多大な影響を受けた。ルイ・アームストロングも大好き。高校生の頃は、図書館からジャズ・レコードを年代順にたくさん借りて聴いてた。ニューオーリンズのビッグ・バンド、キング・オリヴァー、ルイ・アームストロングから聴き始めた。そこから、トランペットのソロだけをカセットテープに録音して自分でまとめてた。当時は、そういうソロをまだ自分で演奏できるレベルではなかったけど、チェット・ベイカーくらいは演奏できた。そして、いろいろなトランペット奏者のソロを採譜して研究した。ウディ・ショウにも多大な影響を受けた。ブッカー・リトルやドン・チェリーも私にとってヒーロー。高校1年か2年の時に、オーネット・コールマンの『The Sound of Jazz To Come』を聴いて、新譜だと思い込んでた(笑)。1999年に聴いたんだけど、1959年の作品だった。ルールに囚われないサウンドに感銘を受けた。ジョン・コルトレーン後期の作品も聴いて、人生が変わった。
—— 割とアバンギャルドなジャズに惹かれたんですか?
そう。当時、オーネット・コールマンの『The Sound of Jazz To Come』とダニーロ・ペレスの『Motherland』をほぼ毎日聴いてた。ストレートなジャズも聞いてたけど、シカゴのジャズの歴史を知るようになって、完全にフリージャズの世界にのめり込んでいった。
—— 女性のトランペット奏者は比較的少ないと思いますが、ジャズの世界で差別はありましたか?
シカゴのジャズ・シーンはいつでも私を歓迎してくれた。だから、女性であることは問題にならなかった。ただ、どんなミュージシャンも常に自信を持つことは難しいから、答えづらい質問でもある。私は女性ではあるし、女性である以外の経験をしたことがないから、比較できるものがない。女性だからといって、チャンスが少なかったかはわからない。ただ、私は活動し始めた最初の頃から、常に自分のバンドを組んでた。ずっとバンド・リーダーをやってきたし、自分でライヴをブッキングしてきた。そういう意味で、自分でチャンスを生み出すことができた。でも、女性だということで嫌な態度をする男たちとは、どっちみち一緒に演奏したくもない。だから、女性蔑視的なことを経験したことはあるけど、だからと言って、自分の音楽、演奏の妨げになったことはない。
—— シカゴのシーンには、どのくらいの時期、関わっていましたか? また、そこから学んだことは?
10年くらいかな。シカゴのジャズ・シーンのアーティストは、リスクをとる人が多くて、それが刺激になった。あと、このシーンのジャズ・ミュージシャンは、普通の楽譜だけではなく、グラフィック・スコアを使う人が多い。私も、普通の楽譜ではなく、楽譜の中にイラストを取り入れたり、テキストで指示を書き込んだり、図形楽譜も取り入れている。音というのは、非常に三次元的なもの。それを表現している。
—— グラフィック・スコアはどこから学びましたか?
音大時代で知ったと思うけど、AACMのメンバーだったムワタ・ボウデン(Mwata Bowden)が様々なタイプのグラフィック・スコアを見せてくれた。その時に初めて、完全な図形楽譜の作品を演奏させてもらった。ニコール・ミッチェルとも演奏したことがあるけど、彼女もグラフィック・スコアや図形楽譜について教えてくれた。彼女は、インプロヴァイザーのために、どのような楽譜を書けばいいかということを詳しく教えてくれた。
—— 絵を楽譜に取り入れることで、より表現力が高まるのでしょうか?
そう。「こう演奏しなさい」と明確に指示をしてないわけだからね。もっとアブストラクトな楽譜だから、よりオープンな演奏が可能になる。
—— フライ・オア・ダイ(Fly or Die)の録音には、チャド・テイラーの他に、トータスのダン・ビットニーも参加していますね。シカゴ・アンダーグラウンドやトータスの音楽から影響は受けましたか?
もちろん! トータス、アイソトープ 217°、タウン・アンド・カントリーなども大好きだった。ジョシュア・エイブラムスが参加したバンドはなんでも大好き。彼が出演するライヴはだいたい見に行ったの(笑)。Thrill Jockey、Touch and Go、Matador、Quarterstickなどのレーベルのものも好きだった。
「生命に近づいているか、死に近づいているか」
—— あなたは、 New England Conservatory of MusicやTowson Universityで学んでいますね。そこで学んだことを教えてください。
大学生だった頃は、練習することに没頭できたのが良かった。たくさん練習できたし、NECでは、スティーヴ・レイシーから1学期学ぶことができて、それは素晴らしい体験だった。スティーヴ・レイシーが亡くなってから、ギタリストのジョー・モリスに師事することにした。その経験から、自分のサウンドを掘り下げることができた。でも、最も成長できたのは、学校の外だった。学校は、閉ざされた環境だけど、現実の世界で演奏するのとは違う。たくさんライヴの現場を経験しないと成長できないわけだけど、シカゴでは1週間に何度もライヴが出来るから、そういう意味で成長しやすい環境だった。だから、クラブや様々な現場を踏むことで、成長することができた。ただ大学では、時間をかけて、楽器の演奏技術を磨くことはできた。大学生の頃は、バイトはしていたけど、フルタイムで働いていなかったから、練習に集中しやすかった。卒業すると、仕事しながら演奏しないといけないから、環境が変わる。だから、その前に演奏技術を磨くことができてラッキーだった。
—— 現在の活動拠点はニューヨークのブルックリンですね。シカゴにルーツがあるのに、なぜニューヨークに移ったのでしょうか?
Towson Universityはボルチモアにあるんだけど、そこに通うためにシカゴを離れた。結局中退したんだけど、学校を離れてから、シカゴに戻るか、ニューヨークに行くという選択肢があった。ニューヨークは、9歳以来住んでいなかった。しばらく新しい環境に身を置いてみようと思って、ニューヨークに行った。でも、最終的にいいチョイスだった。
—— ソロ・デビュー・アルバム『Fly or Die』はどんな意図を持って制作されたのですか?
このアルバムは、ジェイミー・ブランチの人生の歴史を凝縮した作品。ダンサブルな要素、ヘヴィーなサウンドを含む組曲のような作品。最初から最後まで演奏が繋がっていて、そういうコンセプトのもとに制作した。一つ一つの個別の楽曲を作るのではなく、アルバム全体が一つのコンポジション。それを様々なテーマに分けて、それが曲になった。一気に作曲した作品だった。私のイントロでありながら、私の歴史を反映した作品。シカゴにいる時代から、私はこういう方向性で作曲していた。チェロがサウンドのポイントになっているけど、チェロのために作曲するのが好き。あと、このメンバーと作品を作るのが大好き。
—— フライ・オア・ダイは、その後のあなたのリリースに常に使われていますが、これはグループ名と言ってもいいのでしょうか?
そう、これはグループ名でありながら、アルバムのタイトルでもあるし、曲名でもある(笑)。この名前は、「生命に近づいているか、死に近づいているか」という意味が込められている。「飛び立つのか、死に向かうのか」という意味。「飛ぶ」ことを選ぼう、ということを自分に言い聞かせるための名前でもある(笑)。カルテットの名義がフライ・オア・ダイでもある。
—— カルテットのメンバーは、どのように選ばれたのでしょうか? チェロとアップライトベースの両方がグループにいるのは珍しいですよね。
チャド・テイラーは素晴らしいシカゴのドラマー。このバンドを組んだ時に、初めて彼に電話をしたんだけど、とても親切だった。優れたドラマー、パーカッショニストなだけではなく、ムビラ(カリンバ)奏者としても素晴らしい。ジンバブエのムビラ奏者の師匠から演奏を学んでるの。彼は本当に奥深いミュージシャン。ある意味、ステージに立っている時は、彼がバンドのリーダーになっている。彼がしっかりと土台を作ってくれるから、私は自由に飛び回ることができる(笑)。ジェイソン・アジェミアンとは、2004年、シカゴ時代から一緒に演奏している旧友。私は、ハイライフ、フォークローズ、フー・ケアーズ・ハウ・ロング・ユー・シンクなど、彼のバンドにも参加してきた。ジェイソンとは長年演奏しているけど、とにかく彼のベース・サウンドが大好き。彼のサウンドはとても壮大で、とても革新的な演奏をベースでやっている。弓弾きも素晴らしいし、とても巧みに動き回る演奏ができる。トメカがソロ活動で忙しくなって、その後に入った最新のメンバーがレスター・セント・ルイス。彼はチェロで、現代音楽的な要素をこのバンドに取り入れてくれる。彼が最年少のメンバーで、ニューヨーク・クィーンズ出身。バンドメンバー全員のパーソナリティの相性がいいし、みんな仲がいいから、一緒にツアーしやすい。私は昔からチェロのために作曲をしてきたけど、この楽器が大好き。とてもフレキシブルな楽器で、リズム・セクション、ストリングス・セクションの一員にもなれるけど、ソリストとしても演奏できる。確かに、ベースと似た音域なんだけど、ベースの音域をさらに広げてくれる。だからある意味、ベースとチェロが合体して一つの楽器になっている。
—— 通常ジャズのバンドでは、ピアノがコードを演奏するわけですが、あなたのバンドにそれがないのがユニークですね。
そう、この編成にすることで、ハーモニーをはっきり演奏するより、ほのめかすような方法で演奏することができる。とてもオープンに演奏できる。私が演奏したピッチが、ジェイソンとレスターの演奏のコンテキストを変えることができる。そういう意味で、制限されないから、とても面白い。
—— では、意識的にピアノなどは入れなかったということですか?
このシカゴ出身のメンバーを意識して作曲していたから、こういう編成になった。たまたまその時にシカゴ出身のピアニストがニューヨークに来ていれば、その人もメンバーになっていたかもしれない。でも、私は身近にいるメンバーを意識して曲作りをしていたから、それがバンドのサウンドの特徴となった。トメカが辞めてから、ヴィブラフォン奏者も試しに入れてみたんだけど、やっぱりチェロがこのバンドのサウンドの特徴になっていることに気づかされた。だから、それ以降もずっとチェロを意識して作曲している。
緊張するし、怖いからこそ、歌うことが好き
—— 『FLY or DIE II: bird dogs of paradise』は、『Fly or Die』を踏まえて、どのように制作されたアルバムなのでしょうか?
『Fly or Die』は、私の歴史を振り返る作品で、『FLY or DIE II: bird dogs of paradise』は2018年に起きたことを表現したアルバム。ツアー中に作曲した曲で構成されていて、ツアーが終わってからレコーディングした。このアルバムでは力強い政治的メッセージを打ち出したかったたから、初めてこのアルバムで歌った。12分の曲“Prayer for Amerikkka”で、初めて歌った。声と歌詞を使う場合は、はっきりメッセージを聞き取れるわけだから、その手法を取り入れた。『FLY or DIE II』も組曲的な作曲方法でアプローチしたんだけど、“nuevo roquero estereo”、“simple silver surfer”みたいな曲を入れることで、最初の組曲的な構成とはちょっと違う仕上がりになった。
—— なぜ、ダイレクトなメッセージを打ち出したくなったのでしょうか?
ファーストをレコーディングした時、アメリカ発の女性の大統領が決まりそうだったけど、トランプが大統領になってしまった。トランプの人種差別的発言が、アメリカの多くの人種差別者を奮い立たせた。それに、アメリカ中で警察による暴行事件が横行した。これは昔からある問題だけど、今はそういう事件がカメラで撮影されるようになったから、誰も目を背けることができなくなったし、直面せざるをえない状況になった。白人のアメリカ人が変化しなければいけない状況になった。そういう気持ちが全て『FLY or DIE II』に込められている。母親がソーシャル・ワーカーだったから、“Prayer for Amerikkka”の後半は、母親が助けようとしていた移民の家族を題材にしていた。その家族は、亡命するためにアメリカにやってきたんだけど、その家族の娘が国境で入国拒否されて、母親と息子二人だけがシカゴに入った。娘が国外退去させられて、またアメリカに戻ってこようとした時に、国境で3年間も収容されることになった。そのストーリーをあの曲の中で描写した。

—— あの曲の歌詞に登場する19歳の女性というのは、その家族の娘のことなんですね。
その通り。『FLY or DIE II』のライナーノーツでも、そのことについて書いた。
—— ヴォーカルの表現で意識していることはありますか?
歌うことに対しては、緊張するし、怖いからこそ、歌うことが好き(笑)。歌うとアドレナリンが流れるし、パフォーマンスのそういうところが楽しい。歌うことで、新しいことに挑戦しているという実感があったし、そうすることで成長につながる。だから歌を取りれることは自然なプロセスだったけど、同時に恐怖も伴った(笑)。歌うことは、心の内を露呈しなければいけない。私は38歳だけど、トランペットは29年も演奏してる。歌はステージであまり歌ったことがなかったから、歌う時は間違いなく心臓がバクバクする。
——『FLY or DIE LIVE』に参加した面々が、いまのあなたのバンド・メンバーと言っていいのでしょうか?
さっき話したレスター、ジェイソン、チャドがこのアルバムのメンバーで、私のグループのコア・メンバー。
—— プレスリリースによると、この作品のライヴの印象は個人的にそんなに良くなかった、と書いてありましたが、そういう印象が残っていたから、長い間ライヴ音源を聞こうとしなかったのでしょうか?
どちらかというと、あまり自分の演奏を聞きたくないという気持ちだった。自分のライヴの演奏を聴いて、がっくりしたくなかった、という気持ちもあった。パンデミック中は、ちょっと前までは世界中をツアーして最高の気分だったのに、今はベッドルームにこもっている、という状態で少し落ち込んでた。だから、自分の演奏を聴きたい気持ちじゃなかった。あのライヴを振り返った時に、自分が素晴らしい演奏ができたという記憶はなかったんだけど、逆に、それはすごくいいライヴだったという啓示でもあった。なぜかというと、演奏している最中は、自分の演奏を客観的にジャッジすることができないから。ライヴがすごくうまくいったという記憶があったとしても、聴き返した時に、その記憶を超えないこともある。ライヴ中に演奏している時に、自分の体から一歩踏み出して、客観的に自分を見ているということは、演奏に没頭していないことになる。ということは、ゾーンに入って演奏できていないことになる。だから、この作品については、ライヴの記憶がそんなに良くなかったけど、聴き返したときはすごくよかった。
—— 完全に演奏に没頭して、ゾーンに入っていたから、逆にそのライヴの記憶がなかった、ということでもあるんですね。
その通り。
声もトランペットも両方ともジェイミー・ブランチという楽器の一部
—— 楽曲は、どのように作曲されるのでしょうか? 制作のプロセスを教えてください。
この作品の曲は、最初は耳を頼りに作ってた。実際に楽譜を持ち込んだのは、ロンドンのコンサートの前日だった。ロンドンの前日に大きなリハーサルをやって、組曲を全て演奏して録音した。バンドのレコーディングをしてから、1日オーバーダブをレコーディングした。“twenty-three n me, jupiter redux”、“love song”は古い曲なんだけど、それも作品に入れたかった。“twenty-three n me”は23拍子の曲だから、こういうタイトルだった。チャドはいとも簡単にそのリズムを叩けた。“love song”は、2005年くらいに書いた曲だったけど、“Prayer for Amerikkka”では歌ってたから、“love song”を入れることで収まりが良くなった。ツアー中に、休みの日があると作曲したりしていた。私の作曲方法は、通常はしばらくインプロヴィゼーションをして、その中からアイデアを見つける。あとは、携帯のボイスメモ機能にアイデアを入れていくこともある。ムビラを使った曲は、チャドの演奏を中心に、みんなが演奏を追加していって、バンドが一つの楽器になった。それは、みんなでスタジオの中で見つけた方向性だった。“Prayer for Amerikkka”は完成するのに一番時間がかかった。インストはスタジオの中で作って、満足する歌詞が書けるまですごく時間をかけた。レコーディングをする心の準備ができたら、シカゴで2019年1月にレコーディングした。だから、アルバムは2018年11月にレコーディングして、ボーカルだけは2019年1月にレコーディングした。
—— チューリッヒのライヴ会場も素晴らしかったようですね。
とてもハイな雰囲気だった(笑)。確かソールドアウトだったから、観客は満杯だった。1月だったから、外は寒かったけど、みんなは中で汗をかきながら演奏してた。このライヴの前日はオスロでライヴをやって、レスターのガールフレンドがライヴを見に来てた。だから、みんな気分はよかった。
—— “Prayer for Amerikkka”は、ロックダウンやBLMが本格化する前の録音だったのに、メッセージが今も通用する内容ですね。
あの曲に込めたメッセージは、間違いなく今の状況にピッタリはまってる。あの曲は様々なフラストレーション、怒りを表現しているけど、とにかく世界中の人に目を覚ましてほしいという気持ちが込められている。今のアメリカの政権は民主党が握っていて、もっと良心的だと言われているかもしれないけど、本当の意味での変化はまだ起きていない。政治改革では、ある程度の変化しか得られない。警察のシステムを完全に考え直さなければいけない。警察は、奴隷を捕まえる人の延長線上のシステム。システムの土台がそこにあるということは、間違っている。この国では、大きな移民の問題があって、国境の収容所には今もたくさんの移民の子供たちが収容されている。もっとハッピーな顔の大統領になったから、状況を受け入れやすくしているかもしれないけど、問題はすべてまだ解決されていない。この国を動かしているのは金だから、人を第一に考えるシステムにならなければ、問題は起き続ける。あと、こういうシステムとは別に、人間同士がもっとお互いに優しくするべきだと思う。もちろん、堕落した権力者の前では、強く立ち上がる必要があるけど。“Prayer for Amerikkka”はパート1と2に分けられていて、二つの違う状況を描写している。でも最終的に一つのメッセージになっている。
—— あの曲での叫び方にはパンク的なものを感じました。
以前パンク・バンドを経験したことの影響もあるかもしれないけど、今の世の中の状況に一番影響されている。シカゴのミュージシャンは、一つのサウンドを表現するために、いろいろな作曲方法ができる。声というのは、トランペットよりも直接的なメッセージを表現出来る楽器だけど、私にとっては、両方ともジェイミー・ブランチという楽器の一部と捉えている。他のプロジェクトではシンセやエレクトロニクスを演奏することもあるけど、それも同じく私のサウンドの一部。
—— “twenty-three n me, jupiter redux”というタイトルにはどういう意味があるのでしょうか?
自分のDNAを調べてくれる23 and Meという会社があるんだけど、それが由来になっている。DNAを送ると、自分の人種のルーツを調べてくれる会社。それをもじったタイトル。シンセの音を入れたんだけど、それがエイリアンの声に聞こえた。フリージャズのバンドが、エイリアン・ディスコで演奏しているようなイメージを連想した。それが“jupiter redux”の由来。曲の最後で、地球に戻ってくるようなサウンドになってる。この曲のリズムリズムが4/4と23拍子を行き来していることも、タイトルに反映している。
—— “whales”はクジラのようなストリングスの音が入っていて面白かったです。
ストリングスであの音を作って、チャドがブレイクビーツを叩いてる。本当にクジラの鳴き声に聞こえるから、このタイトルにした。メンバーに、「蜂のような音を出してみて」とか、そういう指示を出すことがある(笑)。
—— “simple silver surfer”はどういうイメージですか?
シルバー・サーファーというコミックのキャラクターがいるんだけど、そのサーファーが宙に浮いているようなサウンドだから、このタイトルにした。でも、これは「シンプルな」シルバー・サーファー(笑)。
—— 自由に受け止めて欲しいわけですね。
そう。これはダンス・ミュージックなの。“nuevo roquero estereo”は「ニュー・ロック・ステレオ」という意味。タイトルを通して、あまり深いメッセージを伝えようとしているわけじゃない。ほとんどのタイトルは、サウンドを反映していたり、面白い響きの言葉を選んでいるだけ。
—— シカゴ、ニューヨーク、ロンドン、チューリッヒと、あなたは様々な場所での演奏からアルバムを作って来ましたが、場所を移動することに、意義を見出していますか?
アルバムをレコーディングする場所が、サウンドに反映される。ファーストは、ブルックリンにある妹のアパートでレコーディングした。セカンドは、ロンドンのTotal Refreshment Centerでレコーディングされた。そこは、アメリカ以外ではフライ・オア・ダイの初のライヴ会場だった。そういう意味であの場所は私にとって特別だった。そこはライヴを開催しなくなったんだけど、スタジオはまだあるから、ロンドンに戻った時は、そこを拠点に使いながら、Cafe Otoでライヴをやった。チューリッヒは、スイスのオーディエンスが一緒に歌っているのが聞こえる。ヨーロッパではそれは割と稀なことだから、他の都市とは違った。ヨーロッパのオーディエンスは、アメリカのオーディエンスより少し大人しい。場所によっては、ライヴの前半は、オーディエンスを盛り上げるためにこっちは頑張ってるんだけど、最後ではみんなが爆発して盛り上がってくれることがある。オーディエンスが大人しい時は、必ずしも楽しんでいないわけじゃなくて、敬意を込めて静かだったりすることがわかった。それは私も学ばないといけなくて、あまり心配しないようになった(笑)。ライヴの最初の方で、「私たちは演奏し始めると最後までずっと演奏し続けるから、自由に拍手したり声を出してね」と言うようにしている。シカゴは私にとってホームだから、シカゴでライヴをやるのは大好き。ロサンゼルス、ニューヨークのライヴも素晴らしかった。ノリのいいオーディエンスは大好き。音大のジャズというのは、静かに座ってライヴを見ないといけなくて、私にとってはすごく退屈。ジャズというのは、本来そういう音楽じゃない。ジャズはもともとダンスミュージックだからね。
—— フライ・オア・ダイの今後と、これからの予定を教えてください。
フライ・オア・ダイは、私にとっての作曲の表現手段だし、このプレイヤーのために作曲をするのが大好き。だから、しばらくはこの形態で続けていきたい。今新しい曲を作っているし、他のバンドもやっている。まだレコーディングをしていないトリオが2つあって、今年か来年にはレコーディングしたいと思ってる。両方のトリオにルーク・スチュアートというベーシストが参加している。ジェイミー・ブランチ・トリオのドラマーはマイク・プライド。もう一つのトリオは、イレヴァーシブル・エンタングルメンツ(Irreversible Entanglements)のチェサー・ホームスがドラマー。このトリオの名前が決まってないけど、よくブルックリンでライヴをやってた。アンテローパーは、私のエレクトロニック・ミュージックのプロジェクトで、ジェイソン・ナザリーとやっているユニット。2022年5月に新作をリリースすると思う。パンデミック中に、たくさんのソロの曲を作ってた。だから、これからソロ作品の曲をレコーディングすることになると思う。トランペット、エレクトロニクス、ボーカルを使った作品になる予定。
—— 今回、初めて、日本盤としてあなたのアルバムが紹介されます。日本のリスナーへのメッセージをお願いします。
ノリ・タナカ(田中徳崇)という日本人のドラマーがシカゴにいたんだけど、ジェイソン・アジェミアンと一緒に彼とよく演奏していた。彼は素晴らしいドラマーで、本当にいい人。Jazz Record Martで働いていた頃は、日本でプレスされたジャズのレコードを見ることが多くて、作りが美しくていつも感動してた。International Anthemは日本のジャズのレコードにインスパイアされて、帯を取り入れるようになったの。日本にはまだ行ったことがないんだけど、日本人のレコードコレクターやDJの友達がたくさんいるし、日本人は音楽を深く愛しているのがわかるから、早く日本に行ってライヴをやってみたい。
RELEASE INFORMATION

2022年8月22日39歳という若さで亡くなった、ダイナミックなジャズ・トランペット奏者/作曲家ジェイミー・ブランチによる、瑞々しく、壮大で、生命力に溢れた遺作となるアルバムが完成。メンバーには、チェリストのレスター・セントルイス、ベーシストのジェイソン・アジェミアン、ドラマーのチャド・テイラーが参加。
Jaimie Branch
Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war))
CD
品番:RINC109(CD)
レーベル : rings / International Anthem
OFFICIAL HP :
Jaimie Branch / Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) – rings (ringstokyo.com)